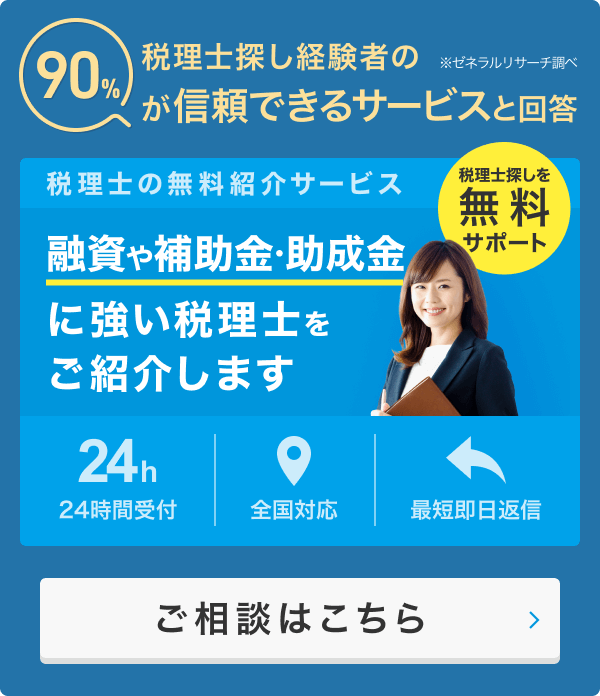補助金とは?活用するために知っておくべき補助金制度の基本
補助金とは、国や地方公共団体などから支給される支援金です。基本的には返済が不要のため、事業などを推し進めるのに有効な資金調達のひとつといえるでしょう。
このページでは補助金とはどのようなものか、受給するための手続きなどについて解説します。
※一般的な補助金について説明しています。制度によってはあてはまらない場合もあるので、活用を検討する際には各制度の詳細を確認してください
目次
補助金とは
起業を考えている人や会社設立から間もない経営者にとって、資金調達や資金繰りは重大な関心事のひとつでではないでしょうか。
補助金は資金調達の有効な手段のひとつであり、以下のような特徴があります。
多くの補助金は返済が不要
融資や借入では当然返済が必要ですが、ほとんどの補助金は返済が不要です。
ただし中には、補助金を受け取って行った事業で収益が生じた場合には、補助金交付額を限度として、収益金の一部を返済するよう定めている補助金もありますので、事前に確認するようにしましょう。
補助金は主に「後払い」方式
融資や借入の場合、審査を通過すれば入金されます。受給した金額は、その融資や借入の条件に沿った範囲内であれば、ある程度使いみちは自由です。
しかし補助金の場合は、原則として「後払い」方式となっています。例えば、総額300万円かかる事業で1/3の補助金を受け取る場合、まず先に自社のお金で300万円を支出する必要があり、対象事業を実施したあとに、精算払いというかたちで補助金が支払われます。
補助金の使いみちについても、指定される対象事業に限られるためご注意ください。
補助金は原則的には課税対象
補助金は、会計上は「収入」とみなされるため、原則として課税対象となります。ただし、サービスなどを提供して受け取った対価ではないため、消費税は課されません。
「助成金」とはどう違う?
助成金も補助金同様、国や自治体から支給される返済不要の資金調達制度です。「補助金」は制度ごとに予算や採択件数、公募期間が決められていて、審査を通過しないと受給できないものが多い一方、「助成金」は通年申請でき、要件を満たせば受給できるものが多いです。
ただし、これらの違いは明確に区別されているわけではありません。助成金と補助金という名称であっても、前述した条件に必ずしも当てはまるとは限らないので、各制度の内容をよく理解したうえで、活用を検討するようにしましょう。
補助金を利用するメリットとデメリット
メリット
補助金で資金調達をすることで、会社の経営が安定したり、積極的な人材採用・設備投資などによる事業の拡大につながります。制度によっては専門家のアドバイスや事業計画のブラッシュアップも受けるため、今後の事業運営の参考にもなるでしょう。
デメリット
補助金を受け取るにはそれぞれの制度の条件に当てはまらなければなりません。申し込み時の審査で採択を得たものの、受給申請時に受給要件が満たされなかったために補助金を受け取れなかったという例もあります。
また、補助金の対象になった場合は、書類作成のほか、事業後に検査を受けたり、経費関連書類を一定期間保管するなど、各種手続きや手間がかかるというデメリットもあります。
補助金の効率的な探し方
補助金は経済産業省、厚生労働省、農林水産省やその他の政府機関・地方公共団体などから数多く出されています。そのためどのような補助金があり、そのうちどれを利用すべきかを1つずつ当該官庁のホームページなどで調べるのはとても非効率です。
補助金や助成金についてまとめている中小企業庁のサイトや情報サイトを利用するのが効率的です。また資金調達に強い専門家に相談するのもよいでしょう。
例えば以下の情報サイトでは、地域や利用目的、支援制度別に検索できるほか、任意のキーワードで補助金を検索することもできます。
補助金の申請から受給までの流れ
補助金の申請から受給までの大まかな流れを確認しましょう。
STEP1 申請書類の作成・提出
申請したい補助金の募集要項・申請書をダウンロードし、必要な内容を記入して事務局に提出します。公募期間が数週間〜1か月程度と決められているものが多いため、申請したい補助金についてあらかじめ調べておく必要があります。
STEP2 審査・採択の決定
審査は書面によって採択される場合と、現地調査やプレゼンなどが必要になる場合があります。選考の結果、補助金が交付される事業者に選ばれたら、案内に従って交付申請書を事務局に提出します。
STEP3 交付の決定・事業の実施
交付申請書を提出したあと、交付が決定したら対象事業を開始します。実施する事業は交付決定された内容に限られます。
制度によっては、事業の途中に事務局によって中間審査が行われることもあります。普段から補助金の対象となる経費の領収書や証拠書類をすべて保管し、審査を円滑に進められるようにしておきましょう。
STEP4 事業実績の報告・補助金の交付
補助事業が終了したら、実施した事業の内容や経費について事務局に報告します。事前の申請通りに適切に実施されたことが確認されると、補助を受けられる金額が確定し、確定通知書が郵送されてきます。通知書に記載された金額の請求書を発行し、指定した口座に補助金が入金されます。
なお、補助金の交付後も一定期間は定期的に事業の遂行状況報告が必要になったり、補助事業終了後5年間は、中小企業庁や会計検査院の検査が行われる可能性があります。
そのため、補助金の対象となる領収書など経費の支払いがわかる書類は5年間保管しておきましょう。
※制度によってはこれらの流れに当てはまらないこともあります。各制度の公募要件をよく確認しましょう
補助金申請の採択率と成功のポイント
一般的に、補助金は申請すればもらえるのではなく、多くの申請者の中から選考・採択されるため、その競争率は高くなります。採択されるためには、魅力的な申請書・事業計画書を作成することが重要です。
また、補助金や助成金の申請には、「認定支援機関」による計画書の確認などを要件としているものもあります。認定支援機関とは、経済産業省によって専門知識、実務経験が一定レベル以上あると認定された税理士や公認会計士、金融機関などのことです。
ですので、認定支援機関に認定されている専門家に協力を得ることも検討するとよいでしょう。
補助金申請を依頼できる専門家と費用相場
税理士の中には、創業支援や資金調達に力を入れている事務所も多くあります。税理士に依頼することで、申請書類や手続きの正確さはもちろん、補助金にまつわる税務・会計処理を適切に行ってもらえます。
他に補助金の申請を取り扱う専門家には、中小企業診断士・社会保険労務士や、資金調達を扱うコンサルタントも挙げられますが、前述した「認定支援機関」の支援が欠かせない補助金の場合は、認定支援機関に認定されているかどうかを確認しておきましょう。
専門家に依頼する場合の費用相場は、着手金として3〜5万円程度の料金を事前支払うケースや、成功報酬として受給金額の10〜15%程度がかかるケースが多いようです。
初回相談や費用見積は無料で対応してくれる専門家も多いので、無料見積もりを利用した上で、実務の依頼を検討するとよいでしょう。
税理士選びでお悩みの方へ
「どんな税理士がいいの?」「もっと親身な税理士に変更したい」など税理士選びでお困りの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。
また、予算が気になる場合は<税理士の費用・料金相場>を参考に、おおよその料金を把握しておくとよいでしょう。
税理士選びでお悩みなら税理士ドットコムにご相談ください

※ゼネラルリサーチ調べ