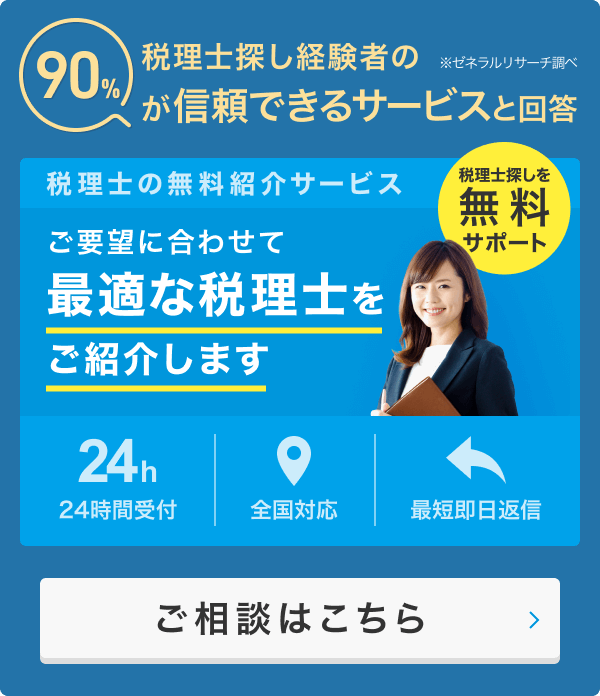年末調整を税理士に依頼するメリットや費用実例をご紹介します
年末調整は年に一度の業務とはいえ、手間と時間がかかります。
そこで検討したいので年末調整のアウトソーシングですが、年末調整を代行できるのは税理士のみと決められていることをご存知でしょうか。税理士資格のない社労士など他の専門家では通常対応できないのです。
そこで、年末調整を税理士にアウトソーシングするメリットをはじめ、報酬相場や費用実例を紹介します。
目次
年末調整の代行を依頼できるのは「税理士」のみ
年末調整をアウトソーシングする際、誰に頼むべきかご存知でしょうか?
年末調整は「給与計算」と密接する手続きです。給与計算には社会保険関係の手続きが伴うため、かつては社会保険労務士が年末調整を行っているケースがありました。
ところが2002年(平成14年)、日本税理士連合会と全国社会保険労務士会連合会により、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する
という確認書が設けられました。
つまり、社労士が年末調整を行うことは税理士法違反となるという見解で両会一致したのです。そのため、税理士資格のない他の専門家は年末調整の代行を行うことはできないことになっています。
年末調整の税理士費用は「基本料金1万〜3万円」程度
年末調整の料金は、従業員1名あたりいくらという算出の仕方が一般的です。
以下のように基本料金を設定して、ある一定の社員数までは基本料金内で収まり、超えた分に関しては1名あたりいくらという従量制となります。
- 基本料金:1万〜3万円(社員10〜15名までは基本料金内で対応)
- 基本料金内以降、1名増えるごとに+1,000円〜3,000円
これらの料金に、「源泉徴収票や給与支払報告書、法定調書合計表、支払調書」などの作成も含まれている場合もありますが、別途料金が発生する場合がありますので、税理士に事前に確認しましょう。
また、税理士によっては年末調整の料金を顧問料に含むというケースもあります。対応する人数(従業員数)が多ければ、人数に応じて別途料金が発生することもありますが、小規模であれば年末調整の代行をきっかけに顧問契約を視野に入れても良いかもしれません。
実際いくら?年末調整を税理士に依頼したお客様の実例
それでは税理士ドットコムに寄せられた相談を元に、年末調整業務を税理士に依頼された方の料金実例を紹介します。
実例1 東京都・人材派遣業を営むA社(売上高:9億5000万円、従業員数:45名)
税理士 報酬金額(スポット契約):11万2500円
法人の経理担当の方より、既に顧問税理士はいるものの、年末調整の料金で折り合いがつかないとのことで年末調整業務だけをお願いできる税理士を探している、とご相談いただいたケースです。
従業員1人あたり年末調整等2500円で契約に至りました。会社があるエリアからは距離が離れた税理士事務所でしたが、オンラインツールでやり取りでき、即時レスポンスがもらえることが決め手となったようです。
実例2 千葉県・建設業を営むB社(売上高:8000万円、従業員数:10数名)
税理士 報酬金額(顧問契約): 22万5000円
「記帳は自社で行なっているものの、税務に明るくないため税理士にサポートしてほしい」とのことで、弊社の税理士紹介サービスにお申し込みいただきました。
当初は年末調整のみご依頼の意向でしたが、年々売り上げが上がってきて従業員も増えてきていることもあり、最終的には顧問という形で決算などもおまかせできる税理士とご契約されました。
実例3 岐阜県・保険代理業を営むC社(売上高:500万円、従業員数:2名)
税理士 報酬金額(顧問契約):28万0000円
ご契約中の税理士事務所の料金と対応面に不満があるため、費用をおさえつつ親身に相談に乗ってくれる税理士を見つけたいとのご希望でした。
複数の事務所を面談を行い、面談時の説明が丁寧で疑問点に柔軟に答えてくれた税理士と、年末調整・給与計算・決算申告込みで顧問契約されました。
年末調整を税理士に依頼する3つのメリット
以上のように、税理士に依頼すると一定の費用がかかってしまうのはネックですが、それ以上にメリットが受けられる可能性があるのです。具体的には以下のようなメリットがあります。
- 年末調整にかかる手間と時間を削減できる
- 法改正に対応し正確な作業ができる
- 追加人員を雇用するよりコストが抑えられる
メリット1.年末調整にかかる手間と時間を削減できる
年末は賞与の計算や年内の売上計上など、ほかの業務が立て込む時期です。そのため年末調整を税理士に依頼することで、その手間と時間を省くことができます。
経営者であれば本業や別の業務に時間を割けるほか、担当者であれば膨大な事務的負担を大幅に軽減することができます。
メリット2.法改正に対応し正確な作業ができる
慣れている経理担当者であれば、年末調整へ問題なく対応できますが、経理担当者がいない会社や初めて人を雇用した個人事業主などであれば、対応が遅れがちになってしまうこともあるでしょう。
年末調整が翌年1月31日までの期日以内に終えられていない場合は、ペナルティとして不納付加算税や延滞税といった追徴課税が発生するため注意が必要です。
さらに、税法は毎年改正されるため最新の情報に対応する必要もあります。そのため、自社の経理部門で対応するのではなく、税理士に年末調整を依頼すれば、手間が省けるだけでなく「早く」「正確」に年末調整業務が完了します。
メリット3.追加人員を雇用するよりコストが抑えられる
年末調整のために、残業が一時的に増加したり、追加人員を雇用すると、企業にとっては人件費が増加することになります。
年末調整の外注にかかる費用は比較的安価なため、アウトソーシングすることでコストを抑えることができます。
年末に差し掛かる忙しいタイミングでも経営者や経理担当者の時間を確保できるため、十分な費用対効果があるといえるでしょう。
年末調整をスムーズに進めるには
税理士に依頼するとしても、年末調整のスケジュールを把握しておく必要はあります。必要な手続きとスケジュールを確認し、年末に慌てないよう準備しておきましょう。
このように、年末調整は手間と時間がかかる作業です。対象となる従業員が少人数であれば自社での対応も可能ですが、従業員数が増えれば増えるほど、作業が煩雑になっていきます。
税理士選びでお悩みの方へ
「どんな税理士がいいの?」「もっと親身な税理士に変更したい」など税理士選びでお困りの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。
税理士選びでお悩みなら税理士ドットコムにご相談ください

※ゼネラルリサーチ調べ