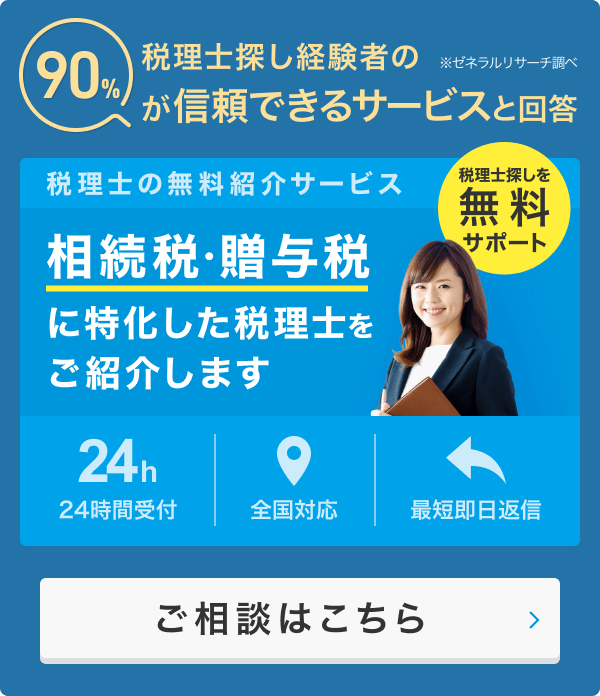法定相続人とは?相続順位や法定相続分の割合について解説
民法では、被相続人(亡くなった方)の財産を誰が相続するのか、どうやって分配するのかについてを『法定相続人』や『法定相続分』として定めています。トラブルを防ぐためや、トラブルが起きた際に恣意性に左右されず公平な課税を実現するためです。
相続では、遺言による遺贈や生前の契約による死因贈与という方法もあり、これらについても把握しておく必要があります。また、法定相続人には最低限の財産を相続できる『遺留分』という権利もあります。
- 相続人って誰がなるの?
- 相続財産(遺産)はどうやって分ける?
- 法定相続人の順位って?
- 相続人と法定相続人って違う?
- 法定相続分とは?
- 遺留分ってなに?
このページでは、法定相続人の範囲と法定相続分、相続・遺贈・死因贈与の違いや遺留分についてご説明いたします。
目次
法定相続人の範囲と順位
「法定相続人」とは、民法によって定められている被相続人の財産を受け継ぐ権利がある人を指します。
法定相続人は全員が平等ではなく、以下のように相続する順位が定められており、その優先順位によって財産を受け継ぎます。

配偶者は常に相続人となるので、配偶者には優先順位はありません。それ以外の相続人の順位は以下のとおりです。
- 第一順位:直系卑属(子や孫)
- 第二順位:直系尊属(親や祖父母)
- 第三順位:傍系の(兄弟姉妹や甥姪)
胎児や養子も含まれる
第一順位である子供には養子や胎児も含まれます。
胎児については、民法上すでに生まれている人とみなされ、相続権が認められます。もし相続時に胎児が相続人になる場合は、出産を待ってから遺産分割を行います。
養子については、血縁関係のない子どもでも、法律的に親子の関係が認められていれば相続人となります。また、正式な婚姻関係のない男女の間に生まれている子供でも父親からの認知が確認されると、実子や養子と同じく第一順位の相続人となります。
相続人がいない場合の「代襲相続」とは
本来相続人となる人が被相続人よりも先に死亡してるケースや、何らかの形で相続権を失っている場合があります。その場合はその人の直系卑属(子や孫)が代をかさねて相続人となり、これを代襲相続といいます。
例えば、子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、子供に代わり孫が相続を受けることになります。また、子も孫も亡くなっているという場合は曾孫が第一順位として相続人になります。
法定相続分と割合
各法定相続人の財産を分ける割合のことを「法定相続分」といいます。相続人が配偶者のみの場合は配偶者がすべてを相続しますが、その他に相続人がいる場合は、その構成によって相続分が変化します。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 (民法第900条)
以下に例を挙げて、法定相続分に沿った財産の分け方を詳しくご説明いたします。
第1順位:子供がいる場合(相続人が配偶者と子供)
| 相続人 | 法定相続人 | |
|---|---|---|
| 子供がいる場合 (第1順位) | 配偶者 | 2分の1 |
| 子供 | 2分の1 | |
被相続人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者1/2、子供1/2という割合で相続が行われます。子供が2人以上いる場合は、相続分の1/2を人数で分割します。子供が2人であれば、子供1人あたりの相続分は全体の1/4ずつとなります。
第2順位:子供がいない場合(相続人が配偶者と直系尊属)
| 相続人 | 法定相続人 | |
|---|---|---|
| 子供がいない場合 (第2順位) | 配偶者 | 3分の2 |
| 父母、祖父母 | 3分の1(複数いる場合はこれを均等按分) | |
被相続人に配偶者がいて子供や孫がいない場合は、配偶者2/3、親1/3という割合で相続が行われます。両親共に健在な場合はそれぞれに全体の1/6分の相続分が認められます。
第3順位:子供も父母もいない場合(相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合)
| 相続人 | 法定相続人 | |
|---|---|---|
| 子供も父母もいない場合 (第3順位) | 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 4分の1(複数いる場合はこれを均等按分) | |
被相続人に配偶者はいるが子供や孫、両親がおらず兄弟姉妹がいる場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4という割合で相続が行われます。兄弟姉妹が2人いる場合は、1人あたりの相続分は全体の1/8となります。
遺贈、死因贈与の違い
法定相続による相続以外にも、「遺贈」や「死因贈与」といった方法で財産を受け継ぐことがあります。
遺言によって相続するのが遺贈
遺贈とは、遺言書で財産を任意の人に相続させることを指します。
原則として、法定相続人にしか相続は行われませんが、遺贈であれば法定相続人以外にも一定の範囲内で財産を被相続人の意思に沿って相続させることが可能です。遺贈する人を「遺贈者」、相続する人を「受遺者」といいます。
例えば友人や知人、NPO法人などに無償譲与をすることも可能です。ただし、受遺者が相続を拒否することもできるという点には注意が必要です。
生前に契約をするのが死因贈与
死因贈与とは、生前に両者の意思によって相続について契約を交わすことを指します。契約後は、原則として相続を拒否できないので、確実に相続を行うことが可能です。
遺贈、死因贈与では相続税の2割加算に加えて不動産所得税が高くなるなど、相続税の計算方法が通常時と異なるので注意が必要です。
「遺留分」で最低の相続分が保証されている
被相続人は、遺言により自由に財産を処分することができますが、「遺留分」について留意する必要があります。
例えば「全財産を第三者へ遺贈する」などの表記により、遺族に相続するものが全く無いという遺言書が残されたとします。その場合は、遺族の最低限の生活が保証できないということが起きかねません。そのような事態を免れるために法定相続人へ最低限の財産を保証する制度があり、これを「遺留分制度」といいます。
遺留分は、原則として遺言でも侵害することはできません。遺留分の範囲は兄弟姉妹以外の法定相続人で、基本的には配偶者、子供、親になります。
また、子供が被相続人よりも先に他界していた場合は、孫が代をまたいで相続(代襲相続)することになります。代襲相続でも遺留分としての原則の権利が認められることがあります。
遺留分の割合は下表のとおりです。
| 法定相続人 | 配偶者 | 子 | 父母 | 遺留分の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | - | - | 1/2 |
| 配偶者と子 | 1/4 | 1/4 | - | 1/2 |
| 配偶者と父母 | 2/6 | - | 1/6 | 2/1 |
| 子のみ | - | 1/2 | - | 2/1 |
| 父母のみ | - | - | 1/3 | 1/3 |
遺留分減殺請求
遺留分を侵害している相続人に対して、遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求には決まった手順はなく、意思表示をすることで効力が生じます。相手との話し合いで交渉が終了することもありますが、証拠を残すという意味で内容証明郵便などで意思表示を行うことが一般的です。
遺留分には期間が定められており、遺留分の侵害を知った日から1年以内、また相続開始から10年以内に申請を行わなければいけません。
遺留分放棄
「遺留分放棄」は被相続人の生前に行うか、死後に行うかによって家庭裁判所の必要性の有無に違いがあります。
通常被相続人の生前に行われる遺留分放棄とは、被相続人の「特定の人に対してのみ財産を相続してほしい」という意思によって行われます。生前での遺留分放棄は、法定相続人の意思よりも被相続人の意思が先行するケースが多く、実際は権利を放棄したくないという被相続人がいるケースを無くすために裁判所の許可が必要になります。
実際に裁判所で遺留分の放棄が認められるには、以下の3点を満たしている必要があります。
- 遺留分の放棄は法定相続人の意思によって行われていること
- 合理的な理由があること
- 遺留分に相当する見返りを受ける(受けていること)
一方、被相続人の死後に行われる遺留分放棄は裁判所の許可は必要ありません。相続人の意思によって、簡単に遺留分を放棄することが可能です。実際には、遺留分というのは請求さえしなければ何も発生しない権利なので、一定期間なにもしなければ遺留分を放棄することになります。
また、遺留分は一度放棄をしてしまうと原則として取り消しができないのでご注意ください。
税理士選びでお悩みの方へ
「どんな税理士がいいの?」「もっと親身な税理士に変更したい」など税理士選びでお困りの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。
また、予算が気になる場合は<税理士の費用・料金相場>を参考に、おおよその料金を把握しておくとよいでしょう。
税理士選びでお悩みなら税理士ドットコムにご相談ください

※ゼネラルリサーチ調べ