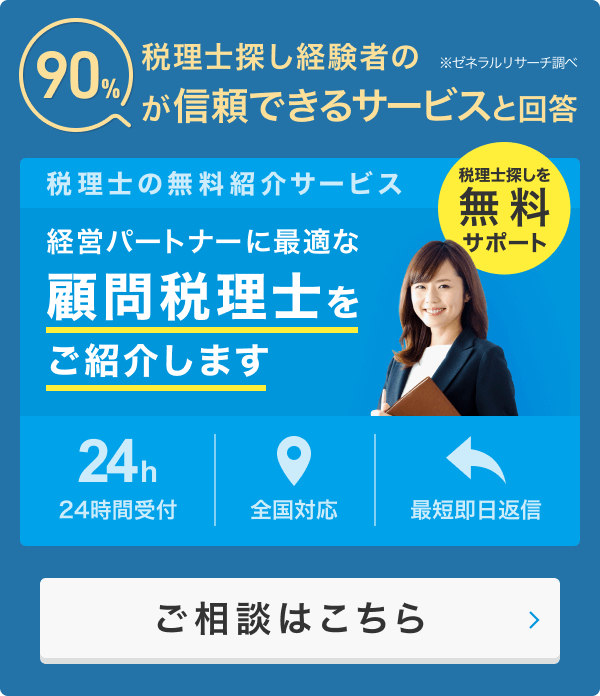税理士と公認会計士の違い - どちらに相談するべきか
(監修:税理士法人シグマパートナーズ 堀内 太郎 税理士)
税理士と会計士の違いって何?と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。どちらも税務や会計などを中心とした業務を生業としていることは共通しているため、混同されてしまうのかもしれません。
また、この「会計士」という名称は正確には定義されていないため、この言葉が税理士を指す場合、公認会計士を指す場合やUSCPA(米国公認会計士)を指す場合にも用いられることがあります。これも違いが分かりにくくなっている背景のひとつと言えるかもしれません。
このページでは、税理士と公認会計士の業務の違いから、具体的な事例をケースを用いて税理士と公認会計士のどちらに相談すべきかを解説します。
目次
税理士や公認会計士資格の取得方法
まず、税理士と公認会計士の違いを理解するために、それぞれの資格の取得方法について確認しましょう。
税理士や公認会計士になるには、どちらも難関の試験を突破して、国家資格を取得しなければなりません。では具体的には、どのような試験を突破しなければならないのでしょうか。
税理士になるには?
税理士になるためには制度上複数の方法がありますが、最も一般的な方法としては、税理士試験に合格し、関連する分野での2年以上の実務経験を積むことです。この二つを満たし、日本税理士連合会に税理士として登録する手続きを行うことで税理士になることができます。
税理士試験の概要は以下のとおりです。
税理士試験の主な受験資格
- 大学・短大・高等専門学校を卒業し、法律学または経済学に属する科目を1科目以上取得した者
- 大学3年次以上で、法律学または経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
- 司法試験合格者
- 公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る)
- 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者
- 全国経理教育協会主催簿記上級試験合格者
税理士試験の受験科目
以下の全11科目から5科目を選択し合格する必要があります。
- 必修科目:簿記論、財務諸表論
- 選択必修科目:所得税法、法人税法
(1科目以上選択) - 選択科目:相続税法、消費税法、事業税、国税徴収法、酒税法、住民法、固定資産税
(但し、消費税法・酒税法と住民税・事業税はどちらか1科目のみ選択可)
税理士試験は年1回開催されます。合格率は各科目10%台と高難度ですが、科目ごとに個別で合否が判定される制度のため、必ずしも一度に5科目すべて合格する必要はありません。
また、弁護士または公認会計士の資格をすでに持っている場合、試験は受けずに日本税理士連合会に税理士登録をするだけで税理士になることができます。
公認会計士になるには?
公認会計士になるためには、以下の4つのステップを踏む必要があります。これを経て、日本公認会計士協会に公認会計士として登録手続きを行うことで公認会計士になることができます。
- 公認会計士試験に合格する
- 2年以上、業務補助を行う
- 3年間の実務補習を受ける
- 修了考査に合格する
公認会計士試験の概要は以下のとおりです。
公認会計士試験の受験資格
年齢・性別・学歴などに関係なく、誰でも受験が可能です。
公認会計士試験の受験科目
- 短答式試験の試験科目:財務会計論、管理会計論、監査論、企業法
- 論文式試験の試験科目:(必修科目)会計学、監査論、租税法、企業法(選択科目)経営学、経済学、民法、統計学から一科目
試験は短答式(マークシート方式)試験と論文式試験に分かれていて、短答式試験は年2回、論文式試験は年1回行われています。短答式では一括合格を、論文式でも原則として一括合格を求められるため、非常に広範囲を一度に学ばなければなりません。
税理士試験や公認会計士試験の対策はどうやってする?
どちらも難関な試験のため、大半の受験者が予備校や通信教育講座を利用します。広範囲の学習が必要なので、独学だけではなく、予備校や通信教育講座を併用して試験対策をすることが一般的です。
税理士や公認会計士試験対策ができる予備校・通信教育講座
予備校は夜間クラスの講座も設置されていて、働きながらでも学びやすい環境が整えられています。通信教育講座は近くに校舎がない方や、なるべく費用を抑えたい方などが利用しています。
税理士試験対策の予備校・通信教育講座で代表的なものとしては以下が挙げられます。どの予備校・通信教育講座も無料で資料請求が可能となっています。
- 資格の大原 (通学/通信)
- LEC(通信のみ)
- クレアール(通信のみ)
色々なコースが用意されていて様々な活用方法があるため、自分の生活スタイルに合わせて最適な試験対策を行うことが重要です。
税理士業務と公認会計士業務の違い
税理士と公認会計士の業務は、同じようなものだと誤解される方が多いですが、実はそれぞれに独占業務を持ち、請け負う案件も大きく異なります。
税理士の業務とは?
税理士の独占業務は税務業務です。
具体的な業務範囲は、納税者に代わって税務申告を行う税務代理、税務書類の作成の代行、税務に関する相談が主となります。
企業の代理人という形で、経営者側に寄り添ったサービスを提供できるため、多くの税理士のクライアントは主に個人の方や中小企業・ベンチャー企業となります。
公認会計士の業務とは?
会計士の独占業務は監査業務です。
監査業務とは、企業から学校法人、公益法人など幅広い対象について、独立した立場から監査意見を表明し、財務情報の信頼性を担保する業務です。
様々な監査のうち最もイメージしやすい金融商品取引法に基づく監査を受ける義務があるのは、主に上場企業であるため、会計士のクライアントは主に大企業や中堅企業となります。
事例解説-どちらに相談するべきか?
では、事業を営む方は税理士と公認会計士のどちらに相談すべきか、具体的な相談内容ごとに解説します。
記帳代行
記帳代行は税理士、公認会計士を問わず相談することができます。しかし、日々の記帳では、消費税や法人税などの税に関する問題が出てくるため、税務に精通する専門家に依頼する方がいいでしょう。
節税の相談
節税など、税務に関する相談は税理士に相談します。税務相談は税理士の独占業務であるため、税理士にしかできない業務です。
M&Aの相談
M&Aに関する相談は、公認会計士に相談するとよいでしょう。M&Aで行われる財務デューデリジェンスは企業会計に関する専門的な知識が必要です。ただし、案件によっては、専門的な税務の知識が必要となることもありますので、その場合は税理士とも連携を取る必要があるでしょう。
おわりに
税理士は相談者の側に立って税務に関する依頼を引き受ける専門家であり、会計士は中立の立場から監査業務を行う専門家です。
しかし、なかには公認会計士兼税理士として活動をしている人もいて、どちらの分野が得意で経験が多いかはそれぞれ異なります。また、弁護士や弁理士などの資格を持った税理士・会計士もいます。
このため、相談や実際に業務を依頼するときには、それぞれの資格についての基礎知識を踏まえ、最後は、その人の得意な分野や経験なども合わせて考慮するとよいでしょう。
税理士選びでお悩みの方へ
「どんな税理士がいいの?」「もっと親身な税理士に変更したい」など税理士選びでお困りの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。
また、予算が気になる場合は<税理士の費用・料金相場>を参考に、おおよその料金を把握しておくとよいでしょう。
税理士選びでお悩みなら税理士ドットコムにご相談ください

※ゼネラルリサーチ調べ