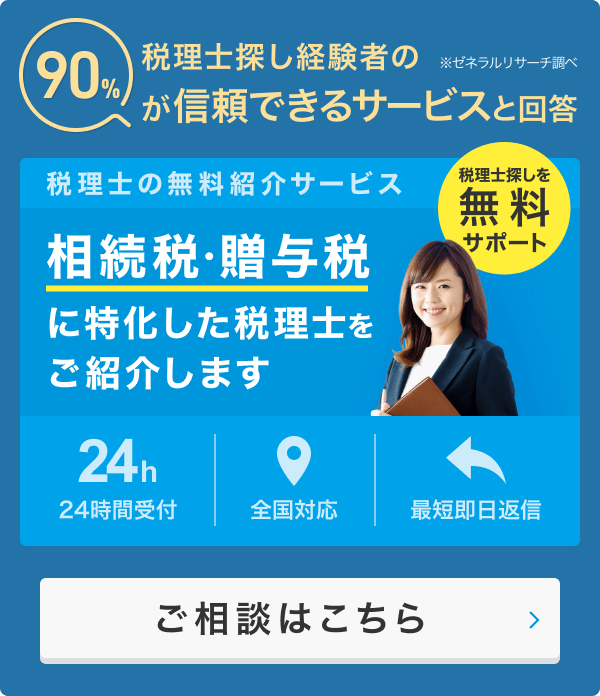相続税が還付されるケース - 税理士に依頼したときの費用実例も紹介
(監修:ゼロイチ会計事務所 井上 貴之 税理士)
相続税は、申告ミスなどで払いすぎている人も少なくありません。
払いすぎた税金は所定の手続きを行うことで「還付」されます。特に土地・不動産といった相続財産については、還付の対象となる可能性が高いです。
そこで相続税の還付を受けたい方に向けて、還付が起こるケースや還付申告(更正の請求)について解説します。
目次
相続税還付は「申告期限から5年以内」に
相続税の還付とは、なんらかの理由で相続税を多く納めてしまっていた場合に、所定の手続きにより返還してもらうことをいいます。
還付を受けられる可能性がある場合、相続税の申告期限から5年以内に手続きをしなくてはなりません。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ですので、過去5年10か月の間に相続が発生している方は、相続税の還付が受けられる可能性があるということです。
ただし、次のような「特別な事情」があるときは、5年10か月を越えても還付の手続きが可能です。
- 分割が終わっていなかった相続財産について、相続税申告後に分割が完了した
- 子供の認知や相続放棄の取り消しなど、相続人に変更があった
- 遺留分(一部の相続人に認められている保護された相続分)の返還があった
- 遺産分割が完了して、特例の適用が可能になった
- 遺贈する旨の遺言書が見つかったり、遺贈の放棄があった
上記のような特別な事情があった場合は、その事由が発生したことを知った日の翌日から4か月以内が還付手続きの期限です。
なお、納めすぎた相続税が還付される際、利息となる「還付加算金」もあわせて支払われることがあります。還付加算金は「雑所得」に区分され、場合によっては確定申告が必要になります。
相続税還付が起きるケース
国税庁が発表したデータによると、令和2年度に相続税の還付を受けた納税者は546人、還付金の合計金額は12億2000万円ということから、1人あたりに換算するとおよそ220万円という金額になります。
ここで知っておかなくてはならないのは、「相続税の納めすぎを税務署は教えてくれない」ということです。
そのため、どういったケースで相続税還付が発生するのかを把握し、自身で「相続税を納めすぎていないか」を確認しなくてはなりません。
相続税の還付が起きやすいのは次のようなケースです。
相続財産に土地が含まれる
相続財産が預金だけの場合、口座残高などで課税対象となる財産金額を明確に判断できますが、不動産が相続財産にある場合、不動産購入時の金額とは別の「相続税評価額」を基準に、課税対象の金額を算出しなければなりません。
不動産の中でも、特に「土地」は面積や立地など複雑な要素が絡むため評価額にブレが生じやすく、過分に査定してしまい、結果として相続税を多く納めてしまうという事態が発生しやすいのです。
しかも土地はわずかな評価差によって納める税の金額も大きくなりやすいので、還付を受けられる場合に戻ってくる金額も大きくなります。
では、特に還付が発生しやすい土地の例を具体的にみていきましょう。
1.500平米以上の面積を有する土地
500平米以上の面積を有するなど、その地域における標準的な宅地に比べて著しく広い土地は、実際に売却しようとしても路線価などで算出した一般的な金額では売却できず、大幅に安くなってしまうことが多くあります。
そのため「地積規模の大きな宅地の評価」という制度が設けられていて、適用が認められると相続税評価額を大幅に減額することができます。
なお、2017年12月31日以前に発生した相続については「広大地評価」が適用されます。
2.線路沿いに位置する土地
線路沿いの土地については、電車の通過による騒音や振動が予想されます。
賃貸物件でも線路沿いの物件は家賃が下がったりすることがありますが、相続税評価額についても、一定以上の騒音がある場合については減額要素となります。
騒音のレベル(デシベル)や電車が通過する頻度のほか、踏切までの距離など減額に足りる要素があるかで判断されます。ただし、近隣の路線価よりも低い土地については、すでに路線価に対して騒音による減額が盛り込まれている場合もあります。
3.無道路地
四方をほかの土地などに囲まれていて道路に面していない宅地を「無道路地」といい、建物の新築や取り壊しが困難になると予想されるため、相続税評価額の減額要素となります。
また、その土地に立っている家に出入りするために細い道を利用している場合にも、該当する可能性があります。
4.傾斜地
傾斜がかかっている土地を「傾斜地(がけ地)」といいます。傾斜地は、平坦な土地と比べて利用価値が低くなるため、相続税の評価額も低くなります。
傾斜地は土地の面積のうち、斜面になっている部分の面積の割合と、がけ地のある方位によって、減額できる価額が変わってきます。
がけ地の占める割合が多ければ多いほど補正率は低くなり、また、方位については、南、東、西、北の順に徐々に補正率が低くなるため、斜面が北側を向いている場合が、最も評価額を減額できます。
5.高圧線が上を通る土地
土地の直上に高圧線が通っている場合、建物が建てられなかったり、構造や高さ、用途などで制限を受けるため、評価額の減額要素となります。
土地の直上に高圧線が通っている場合は、電気事業者との間で「地役権設定契約」などが締結されているはずなので、それらの契約書が権利証と一緒に保管されていないかどうか、確認しておきましょう。
6.不整形地
土地の形が正方形や長方形ではない土地を「不整形地」といいます。多く見られるのが、三角形、L字、台形などといった形の土地です。
不整形地は、正方形や長方形の土地と比べて、土地の有効利用がしづらくなるため、不整形の状況に応じて相続税評価額の減額が可能になります。
評価額の算出には、地積区分表で該当する地積区分を確認し、不整形地補正率表でその地積区分に応じた部分の不整形地補正率を用います。
7.忌み地
墓地などに隣接する土地を「忌み地」といいます。忌み地は、通常の土地に比べ環境面で心理的に影響があり利用価値が低下するとして、相続税評価額の減額要素となります。
ただし、評価対象となる土地が墓地や寺院が多数存在する地域にあるような場合は減額は難しいと考えられます。
8.庭内神しのある土地
鳥居、祠、社など日常礼拝の対象となっている「庭内神し(ていないしんし)」がある敷地部分は非課税になります。以前は庭内神し自体のみで敷地に関しては課税対象でしたが、取り扱いが変更されました。
なお、庭内神しがあるからといって必ずしも非課税になるわけではありません。設備の建立の経緯・目的や敷地への定着性など、さまざまな点を加味して判断されます。
9.登記簿情報より実際の土地面積が小さい土地
土地の相続税評価額を算出する際には、わざわざ測量を行う必要がないため、登記簿上の地積を面積として考えるのが一般的です。ところが、登記簿上の地積と実際の面積が必ずしも同じとは限りません。
たとえば代々受け継いでいるような、明治以前に登記登録が行われた土地の場合には当時の測量技術不足もあり、登記簿上の地積よりも土地面積が小さくなっている可能性があります。
これを見落としたまま、登記簿上の地積のみで計算して申告している場合は、改めて測量をすることで、実際の面積との差額分だけ評価額を減額することができます。
相続税に強くない税理士が申告をした
相続税の申告を税理士に依頼していても、還付が生じる可能性はゼロではありません。
医師や教師に専門分野があるように、税理士にもそれぞれ得意分野があります。特に相続税については、得意不得意が出やすいと言われています。
相続税の申告に不慣れな税理士に依頼すると、ここまでで解説したような減額対象となる要素や、相次相続(以前の相続から10年以内に再度発生する相続)などの控除を見落としてしまうこともあります。つまり、納税者が相続税を納めすぎることになってしまうのです。
相続税還付の手続きと必要書類
納めすぎた相続税があるときは、「更正の請求」という手続きで還付を求めることができます。
更正の請求には、「相続税の更正の請求書」と「申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等」という書類に、更正内容を証明するための書類を添付する必要があります。
土地の評価額の減額によって更正の請求を行う場合には、測量結果や地積測量図、公図、鑑定書、現地の様子がわかる画像などを準備しておきましょう。
書類の提出は、税務署窓口に直接出向く方法と郵送のほか、令和元年分以降の申告からはe-Taxでも可能です。
なお、手続きは還付の対象となる相続人がそれぞれ行う必要があります。
還付金の受け取り方法と時期
更正の請求後は税務署での審査があり、還付金を受け取るまでに通常3〜6か月程度を要します。
還付金の受け取りは、預貯金口座への振込みによる方法と最寄りのゆうちょ銀行または郵便局に出向いて受け取る方法があります。
審査は税務署にもよりますが2〜3か月が目安で、必要に応じて確認や質疑などが行われます。問題なく申告内容が認められれば、「更正決定通知書」が郵送されます。
その後「国税還付金振込通知書」という還付金額などが記載されたハガキが届き、受け取り方法で振り込みを選択した場合は、1週間程度で入金が確認できます。
物納や延納だった場合はどうなる?
税金は現金一括での納付が原則とされていますが、高額になりやすい相続税においては一定の条件を満たしていれば、土地などの現物を納税にあてる「物納」や、分割で納める「延納」という方法で納税することもできます。
「物納」や「延納」により相続税を納付している場合、「更正の請求」について次のように決められています。
- 物納:物納の許可が出て、収納決定した後であれば、金銭一括納付と同じように更正の請求ができる
- 延納:延納が認められた後でも、更正の請求は可能。ただし、還付金については、延納の残金に充当(未払い分と相殺)される
相続税還付に強い税理士の選び方と報酬相場
相続税の還付に心当たりがある方はまず、どの程度還付される可能性があるかを「相続税還付に強い税理士」に相談してみましょう。
相続税還付に強い税理士とは、「相続税申告の経験が豊富な税理士」や「不動産知識のある税理士」です。不動産については、専門家である不動産鑑定士と協働して還付を行なっている税理士もいます。
相続税還付の税理士報酬の相場は、ケースや税理士事務所によって異なりますが、完全成功報酬型を採用している事務所が多くあります。
この場合、相談や手続き段階での費用はかからず、還付金が戻ってきてからの支払いとなります。成功報酬の相場としては還付された金額の20〜40%程度です。
セカンドオピニオンを検討してみよう
還付の可能性があるかもしれないと思ったら、申告時に依頼した税理士とは違う税理士に相談してみることも検討してみましょう。
最近では「セカンドオピニオン」を謳う、相続税の還付専門の税理士事務所もあります。
相続税還付の成功実例
これまでに税理士ドットコムに寄せられた約10万件の相談実績(※)の中から、実際に相続税の還付手続きを依頼された方の実例を紹介します。
※税理士ドットコムの「税理士紹介サービス」に寄せられたご相談
相談者様:被相続人の配偶者
相続人:子2名、被相続人の姉弟
手続き内容:控除の適用漏れ
相続人である子2人は障害者控除の対象者でしたが、相続税申告をしたときには適用しておらず、こちらについて更正の請求手続きをしたいという依頼です。
最初の相続税申告を依頼した税理士へ見積もりをとったところ、相談料30万円+成功報酬という内容で、費用が高く断念したため税理士を探しているという相談内容でした。
数名の税理士を紹介し、その中から完全成功報酬型で成功報酬20%の税理士とご契約されました。
税理士選びでお悩みの方へ
「どんな税理士がいいの?」「もっと親身な税理士に変更したい」など税理士選びでお困りの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。
また、予算が気になる場合は<税理士の費用・料金相場>を参考に、おおよその料金を把握しておくとよいでしょう。
税理士選びでお悩みなら税理士ドットコムにご相談ください

※ゼネラルリサーチ調べ