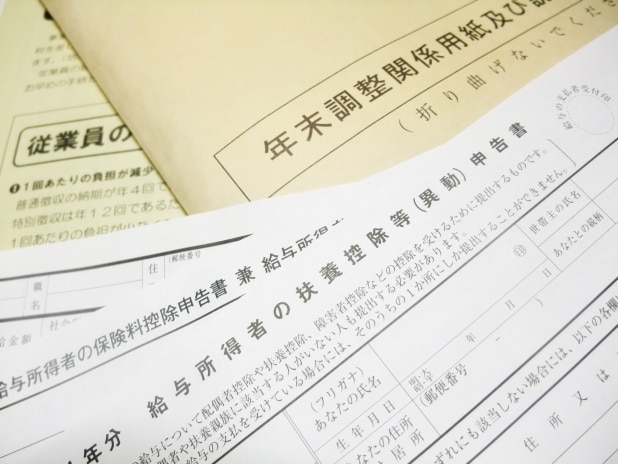【2025年版・個人向け】知らないと損をする?税制改正8つの注目ポイントとは
税金・お金

3月31日、2025(令和7)年度予算案が参議院で可決され、同時に税制改正関連法案も成立した。衆参両院で修正された予算が成立するのは初めてのことだ。
国民民主党が主張する「基礎控除178万円まで引き上げ」は通らなかったが、所得税の課税最低ラインは160万円まで引き上げられた形だ。
そこで改めて、2025年からの税制がどのように改正されたか、主に一般の人に関係がある以下8つの改正事項を確認していこう。
1)所得税の課税最低限を段階的に160万円へ引き上げ
2)特定扶養控除の適用年収の引き上げ
3)特定親族特別控除の創設
4)子育て世代の生命保険料控除の拡充
5)子育て世代の住宅ローン減税拡充を2025年まで1年間延長
6)最大1000万円までの結婚・子育て資金の一括贈与を2027年3月末まで2年間延長
7)退職所得控除の適用ルールが5年→10年に変更
8)所得控除の対象となるiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金が大幅にアップ
●1)所得税の課税最低限を段階的に160万円へ引き上げ
これまで給与所得者は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた103万円を超えると所得税が課税されるしくみとなっていた。いわゆる「103万円の壁」だ。
今回の税制改正で、年収2,545万円以下(合計所得金額2,350万円以下)の場合、基礎控除額は48万円から58万円に引き上げられ、さらに所得金額に応じて基礎控除額の上乗せがされることになった。
<基礎控除額>※()内は合計所得金額
・年収200万円以下(132万円以下)…基礎控除95万円(37万円上乗せ)
・年収475万円以下(336万円以下)…基礎控除88万円(30万円上乗せ)
・年収655万円以下(489万円以下)…基礎控除68万円(10万円上乗せ)
・年収850万円以下(655万円以下)…基礎控除63万円(5万円上乗せ)
この基礎控除の上乗せは、年収200万円以下の人は恒久的に、年収200万円超の人は2年間の限定措置となる。
また、給与所得控除は55万円から65万円に引き上げられた。これにより、所得税の課税最低限が160万円に引き上げられることになる。
●2)特定扶養控除の適用対象となる子の年収の上限引き上げ
これまで、19歳以上23歳未満の子どもが、学生アルバイトなどで給与収入が103万円を超えた場合、親は63万円の特定扶養控除が受けられなくなっていた。今回の改正で特定扶養控除の適用対象となる子の給与収入が150万円(合計所得85 万円)に引き上げられた。
●3)特定親族特別控除の創設
上記に加え、子どもの給与収入が150万円(合計所得85 万円)を超えた場合は、親が受けられる控除額が段階的に減っていくしくみとして、「特定親族特別控除」が創設・導入された。
<左:子どもの給与収入/右:親が受けられる控除額>※()内は合計所得金額
・年収150万円以下(85万円以下)…63万円
・年収155万円以下(90万円以下)…61万円
・年収160万円以下(95万円以下)…51万円
・年収165万円以下(100万円以下)…41万円
・年収170万円以下(105万円以下)…31万円
・年収175万円以下(110万円以下)…21万円
・年収180万円以下(115万円以下)…11万円
・年収185万円以下(120万円以下)…6万円
・年収188万円以下(123万円以下)…3万円
また、1)から3)までの見直しに伴い、以下の変更も行われた。
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を、48 万円以下から58万円以下に引き上げ
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を、48 万円以下から58万円以下に引き上げ
・勤労学生の合計所得金額要件を、75 万円以下から85 万円以下に引き上げ
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を、 55 万円から65 万円に引き上げ
●4)子育て世代の生命保険料控除の拡充
新制度における生命保険料控除は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」のそれぞれについて、所得税から年4万円(合計で最大12万円)まで控除を受けることができる。
23歳未満の扶養親族がいる子育て世代は、このうち「一般生命保険料」で控除額が年6万円まで引き上げられた。2026年のみ暫定適用される予定だ。
●5)子育て世代の住宅ローン減税拡充を2025年まで1年間延長
2024年、19歳未満の扶養親族を有する子育て世帯と、夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯(特例対象個人)の住宅ローン減税が拡充された。
<子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅ローン控除の借入限度額>
・認定住宅…5,000万円
・ZEH水準省エネ住宅…4,500万円
・省エネ基準適合住宅…4,000万円
当初は2024年中に入居する際の時限措置だったが、2025年中入居までと1年間延長された。
●6)最大1000万円までの結婚・子育て資金の一括贈与を2027年3月末まで2年間延長
結婚・子育て資金の一括贈与とは、直系尊属(父母・祖父母など)から結婚や子育てに関する資金を贈与した場合、最大1000万円まで贈与税が非課税になる制度だ。対象期間は2025年3月31日までだったが、2027年3月31日までと2年間延長された。
●7)退職所得控除の適用ルールが5年→10年に変更
これまでは、iDeCoなどの確定拠出年金を一時金で受け取り、退職所得控除の適用を受けた場合、会社の退職金を5年後に受け取れば、退職金も別途退職所得控除の適用が受けられた。改正により、この5年ルールが10年に延長された。
●8)所得控除の対象となるiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金が大幅にアップ
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金について、個人事業主は月額 6.8 万円から月額 7.5 万円、会社員(企業年金未加入者) は月額2.3万円から月額 6.2 万円、同じく会社員(企業年金加入者)月額2万円から月額 6.2 万円ー他の企業年金の掛金と、大幅に拡大された。
以上が一般の人に関係がある税制改正の内容だ。これらを踏まえ、奈須大貴税理士に注意点や見解を聞いた。
●家計に与える影響は大きいが制度が複雑化。迷ったら専門家へ相談も
ーー今回の一般向けの税制改正内容について、全体を通じての見解や注意点などをお教えください。
「今回の税制改正は、特に年収の低い方や子育て世代に向けた支援が多く盛り込まれた点が特徴的です。たとえば、課税最低限が160万円に引き上げられたことで、これまで所得税がかかっていた人の中にも、非課税となるケースが出てくるかもしれません。
ただし、制度が複雑化してしまったという懸念点も大きいかと思います。年収や家族構成、家族の働き方によって控除額が変わるため、家計に与える影響を正しく理解しておくことが大切です。
さらに企業にとっては、年末調整事務の負担が大きく増えてしまう可能性もあります。
また、iDeCo掛金の拡大や退職所得控除のルール変更などは、将来の資産形成や退職金の受け取り方にも影響します。
制度の理解不足が損につながるケースもあるため、早めの確認と専門家への相談をおすすめします。」
【取材協力税理士】
奈須 大貴(なす・ひろき)
税理士、公認会計士、認定IPOプロフェッショナル(SIP)。
1994年生まれ、福岡県北九州市出身。有限責任監査法人トーマツ福岡事務所、株式会社Faroを経て、2023年に独立開業。
「会計で会社を強くする!!!」、「あなたの夢、会計力で応援します!!!」というスローガンのもと、スタートアップ企業、中小企業を中心に税務顧問サービスを提供している。
また、公認会計士として、IPO準備企業の支援や上場企業の決算、開示支援も行っている。
事務所名 :奈須大貴公認会計士・税理士事務所
事務所URL:https://hnasu-cpa.com/