建設業に税理は必要?建設業に強い税理士の選び方や費用相場を解説

建設業を営むうえで、税理士のサポートがどの程度必要なのか迷う方も多いのではないでしょうか。建設業は他業種と比べて会計や税務処理が複雑で、専門的な知識が求められる場面が少なくありません。
たとえば、工事台帳の作成や原価管理、さらには建設業許可の更新手続きなど、日々の業務に加えて対応すべき課題は多岐にわたります。こうした状況をスムーズに乗り越えるためには、建設業に詳しい税理士の存在が欠かせないでしょう。
この記事では、建設業と税理士の関係性にも触れながら、税理士を選ぶ際のポイントや費用の目安を詳しく解説していきます。
目次
建設業に税理士が必要な理由

建設業は、原価管理や売上計上など、以下のポイントで専門的な知識が求められます。
- 経営面で損をする可能性を防ぐ
- 建設業では資金繰りが大切
- 融資に優れた書類作成は正しい知識が求められる
- 建設業許可を取得するのに時間がかかる
適切な処理を進められるように、より詳しく解説していきます。
経営面で損をする可能性を防ぐ
建設業には、業界特有の会計処理が多く存在しています。たとえば、完成基準や進行基準によって収益の計上時期が変わるため、正しい判断ができなければ課税ミスや利益の過大・過小計上が発生する可能性があります。
また、外注費と人件費の区別、工事原価の算出なども非常に複雑であり、処理を誤ると経営判断を誤る要因にもなりかねません。税務署からの追徴課税を受けるリスクなどを回避するため、建設業の業務を深く理解した税理士に依頼をおすすめします。
建設業では資金繰りが大切
建設業では、受注から入金までの期間が長くなるケースが多いため、資金繰りが経営の大きなカギを握ります。特に、資材購入や外注費の支払いが先行しがちなため、売上が発生していても手元に現金が残らない状況に陥ることも少なくありません。
このような資金繰りの難しさに対応するには、建設業の財務構造に詳しい税理士の助けが必要です。資金の流れを見える化し、無理のない支出計画を立てることで、支払い遅延や資金ショートのリスクを減らせます。
融資に優れた書類作成は正しい知識が求められる
建設業では、設備投資や資材調達にまとまった資金が必要になるため、金融機関からの融資を受ける機会が多くなります。融資を成功させるためには、信頼性の高い決算書や財務諸表の作成が欠かせません。
ここで重要になるのが、業界特有の収支構造や会計処理を理解した税理士の存在です。建設業に強い税理士であれば融資に有利な書類を整えて、金融機関に対する事前の準備や面談時のアドバイスも受けられるため、安定した事業運営につながります。
建設業許可を取得するのに時間がかかる
建設業を営むには、原則として建設業許可の取得が必要です。この手続きは多くの書類準備が求められるうえに、要件も複雑であるため、慣れていないと想定以上に時間と労力がかかってしまいます。
税理士事務所の中には、行政書士と連携している事務所も多く、建設業許可に関するサポート体制が整っている場合があります。こうした税理士に依頼すれば、必要書類の整備から申請手続きまでをスムーズに進めてもらえるでしょう。
建設業に税理士に強い税理士の特徴

建設業に特化した税理士は以下のような特徴をもっています。
- 行政書士や社労士との提携がある
- 利益を考慮した資金繰りを計画してくれる
- 具体的な実績件数の記載がある
- 建設業に相性の良いITソフトに関するアドバイスができる
- コンプライアンスに関する知識がある
- 建設業ならではの経理や税務の知識を理解している
- 業界の動向や法改正への対応がスムーズ
行政書士や社労士との提携がある
建設業では、建設業許可の取得・更新や経営事項審査、社会保険手続きなど、他士業との連携が不可欠な業務が多く発生します。そのため、行政書士や社労士と提携している税理士事務所を選ぶことで、必要な手続きをワンストップで受けられる点が大きなメリットです。
建設業許可に関わる手続きを行政書士に、社会保険や労災手続きは社労士に連携して依頼できる体制が整っている事務所であれば、申請の手間や時間を大幅に減らせます。また、必要に応じて、つながりを活かしたサポートも受けられるため、安心して任せられるでしょう。
利益を考慮した資金繰りを計画してくれる
建設業は受注から入金までの期間が長く、資金繰りに悩む企業も少なくありません。そうした中で、利益確保と資金繰り改善の両面をサポートしてくれる税理士の存在は非常に心強いものです。
売上や支出の流れを整理し、利益を残すための計画を立ててくれる税理士に依頼すれば、キャッシュフローの改善が期待できます。さらに、金融機関との融資交渉に強い税理士であれば、資金調達の面でも有利なサポートを受けられるでしょう。このように、経営基盤を強化していきたい方には、資金繰りに詳しい税理士をおすすめします。
具体的な実績件数の記載がある

建設業に対応する税理士を選ぶ際には、どれだけの実績を持っているかを確認することが重要です。具体的な対応件数や業種別の顧問先割合などが明記されている事務所であれば、信頼して相談を始められるでしょう。
自社と同規模の建設業者への支援実績があれば、経営の悩みに対して的確なアドバイスが受けられる可能性が高まります。さらに、これまでに手掛けた建設業許可の申請数や、融資支援実績なども確認しておくと安心です。実績のある税理士に依頼すれば、より専門性の高いサービスが期待できます。
建設業に相性の良いITソフトに関するアドバイスができる
会計ソフトや原価管理ソフトの導入は、建設業の業務効率に直結します。そのため、IT活用に詳しい税理士に依頼することで、事務作業の効率化やミスの防止に大きな効果が期待できます。
たとえばクラウド型会計ソフトの導入支援や、建設業特有の工事台帳との連携方法など、業種に適したITツールの選定・運用支援を受けられる税理士事務所がおすすめです。操作方法の研修や、導入後のフォロー体制が整っていれば、安心してDXを進められるでしょう。
IT導入に不安がある方でも、親身にサポートしてくれる税理士を選べば、スムーズな移行が可能となります。
コンプライアンスに関する知識がある
建設業では、法令遵守の重要性が年々高まっています。特に、社会保険の適正加入や労働時間管理など、法改正によって企業の対応が求められる場面が多く存在します。
こうした中で、コンプライアンスに詳しい税理士に相談することで、労務管理や契約内容の整備など、法的リスクを未然に防ぐ支援が受けられます。また、社労士との連携がある事務所であれば、より実務的なアドバイスを受けられるでしょう。
税務調査や監査の際に不安がある場合でも、あらかじめリスクを見据えた書類管理・体制整備を進めることで、安心して本業に取り組める環境を整えられます。
建設業ならではの経理や税務の知識を理解している
建設業には、工事進行基準や完成基準といった独自の会計処理があり、他業種と同じ対応では正確な申告が難しい場面もあります。そこで、建設業特有の経理や税務に精通している税理士に依頼することで、適切な処理を進められるようになります。
たとえば、外注費と人件費の適切な区分や、工事ごとの原価配分、経費の計上時期など、建設業に詳しい税理士であればスムーズに対応してもらえるでしょう。帳簿のチェックや勘定科目の見直しにより、税務リスクを減らし、無駄な納税の防止も期待できます。
業界の動向や法改正への対応がスムーズ
建設業界は法改正が頻繁に行われる業種であり、常に最新の制度に対応していく必要があります。社会保険加入の義務化や働き方改革の影響など、制度対応に追われる場面も少なくありません。
その点、建設業界の動向に明るく、法改正の影響を踏まえたアドバイスができる税理士であれば、早期に必要な対応策を講じることができます。帳簿の修正や手続きの見直し、関係機関への申請サポートなども期待できるでしょう。変化の激しい業界で安心して事業を続けるためにも、対応力のある税理士を選ぶことをおすすめします。
【目的別】建設業に強い税理士の選び方

建設業を営むにあたって、以下のような目的にあった税理士の選び方も大切です。
- 税理士との顧問契約を検討したい
- さらに大きな規模の工事をとりたい
- 事業拡大を目指して現状の分析をしたい
- 資金繰りに対する苦手意識の解消
- 人材不足の解消
- 労働環境の改善
ここでは目的別に適した税理士の選び方を紹介していきます。
税理士との顧問契約を検討したい
創業間もない方や個人事業主の場合、税理士との顧問契約に踏み切るかどうか悩むことがあるかもしれません。そのような場合は、記帳代行サービスに対応する税理士を選びましょう。経理の負担を軽減できるうえ、専門家のチェックで税務処理のミスを防げます。
契約は月額1〜3万円程度が目安となっており、試しやすい価格帯である点も魅力です。記帳代行のみの依頼からスタートし、対応や相性を見て顧問契約に移行する方法もおすすめです。実際にサポートを受けることで、自社に合う税理士かどうかの判断がしやすくなるでしょう。
さらに大きな規模の工事をとりたい
現在より大規模な案件を受注したいと考えている場合、資金調達の強化と建設業許可の取得・更新が不可欠です。そのためには、融資に強く建設業に特化した税理士の支援が有効です。業界知識を備えた税理士であれば、金融機関に信頼される決算書の作成や、事業計画書の策定支援にも対応してくれます。
また、行政書士と連携して建設業許可の手続きもスムーズに進められるため、時間や労力の削減にもつながります。大規模工事の入札参加に必要な書類作成なども含め、拡大戦略において多角的な支援を受けたい方にとって、経験豊富な税理士は心強いパートナーとなるでしょう。
事業拡大を目指して現状の分析をしたい

将来的な事業拡大を見据えている経営者にとって、現状の財務分析と改善プランを提案してくれる税理士の存在は欠かせません。税務や会計にとどまらず、経営コンサルティングも進める税理士を選べば、収益性やコスト構造の見直し、課題抽出といった戦略的な支援を受けられます。
さらに、デジタル技術の導入に精通している税理士であれば、業務効率の向上やシステム導入のアドバイスも受けられるでしょう。経営全体を見渡したうえでの提案が得られるため、ビジネスが軌道に乗り始めている企業にとっては非常に有益な存在となります。
資金繰りに対する苦手意識の解消
建設業での資金繰りは、現場の運営や将来的な投資計画にも大きく影響します。入金と支出のタイミングがズレやすく、資金繰りの管理が複雑になる建設業では、キャッシュフローの改善に強い税理士の支援が不可欠です。
資金繰りに精通した税理士であれば、収支バランスの見直しや支払いサイクルの調整、融資申請に有利な資料作成のアドバイスも受けられるでしょう。また、仕入れ先との交渉に関する戦略的な助言が得られるケースもあり、経営安定の鍵となります。そのため、資金管理に不安を感じている方は、資金繰りに実績のある税理士をおすすめします。
人材不足の解消
建設業では慢性的な人材不足が大きな課題となっています。職人や現場監督など専門職の確保と定着を図るためには、人事・労務に強い税理士や、社労士と連携している税理士事務所を選ぶようにしましょう。労務改善や採用支援、就業規則の見直しなど、人的資源に関する課題解決を多角的にサポートしてもらえます。
また、福利厚生制度の導入支援や給与設計の見直しなどを通じて、従業員の定着率向上にもつなげることが可能です。税理士が経営と人材戦略の両面に精通していれば、建設業の安定運営に大きな助けとなるでしょう。
労働環境の改善
労働時間や待遇に課題を感じている建設業者の方は、労働環境の改善に強い税理士を選ぶことがポイントです。社労士との連携がある税理士事務所であれば、法令遵守を前提とした労働条件の見直しや安全管理の助言など、労働環境に関する幅広いサポートが受けられます。
職場環境の改善は、従業員の離職率低下やモチベーション向上につながり、最終的には企業の生産性や信頼性にも良い影響を与えます。また、改善に伴うコスト面も含めた財務的なアドバイスも受けられるため、無理のない改革が実現できる点も魅力の1つです。
建設業に関する事柄を税理士に依頼する際の費用相場

建設業に特化した税理士に依頼する場合、以下の項目で費用相場は異なります。
- 顧問料
- 申告料・決算料
また、業務内容や事業規模によって大きく異なります。ここでは、建設業で税理士と契約する際の費用の目安を紹介していきます。
顧問料
建設業で税理士と顧問契約を結ぶ場合、月額の顧問料は1〜3万円程度が相場です。記帳代行を含めると、業務量に応じて金額が調整されるケースもあり、企業の規模や取引の複雑さによって費用が変動していきます。
月1回の訪問を希望する場合は、月額3万円程度が目安となるでしょう。訪問頻度が少ない場合には、月額1万5千円前後に抑えられるケースもあります。
顧問契約では、日常的な会計処理から経営相談まで幅広い支援が受けられます。とくに、建設業に強い税理士であれば、工事進行基準に基づいた会計処理や資金繰り支援にも精通しているでしょう。そのため、月々の経理業務の負担を軽減したい場合は、まず相談してみることをおすすめします。
申告料・決算料
申告料や決算料は、顧問料とは別に発生する費用であり、一般的には顧問料の4〜6ヶ月分が相場です。たとえば、月額顧問料が2万円の場合、決算料は8万円〜12万円程度が目安となるでしょう。
この費用には、決算書や法人税・消費税の申告書作成、節税に関するアドバイスなどが含まれます。また、決算申告に加えて税務調査の立ち会いや追加書類の作成が必要になる場合は、別途料金が発生するケースもあります。
建設業に特化した税理士であれば、工事ごとの収支計算や原価管理にも配慮した決算処理が受けられます。そのため、税理士事務所を選ぶ際は安心して経営を進められるように、費用とサービス内容の両方を確認してみましょう。
建設業に強い税理士に依頼できないもの

建設業に強い税理士であっても、以下の業務には直接対応できません。
- 建設業許可申請
- 労働保険・労災保険の手続き
- 労働基準監督署調査
法律により業務範囲が明確に定められているため、ここでは、建設業の方が誤解しやすい業務を解説していきます。
建設業許可申請
建設業を営むうえで必要な「建設業許可」の申請は、税理士ではなく行政書士が対応する業務です。都道府県内で営業する場合は都道府県知事、それをまたぐ場合は国土交通大臣の許可が必要になります。
これらの許可申請には多くの書類が必要となり、専門知識が求められるため、行政書士に依頼するのが一般的です。行政書士に任せることで、書類の不備や手続きの遅延といったリスクを回避できる点が強みです。
そのため、あらかじめ行政書士との連携がある税理士事務所を選べば、後々に慌てずスムーズな手続きが期待できるでしょう。
労働保険・労災保険の手続き
労働保険や労災保険に関する手続きも税理士の業務範囲外です。従業員を雇っている場合は労災保険や雇用保険の加入が義務付けられており、法人であれば健康保険や厚生年金といった社会保険の加入も必要です。これらの手続きは、社会保険労務士に依頼しなければなりません。
とくに建設業では1人親方や中小事業主向けの「労災保険特別加入制度」の利用も多く、この手続きも社労士の独占業務といえます。そのため、あらかじめ社労士と連携している税理士事務所を選び、後に困らないよう準備しておくことをおすすめします。
労働基準監督署調査
建設業では、労働環境の安全性確保が重視されるため、労働基準監督署による調査が行われる機会も少なくありません。
調査の際には、出勤簿や労働者名簿、時間外労働に関する協定書など、多くの書類が求められることになります。しかし、これらの調査対応も税理士ではなく、社会保険労務士が対応する分野です。
そのため、社労士とつながりのある税理士に依頼すれば、事前準備から調査時の対応、是正勧告への対処まで一貫したサポートが受けられます。労働関連法令に精通している社労士の支援を通して、安心して調査に臨めます。
建設業での税理士の役目

建設業は経理処理や資金管理が複雑で、以下のポイントで特に専門的な知識が求められます。
- 経費・会計処理
- 資金調達
- 帳簿の作成
- 建設業許可申請の取得サポート
- 税務書類作成
- 節税のアドバイス
ここでは税理士による、さまざまなサポートを詳しく解説していきます。
経費・会計処理
建設業においては、工事ごとにかかる原材料費や人件費など、さまざまな経費の管理が必要になります。そのため、経費区分の正確な把握と記録が重要です。
税理士に依頼することで、工事台帳の整備や外注費と給与の適切な区別など、建設業特有の会計処理を正確に進められるでしょう。
経費の過不足や記帳ミスを未然に防げるため、税務調査でも安心です。会計の煩雑さから解放されたい方には、建設業に精通した税理士をおすすめします。
資金調達
建設業では、高額な材料費や外注費が発生しやすいため、安定した資金繰りが経営の鍵となります。税理士に相談することで、金融機関からの融資申請や補助金申請に必要な書類の作成支援が受けられます。
また、事業計画書や資金繰り表の作成を通じて、説得力のある融資対策を進められるでしょう。資金繰りに不安がある方は、経営の安定を図るためにも、資金調達の実績のある税理士への依頼がおすすめです。
帳簿の作成
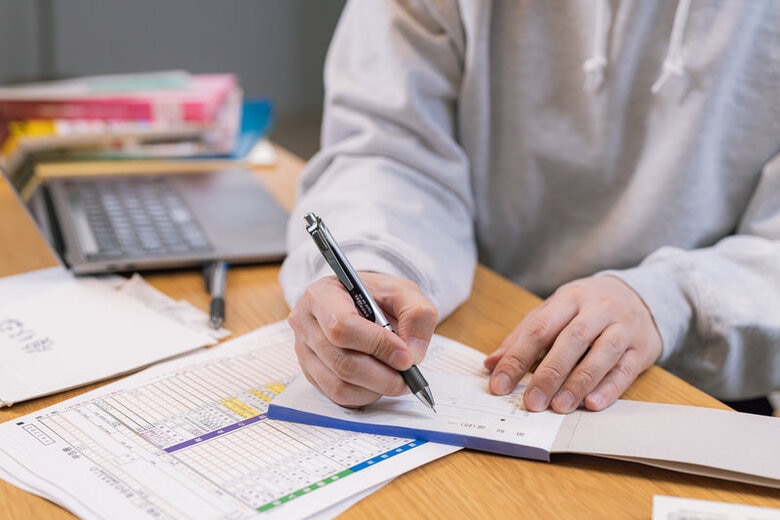
建設業では取引が多岐にわたるため、帳簿の作成と管理は欠かせません。税理士に依頼すれば、請求書や領収書をもとに、正確な帳簿を作成してもらえるため、経営者は安心して本業に集中できるでしょう。
特に月次や年次決算において、タイムリーな帳簿管理は経営判断の材料になります。帳簿の不備は税務調査の指摘につながるため、専門家に任せましょう。業務負担を減らしつつ、正確な記録を残すためにも、帳簿作成は税理士への依頼をおすすめします。
建設業許可申請の取得サポート
建設業許可の取得には多くの書類と煩雑な手続きが必要で、個人で進めるには大きな負担が伴います。税理士は行政書士と提携していることが多いため、建設業許可の申請をワンストップでサポートしてもらえるのが強みです。
特に、経営事項審査や公共工事の入札資格取得には、専門的な書類作成が求められるため、連携している専門家の存在は非常に心強いでしょう。スムーズに許可を取得したい方は、行政書士と連携のある税理士に依頼してみてください。
税務書類作成
建設業では、法人税・消費税・源泉所得税など、さまざまな税務申告が必要です。税理士はこれらの申告書類を正確に作成し、期限内に提出できるようサポートしてくれます。
帳簿の内容をもとにした決算書や確定申告書の作成のほか、税務署への対応も任せられるため、経営者の負担を大きく減らせます。記載ミスによるペナルティを回避するためにも、税務書類の作成は税理士への依頼がおすすめです。
節税のアドバイス
建設業は売上や経費の規模が大きく、税金の負担も重くなりがちです。税理士に依頼することで、最新の税制や法改正を踏まえた節税対策の提案が受けられます。
たとえば、経費の適正な計上、減価償却の見直し、補助金活用による税負担の軽減など、多角的な対策が期待できるでしょう。
節税によって経営資金を確保し、事業の成長に活用したい方は、税務のプロである税理士への相談をおすすめします。節税効果を実感できるアドバイスが受けられるはずです。
建設業に強いが税理士に依頼する際のよくある質問

建設業に強い税理士へ以下のような質問が多くあります。
- 顧客別の顧問料はどのくらい異なる?
- 顧問契約のメリットは?
- どのように料金を支払う?
ここでは、実際に多い質問とその回答のポイントを、わかりやすく解説していきます。
顧客別の顧問料はどのくらい異なる?
建設業における税理士の顧問料は、年商や従業員数、経理の複雑さなどにより異なります。たとえば、訪問頻度が多く、記帳代行を依頼する場合は、月額3万円以上が目安となるでしょう。
一方で、記帳は自社で進めて訪問も少なめにするケースであれば、月額2万円前後に抑えられることもあります。
それぞれの経理状況に応じた柔軟さが建設業に強い税理士の強みでもあるため、自社の業務内容を整理したうえで、詳しい見積もりを依頼してみることをおすすめします。
顧問契約のメリットは?
顧問契約で税務や会計に関するあらゆる相談を随時受けられるようになります。とくに建設業では、資金繰りや節税、原価管理といった課題が日常的に発生するため、税理士のアドバイスが非常に有効です。
たとえば、利益が出たタイミングでの節税対策や、突発的な資金調達が必要になったときも、素早いサポートは大きな安心につながるでしょう。
工事進行基準など業界特有の会計処理も、継続的に把握してもらえるので精度の高い対応が期待できます。
どのように料金を支払う?
税理士との顧問契約では、支払い方法も柔軟に対応してもらえる場合が多くなっています。一般的には、銀行振込や口座引き落としが主流ですが、最近ではキャッシュレス決済に対応する事務所も増えてきました。
口座引き落としは支払い忘れを防ぐことができ、事務処理の手間もかからないためおすすめです。訪問時に現金手渡しを希望される場合でも対応してもらえることがあるため、まずは希望を伝えてみましょう。
まとめ
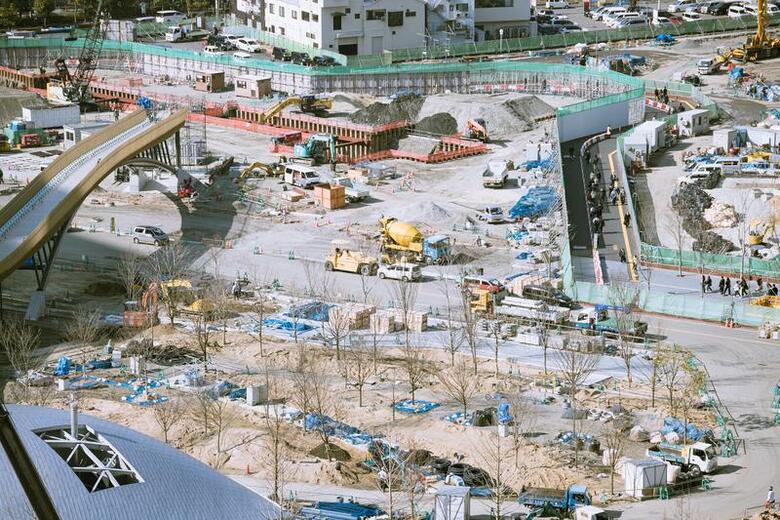
この記事では、建設業における税理士の必要性と、業界に強い税理士の選び方や費用相場を解説しました。
建設業は会計処理や税務が複雑で、他業種とは異なる独自の知識と経験が求められる分野です。そのため、建設業に強い税理士と顧問契約を結ぶことは、経営を安定させるうえで大きなメリットになるでしょう。
資金繰りや節税対策、会計処理、融資サポートなど、多角的な支援が受けられるのが特徴です。
また、行政書士や社労士との連携がある税理士であれば、建設業許可や労務管理なども一貫して任せられるため、さらに安心です。
この記事を参考にして、自社に合った税理士を選んでみましょう。
