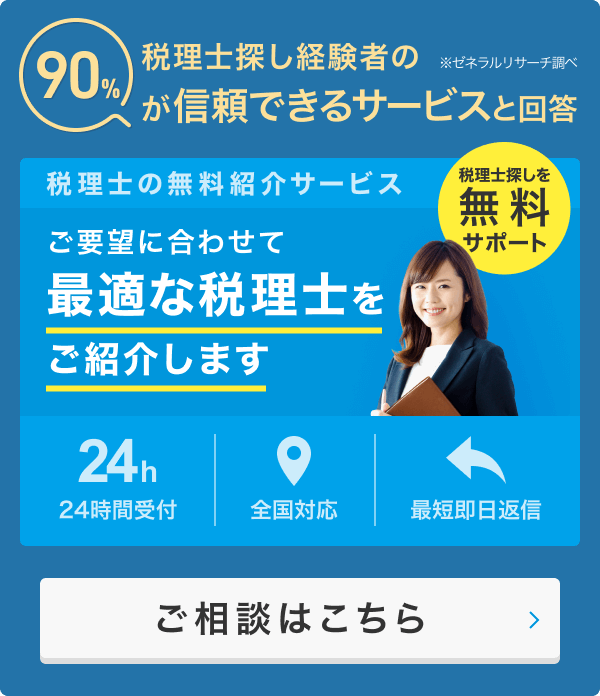インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?記入例や注意点を解説
2023年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」がはじまりました。制度の導入に伴い、免税事業者からの仕入税額控除の廃止が段階的に行われます。インボイス制度のしくみや注意点について詳しくご紹介します。
著者:山田 大悟税理士
目次
基本的な消費税の計算方法
まず、消費税の基本的な考え方を確認します。
消費税は分類でいうと「間接税」であり、税金を納める義務がある者(納税者)と、税金を負担する者(担税者)が別に存在している種類の税金です。
最終的に税を負担するのは消費者ですが、税金を納めるのは、課税対象となる商品やサービスに関して生産や提供、流通等に関わっている事業者となっています。
課税事業者は、「課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額」から「その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額」を控除して計算した消費税額を納付します。ざっくり言うと、消費税と一緒に売上げを預かり、そこから仕入にかかった消費税額を差し引き、残りを納税するということです。
この、仕入にかかった消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。この適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存しなくてはなりません。
この記事のテーマであるインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、この仕入税額控除に関する請求書がポイントとなります。
- 消費税の納税はどのように行う?計算方法や申告・納付手続きについて
- 消費税の原則的な計算方法(一般課税・本則課税の計算方法)をわかりやすく解説
- 【保存版】簡易課税制度とは?計算方法や事業区分の判定などわかりやすく解説
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、適格請求書発行事業者登録制度を創設し、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」または「適格簡易請求書」の保存を仕入税額控除の要件とすることです。
これまでは、請求書等を保存しておけば仕入税額控除の適用ができましたが、2023年10月にインボイス制度が導入されてからは、事前に登録されたインボイス発行事業者からの仕入れでないと、仕入税額控除の対象となりません。
これまで仕入税額控除を行うに際して、どのような内容の取引か(消費税の課税対象となる取引なのかどうか)ということのみがポイントであったものが、インボイス制度導入によって、取引の内容だけではなく、どのような事業者との取引なのか(インボイス発行事業者なのかどうか)という点が、問われるようになりました。
適格請求書の記載事項
インボイス発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除いて、取引の相手方の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。
適格請求書には、以下の項目を記載することを義務付けられています。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨) - 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

この例では、発行事業者の次に登録番号を記載し、また税率の異なるごとの消費税額も明示しています。
適格簡易請求書の記載事項
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業ほか、駐車場業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業者については、適格請求書に代えて、適格請求書を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。
簡易請求書では、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が不要で、税率は「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載で良いこととなっています。「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。
免税事業者からの仕入税額控除の廃止
消費税には「免税事業者」といって、一定以下の取引規模の事業者等は消費税を納める義務を免除されるという制度があります。
これまでは免税事業者との取引でも課税事業者との取引であっても、仕入税額控除を行う上では問題ありませんでしたが、インボイス制度の導入によって、この点に変化があります。
インボイス発行事業者の登録を受けるには、課税事業者となる必要があるため、免税事業者のままでは適格請求書発行ができません。必然的に取引の買手側の事業者からすると免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除ができないこととなります(一定の経過措置あり)。
また、インボイス制度導入前は免税事業者の場合、売上に伴い預かった消費税と仕入に伴い支払った消費税の差引がプラスであっても、納税の必要がありませんでした。これを一般的に益税と言いますが、インボイス制度導入に伴い益税もなくなります。
以上を踏まえ、免税事業者は、課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を受けるか、免税事業者のままで消費税を受け取らないようにするかを検討する必要があります。
経過措置について
免税事業者からの仕入税額控除の廃止については、段階的に進められることとなっています。まず、インボイス制度導入後3年間(2026年9月30日まで)は仕入税額相当額の80%、その後3年間(2029年9月30日まで)は50%の控除が可能となっています。
制度導入後の7年目から、免税事業者からの仕入税額控除が全額廃止になると覚えておきましょう。
適格請求書発行事業者の登録について
適格請求書(インボイス)を交付することができるのは、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみとなります。そのため、インボイス発行事業者になろうとする方は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要です。
なお、登録申請から登録通知までの期間は、e-Tax利用の場合で約1か月、書面での提出の場合は約1か月半ほど要します。
免税事業者の場合、インボイス発行事業者の登録を受けるためには、原則として「消費税課税事業者選択届出書(課税選択届出書)」を提出し、課税事業者となる必要があります。
ただし2023年10月1日から2029年9月30日までは、「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受ける場合は、インボイス発行事業者として登録するに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
また、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。
おわりに
なお、本制度に関しての最新情報は、国税庁が設ける特集ページにて掲載されているのでそちらをご覧ください。
インボイス制度導入は消費税のひとつの転換点です。
特に免税事業者であるならば、インボイスに登録して課税事業者になるかなど、事業上の決断をしなくてはなりません。インボイス発行事業者でなくとも、経理システムへの対応など検討するべき事項は多いです。インボイス制度についてしっかりと理解し、対応するようにしましょう。
税理士選びでお悩みなら税理士ドットコムにご相談ください

※ゼネラルリサーチ調べ