税理士に相続税申告を依頼する際の費用相場はいくら?費用相場よりも高くなるケースについても解説!
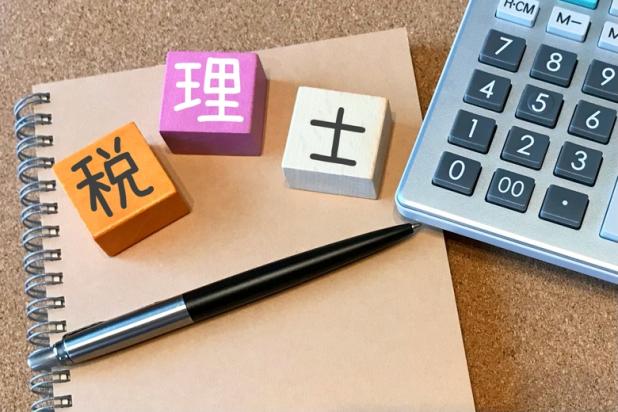
相続税の申告をしたいけど、税理士に依頼すると費用はどれだけかかるのだろうと悩んでいる方は多いでしょう。申告を依頼する場合の費用は税理士によって異なるので、場合によっては費用相場が高くなるケースもあります。そのため、事前に費用をしっかり確かめることが大切です。
そこでこの記事では、税理士に相続税申告を依頼する際の費用相場を解説します。税理士選びのコツや依頼するメリットも解説するので、これから相続税の申告を考えている方はぜひ参考にしてください。
目次
税理士に相続税申告を依頼する際の費用相場はいくら?

税理士に相続税の申告を依頼する場合、税理士に対して報酬を支払う必要があります。
相続税申告を依頼する場合、基本報酬の目安相場は遺産総額の0.5%〜1%が平均です。つまり、遺産相続の費用相場は1億円以下であれば20万円〜55万円、2億円〜4億円であれば100万円〜170万円、5億円以上であれば200万円が平均費用となります。
相続税の申告は、他の税金と比べても確定申告の難易度が高いので、高額の申告をする場合は自分で申告するのはおすすめできません。正確に申告を終わらせるためにも、相続税に強く信頼のおける税理士に依頼するようにしましょう。
税理士の相続税申告をする際の費用内訳
税理士に対して、相続税申告を依頼する際の費用の内訳は、以下の3つになります。
- 基本報酬
- 加算報酬
- その他の報酬
それぞれ詳しく解説していきます。
基本報酬
相続税の申告を税理士に依頼した際には、必ず基本報酬が発生します。
基本報酬は遺産総額に基づいて計算されるのが基本です。そのため、相続税の料金が高くなれば、税理士に基本報酬を多めに支払わなければなりません。
税理士事務所の多くは、ホームページで料金表を公開しています。報酬規定は大抵料金表で収まるようになっていますが、書類用意などで料金が加算される場合もあるので注意しましょう。
また、基本報酬は申告終了後に決まります。後々トラブルにならないためにも、報酬の決定方法は必ず税理士事務所に確認しましょう。
加算報酬
加算報酬は、相続財産の種類や相続人の人数によって加算される報酬で、基本報酬の追加料金になります。加算報酬は税理士事務所や相続内容によって料金は異なるので、事前に調べておくことが大切です。
特に、相続財産に非上場の株式がある場合、加算報酬を支払う必要があります。なぜなら、企業の規模や不動産の価格などの調査が必要となり、株式の評価に時間がかかるからです。
他にも、被相続人の財産を相続する人が1人増えていくごとに、基本報酬から10%〜15%の加算報酬がかかります。
その他の報酬
税理士に相続税の申告を依頼する場合、その他の報酬として基本報酬と加算報酬以外にも報酬を支払わなければなりません。急な依頼で申告までの期限が短い時や、税務調査に係る対応など、イレギュラーな対応の際に報酬が加算されます。
また、書類の取得代行にかかる実費も報酬に含まれるので注意しましょう。他にも現地調査にかかる旅費や交通費、戸籍や金融機関の残高証明書を発行する場合も、その他の報酬の中に含まれます。
そのため、相続税を依頼する際には、その他の報酬がいくらかかるのかもしっかり相談しましょう。
相続税申告において税理士報酬以外にかかる費用
相続税申告をする際には、税理士報酬以外にもかかる費用があります。主な費用は、以下の4つです。
- 弁護士報酬
- 遺産分割協議書作成費用
- 測量費用
- 登記費用
それぞれ詳しく解説します。
弁護士報酬
相続の際、遺産の取り分でトラブルに発展する場合があります。そうした際にトラブルを解決してくれるのが弁護士です。
弁護士を利用する際には、税理士報酬以外に弁護士報酬も用意しなければなりません。
弁護士は依頼者の代理人の立場で、相続の取り分で折り合いがつかない場合に交渉をしてくれます。裁判に発展する場合もあり、弁護士は弁護人の立場になります。
着手金は、平均で20万円〜30万円程度が相場です。しかし、遺産の額やトラブルが大きくなると、それ以上の金額がかかるでしょう。
遺産分割協議書作成費用
遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産の分割方法や割合が記載された書類のことです。
これらは本来相続人同士で自由に作成可能ですが、法的効力のある遺産分割協議書を専門家に作成してもらう場合は作成費用がかかります。遺産分割協議書の作成は、税理士だけでなく目的によって弁護士や司法書士、行政書士に作成を依頼できます。
費用は行政書士に依頼するのが1番安く、相場は約3万円程度です。税理士に依頼する場合、遺産総額の0.5%〜1%分の費用がかかります。司法書士の場合は協議書作成で約5万円ですが、弁護士に協議書作成を依頼すると10万円程度かかります。
測量費用
相続財産の中に不動産が含まれている場合、土地の測量が必要になります。もしも家族が何かの土地を持っていた場合、土地家屋調査士に依頼して、正確に測量してもらいましょう。
料金は資料調査や現地調査が3万円〜、土地の現況測量が10万円、土地の境界点を決める境界測量は4万円〜程かかるのが一般的です。他にも、資料や現地調査、測量などでいろいろ細かく料金が分けられているので、依頼前にしっかり確認するようにしましょう。
登記費用

被相続人が残した不動産の名義変更をすることを、相続登記と言います。土地や家の名義を変更する場合、司法書士に依頼する必要があるため、報酬となる費用を支払わなければなりません。
登記の種類は以下の4つがあり、登記費用はそれぞれ異なります。
- 所有権移転登記
- 所有権保存登記
- 抵当権設定登記
- 相続登記
最も安いのは所有権保存登記と抵当権設定登記で、費用は1万円〜7万円程です。相続登記や所有権移転登記は、安い場合は2万円程ですが、場合によっては10万円以上かかる場合もあります。
ただし、住んでいる地方によって値段が異なるので、事前に調べておきましょう。
相続税申告の報酬が費用相場よりも高くなるケース

相続税申告の報酬は、場合によっては費用相場よりも高くなってしまいます。報酬が費用相場より高くなるケースは、以下の5つです。
- 土地の評価が難しい場合
- 申告期限が迫っている場合
- 非上場株式が遺産に含まれている場合
- 相続税を物納する場合
- 相続人数が多い場合
それぞれ詳しく解説していきます。
土地の評価が難しい場合
相続税の申告では、土地の評価が難しいケースがあります。これは、土地の評価額がその場所や形状によって異なるためです。
例えば、間口が狭く形状がいびつな土地や賃貸マンションの敷地は、評価額が低くなる傾向があります。また、土地の種類や特性によっては、評価に時間がかかる場合があり、それに伴い税理士への報酬が高くなることもあるでしょう。
さらに、所有する土地が複数ある場合、それぞれを個別に評価する必要があります。この作業には多くの手間がかかるため、報酬が加算されることがあるので注意が必要です。
申告期限が迫っている場合
相続税の申告期限は、被相続人の死亡が判明した日の翌日から10ヶ月以内と定められています。この期限が迫ると、慌てて税理士に依頼するケースも少なくありません。ただし、急な依頼の場合、追加報酬が発生する可能性があるため注意が必要です。
10ヶ月という期間は、一見すると十分に長く感じられるかもしれません。しかし、財産の調査や必要書類の準備に時間がかかるため、意外と早く過ぎてしまいます。
多くの税理士事務所では、急ぎの申告に対応するための特別料金を設けています。申告を急ぐ場合は、事情を詳しく説明し、税理士に相談してみると良いでしょう。
非上場株式が遺産に含まれている場合
遺産に非上場株式が含まれている場合、税理士報酬が追加で発生する可能性があるため注意が必要です。上場企業の株式は市場価格を基に相続財産を算定できますが、非上場株式は市場価格がないため、評価額の査定が難しい資産です。
非上場株式の評価額を決める際には、企業の総資産や利益など、さまざまな要素を考慮する必要があります。また、専門家によって見解が分かれることも多く、手続きが複雑です。そのため、報酬が発生しても税理士に依頼することをおすすめします。
多くの税理士事務所では、非上場株式の評価に関する加算報酬を1社ごとに設定しています。事務所ごとの料金を比較し、自分に合った事務所を選ぶ際の参考にしましょう。
相続税を物納する場合
相続税を現金で支払えない場合、不動産などを代わりに納める「物納」を選択することがあります。この際、税理士に依頼すると追加報酬が発生する可能性があるため、注意が必要です。
相続税は、発生から10ヶ月以内に納付することがルールとなっています。しかし、相続税額が大きい場合、必要な現金を準備できず、支払いが難しくなることもあります。その際に物納が選択されます。
物納には「物納申請書」や「物納の理由書」などの提出が必要です。また、物納する財産の種類によっては、さらに多くの書類を用意する必要があります。これにより、通常の相続税申告よりも手続きが複雑になるため、自分で対応が難しい場合には、追加報酬を支払って税理士に依頼するのがおすすめです。
相続人数が多い場合
相続人が複数いる場合、手続きが複雑化し、必要な書類が増えることがあります。そのため、追加報酬を支払って税理士に依頼することをおすすめします。
税理士に依頼することで、節税の提案や遺産分割に関するアドバイスを受けられるため、相続に伴うトラブルを回避しやすくなります。特に、相続税には「小規模宅地の特例」や「配偶者控除」などの特例が多く含まれており、それぞれに細かな要件があります。税理士に相談することで、これらの要件を正確に理解し、最大限の節税効果を得られるでしょう。
また、遺産分割を税理士に依頼すれば、相続の条件によっては大幅な節税が可能になることもあります。なお、税理士事務所によっては、相続人が一定人数を超える場合、1人ごとに報酬が◯%加算されるかもしれないので、事前に確認しておきましょう。
適正金額で相続税申告を依頼できる税理士選びのコツ

適正な金額で相続税申告を依頼できる税理士を選ぶコツには、以下の方法があります。
- 相続に特化した税理士を選ぶ
- 報酬額を公開している税理士を選ぶ
- 安すぎる税理士は選ばない
- 複数の税理士で見積もりしてもらう
- 成功報酬制の税理士は選ばない
これらのコツを、以下で詳しく解説していきます。
相続に特化した税理士を選ぶ
適正な金額で税理士に相続税申告を依頼するためには、相続に特化した信頼できる税理士を選ぶことが重要です。相続税の申告には特別な専門性が求められることが多いため、相続税の実績がない税理士が担当すると、手続きに時間がかかるかもしれません。
相続税申告の実績が豊富な税理士は、これまでに何十件もの申告を担当しており、さまざまなケースに対応した経験があります。これにより、申告時に発生する課題に的確で迅速に対応できるでしょう。
スムーズに相続税の申告を完了させるためには、相続税に強い税理士を慎重に探し、選ぶことが大切です。依頼前に実績や専門性を確認することで、安心して手続きを進めることができます。
報酬額を公開している税理士を選ぶ
相続税に強い税理士は、過去の報酬額を公開しているケースが多いです。そのため、なるべく報酬額を正直に公開している税理士を選ぶようにしましょう。
報酬額を公開していない税理士事務所は、さまざまな追加報酬や莫大な成功報酬を設定しているかもしれません。逆に安すぎる場合は、相続税に関する専門知識や実績が不足しているかもしれません。
税理士を選ぶ際には、相続税に特化していて、過去の実績や報酬額をはっきり公開している税理士事務所を選ぶようにしましょう。
安すぎる税理士は選ばない

税理士を選ぶ時には、報酬が安すぎる税理士を選ぶのはおすすめできません。なぜなら、報酬が安すぎる税理士は、相続税申告の経験が不足している場合があり、相続税に関する適切なアドバイスをもらえない恐れがあるからです。
また、安すぎる税理士の中には、オプション料金として細かい料金が後から追加される可能性も高いです。まれではありますが、安い価格で誘って脱税を指南する悪徳税理士もいるので注意しましょう。
格安の税理士に依頼する場合は、事前に報酬額やオプション料金の有無などしっかり確かめておくことが大切です。
複数の税理士で見積もりしてもらう
税理士事務所では、相続依頼にかかる費用の見積もりに応じてくれるため、複数の税理士に見積もりを依頼し、候補を絞り込むことをおすすめします。ただし、費用が安いという理由だけで税理士を選ぶと、後々のトラブルにつながるリスクもあるため、慎重に比較することが大切です。
見積もり作成の際には、税理士から家族構成や相続財産の詳細について質問されることが一般的です。財産の内容が曖昧な場合、正確な見積もりを出すことが難しくなるため、事前に財産の内容を整理し、答えられるよう準備しておきましょう。
また、一部の税理士事務所では、見積もりの段階で契約をすすめられる場合もあります。費用や内容に納得がいかない場合は、即答せず見積もりを持ち帰り、検討してから判断しても問題ありません。
成功報酬制の税理士は選ばない
税理士に相続税申告を依頼する際は、成功報酬制を採用している税理士を選ぶのはおすすめできません。なぜなら、成功報酬制の場合、失敗を避けるために強引な融資を実行してくる恐れがあるからです。
成功報酬制の税理士は豊富な実績を持っているため、交渉に強いメリットを持っていますが、成功した場合の報酬はかなり高くなるデメリットがあります。他にも成功のみに重きをおくので、細かなサポートが不足する傾向もあります。
特に初めて相続税申告を税理士に依頼する場合、申告に関しては細かい相談が必要となるケースもあるので、なるべく成功報酬制の税理士は選ばない方が無難です。
相続税申告を税理士に依頼すべきケース

相続税申告を税理士に依頼するべきケースには、以下の3つのケースがあります。
- 評価しにくい財産がある場合
- 二次相続を控えている場合
- 遺産総額が1億円以上の場合
それぞれ詳しく解説します。
評価しにくい財産がある場合
財産の中に評価しにくいものがある場合、相続税申告を税理士にお願いすることをおすすめします。評価しにくい財産とは、相続税の中に不動産や非上場株式が含まれているケースです。
土地の相続税の評価額は路線価を元に算出しますが、土地の形状によっては路線価を修正する必要があります。そのため、申告の際には不動産の専門的な知識が必要です。また、非上場株式に関しても、企業規模や不動産評価の決定など専門的知識が必要になります。
これらの算出は個人ではかなり難しいので、不動産や非上場株式に詳しい税理士に依頼して評価をしてもらいましょう。
二次相続を控えている場合
一次相続の相続人であった配偶者が二次相続を控えている場合、税理士に相続税申告を依頼するのがおすすめです。二次相続の場合は、起訴控除額が少なくなり配偶者控除が減ってしまうので、相続税額は一次相続より高くなります。
そのため、一次相続の時点で二次相続を意識しておかないと、双方の相続人である子供が多く納税を負担しなければなりません。そのため、正しい遺産分割方法を税理士に相談すれば、二次相続を見据えた具体的な提案を提示してくれます。
二次相続は一次相続と比べて、家族間で取り分を巡ってトラブルに発展するケースも多くあります。税理士に相談すれば、さまざまな遺産の分け方に応じた対応方法を提案してもらえるので、気軽に相談してみましょう。
遺産総額が1億円以上の場合
遺産総額が1億円以上の高額になる場合、税理士に相続税申告を依頼するのがおすすめです。なぜなら、遺産総額が高ければ高いほど、税務署による税務調査が行われる可能性が高いからです。
もしこれらのケースで税務署から申告漏れを指摘された場合、ペナルティとして追徴課税が課せられるかもしれません。高額の遺産相続をする場合は、税理士に相談して対策をねってもらうようにしましょう。
税理士に相談すれば、家庭の状況などを配慮して最善の対策を提案してくれます。トラブルや申告漏れを防ぐためにも、早急に税理士に相談しましょう。
相続税申告を税理士に依頼するメリット

相続税の申告手続きを税理士に依頼するメリットには、以下の4つの理由があります。
- 申告手続きの手間が省ける
- 正確に申告ができる
- 納税額の過不足をなくせる
- 税務調査に入られるリスクが減る
それぞれ詳しく解説します。
申告手続きの手間が省ける
相続税の申告手続きを税理士に依頼する最大のメリットは、手続きの手間を大幅に省けることです。相続税の申告期限は、相続発生から10ヶ月以内と決められており、書類の準備や相続財産の計算には、場合によっては数ヶ月以上の時間がかかることもあります。
また、特例や制度の適用可否を見極め、正確に相続財産を計算する必要があります。財産の種類や内容によっては非常に複雑な作業となり、多くの時間と労力が必要です。そのため、これらの手間を避け、スムーズに手続きを進めるためには、税理士に依頼することが有効です。
税理士に依頼することで、専門的な知識と経験を活用できるため、適切な申告ができるだけでなく、トラブルのリスクも軽減できます。
正確に申告ができる
税理士に相続税申告を依頼するメリットの2つ目は、正確に申告ができるところです。もし自分で相続税申告をしたとしても、財産の計上漏れを税務署から指摘された場合は修正に時間がかかる場合があります。
修正に時間がかかって申告期間を過ぎてしまうと、申告漏れとみなされて延滞税や過少申告加算税などのペナルティが与えられてしまいます。こうしたリスクを避けるためにも、税理士に依頼して正確な申告をした方が安全です。
納税額の過不足をなくせる
税理士に相続税申告を依頼するメリットの3つ目は、納税額の過不足をなくせることです。税理士は減額ポイントなど特例を有効に活用して、少しでも相続税が安くなるように対策しています。
税理士に依頼することで、過度な納税や計上漏れによる過小申告を防ぐことが可能です。過払金請求などの不要な作業をしないためにも、税理士報酬を払ってでも税理士に対応してもらいましょう。
税務調査に入られるリスクが減る
税理士に相続税申告を依頼するメリットの4つ目は、税務調査に入られるリスクを減らせることです。申告書の1番下には、作成した税理士の名前を書く署名欄があり、自分で作成する場合にはそこに名前を記載しなければなりません。
この場合、税務署からは申告のミスがあるのではと疑われる可能性が高く、申告漏れを調べるために自宅に税務調査が入ってくるリスクがあります。このような負担を減らすためにも、税理士に依頼して書類を作成した方が無難です。
税理士報酬に関するよくある質問
ここからは、税理士報酬に関してよくある疑問に回答していきます。税理士報酬の支払いや控除の方法など、初めて税理士に依頼する場合わからないことが多いと悩んだ方は多いのではないでしょうか。
税理士報酬の支払いに関してお悩みの方は、ぜひこちらの項目を参考にしてください。
税理士報酬は相続財産から控除できますか?
基本的に、税理士報酬は相続財産から控除はできません。
相続財産から控除ができるのは、葬儀にかかる費用を除いて相続開始時に債務の確定している金額のことです。税理士報酬は、相続発生後に確定する金額のため、控除の対象からは外れます。
他にも、相続登記の作成費用や不動産の解体費用、相続財産の名義変更や戸籍標本の作成も控除の対象からは除外されます。そのため、相続税を計算する際には控除の範囲であるかどうかをはっきり見極めるのが大切です。
税理士報酬を支払うタイミングはいつですか?
税理士報酬を支払うタイミングは、相続税申告の前後に支払うようにしましょう。税理士事務所によっては前金が必要になる場合もあります。そのため、事前に税理士事務所に確認を取ることが大切です。
税理士報酬を支払うタイミングは、基本的に初回訪問時から詳細が語られます。その際、疑問点は必ず質問するようにしましょう。ただし、説明がされない場合もあるため、必ず支払いに関しては質問するようにしてください。
税理士報酬は誰が支払いますか?
税理士報酬は、家族の誰が支払っても大丈夫です。
税理士報酬の支払いは、必ずこの人が支払わなければならないと法律では決まっていません。1人で全額負担も可能ですが、相続人全員で折半もできます。
ただし、税理士は相続人の代理人に税理士費用を請求するため、支払いの際には折半でも代表者がまとめて支払わなければなりません。また、子供が税理士報酬を支払うケースになった場合、親が税理士報酬を支払ってしまうと贈与としてみなされて贈与税を支払うケースになる場合もあるので注意が必要です。
まとめ
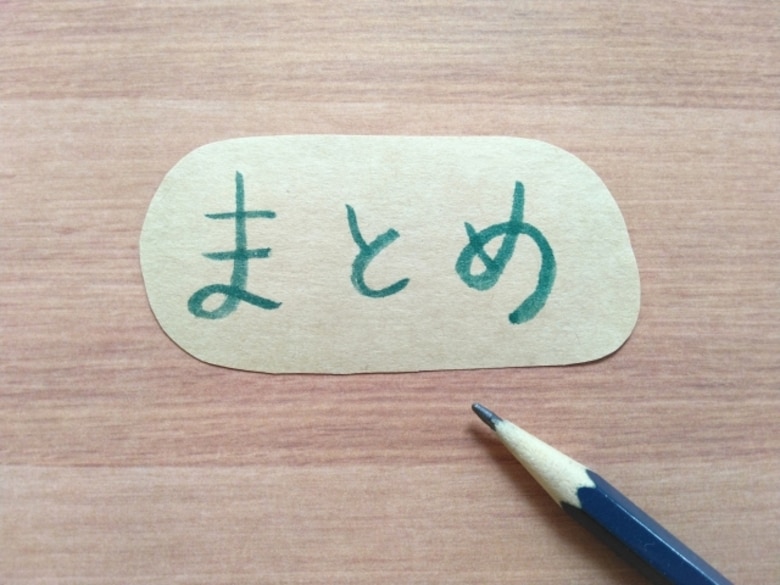
この記事では、税理士に相続税申告を依頼する際の費用相場と、費用相場よりも高くなるケースを解説しました。
相続税申告を依頼する場合、遺産相続の費用相場は1億円以下では20万円〜55万円、2億円〜4億円であれば100万円〜170万円、5億円以上であれば200万円が平均費用です。
上記の基本報酬以外にも、申告期限が迫っている場合や土地の評価が難しい場合には追加料金が発生して、費用相場が高くなります。この記事を参考にして、税理士に相続税申告を依頼する際の参考にしてください。
