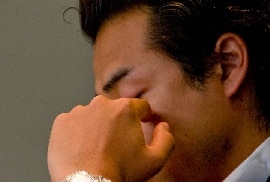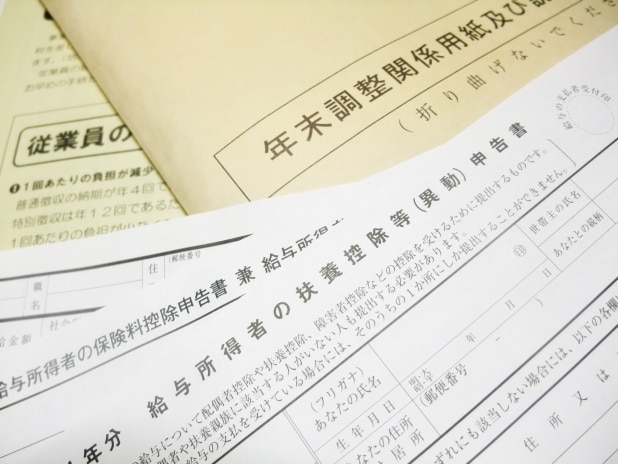なぜオーナー社長は息子が「ボンクラ」でも会社を継がせてしまうのか?
経理・決算

「どうして二代目社長って無能な奴しかいないのですか?」。こんな質問がインターネットのQ&Aサイトに寄せられている。社長の息子が後継ぎとなるのは、中小企業においては珍しくない話だが、必ずしも能力的に十分ではないケースもあり、従業員の不満が高まることになる。
別の投稿では、中小企業で経理を担当しているという女性が、社長の息子に苦労していることを打ち明けていた。会社の経費を使い込んで遊び呆ける一方、仕事の出来はめっぽう悪い。社長に苦言を呈そうにも、息子を甘やかすばかりで解決の糸口が見つからないという。
能力不足であっても、社長の息子(または娘)が後継ぎとなってしまうのはなぜだろうか。お金の面と、それ以外の面から考えてみたい。
●「親バカ説」から、「他に誰もいない説」まで
<親バカ説>
まずはお金以外の面から考えると、身も蓋もない話だが、社長の親バカが原因となっている可能性は見過ごせないだろう。息子(娘)がかわいいがあまり、素質がどうであれ、後を継がせたくなる。
<勉強してほしい説>
息子(娘)を甘やかしていなくても、社長の座に就かせることで責任感を増していってほしいという、教育的な意図もあるだろう。その結果、大化けして、優れたリーダーになる可能性もある。
<求心力を高めたい説>
組織の求心力を高めたいという可能性もあるだろう。家族経営の中小企業などであれば、一般社員を抜擢して、他の社員の不満が高まってしまうよりは、息子(娘)に継がせることで余計な争いを生ませないという方針も考えられる。対外的な取引においても、社長の息子(娘)という看板は、相手に安心感を抱かせるかもしれない。
<他に誰もいない説>
そもそも社長の座を継ぐ人物がいないという可能性もある。倒産などのリスクを恐れ、一般社員が事業を継ぐことに対して気後れしている場合もある。他に継ぐものがいなければ、廃業になってしまうため、息子(娘)が後継ぎになる。
これらの考え方について、お金の観点からはどのような考察が可能なのか。小林拓未税理士に聞いた。
●お金の面からみても「他に誰もいない説」が有力
「オーナー会社の社長にしてみれば、自分が築き上げたビジネスを、自分の子供に継がせたいという思いは自然なものです。ただし、最近では、オーナー会社を承継しないケース、いわゆる後継者問題が増えています。
例えば借入金。仮に事業がうまくいっていたとしても、設備投資などで借入金がある会社の社長に就任する場合、連帯保証を求められます。また、オーナー会社の非上場株式を相続する場合、換金性が乏しいのに多額の相続税を支払う場合もあります。先代社長の苦労や、それらのリスクを考えると、二代目社長になることをためらうケースも散見されます。
そこで政府は事業承継をスムーズにするために連帯保証人不要の融資制度を設けたり、事業承継税制の創設、拡充を行っています。
二代目社長がボンクラであったとしても、オーナー会社の二代目社長に他人は就任しにくいですから、後継者問題が解決し、会社が存続するだけましと言えるかもしれません。お金の面からは、<誰も他にいない説>が有力です。借入、相続、先代と比較され続けるプレッシャーなどを考えると、二代目社長もいいことばかりではありません」
【取材・監修協力税理士】
小林 拓未(こばやし・たくみ)税理士
東京都中央区にて平成19年から開業。「専門家として、長期的な視点で顧問先の発展に尽力する」ことを経営理念に掲げる。平成30年1月から社会保険労務士業務も開始。8月にオフィス拡大のため事務所移転し、10月には横浜支店を開設。
事務所名 :税理士法人石川小林
事務所URL:https://www.ktaxac.com