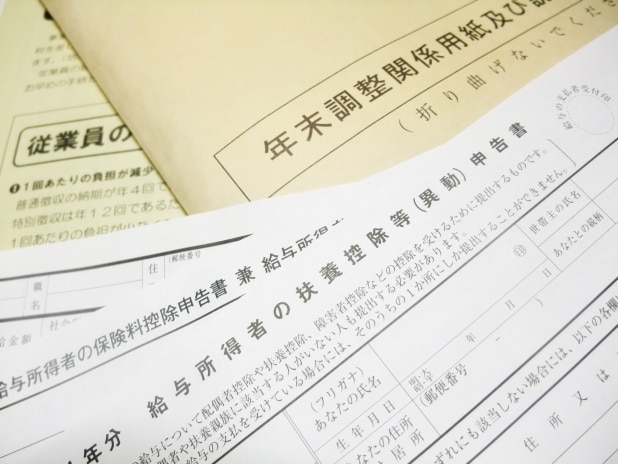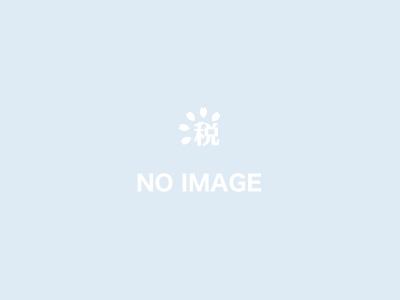投資で得た配当や利益が保険料に反映される!?どんな人が影響を受けるか、税理士が解説
税金・お金
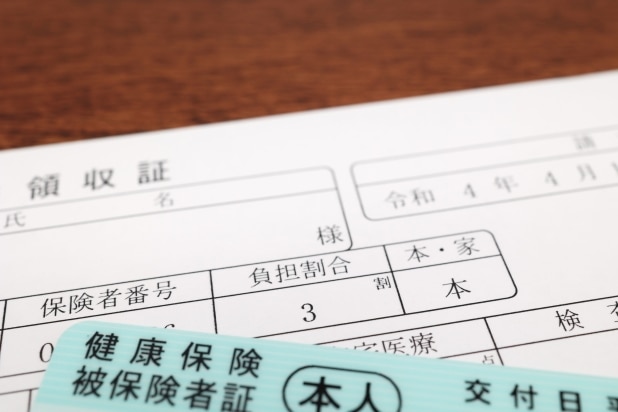
少子高齢化により、社会保障費が年々増加傾向にある中、政府は、株式配当などの金融所得を医療・介護保険料に反映する案を以前より検討中だ。
現在、医療保険や介護保険などの公的保険料は、給与や年金などの所得額に応じて決まる。さらに、上場株式や投資信託等の売買で得た収益や配当などの金融所得は、確定申告をすることで翌年度の公的保険料に反映されることになっている。
ただし、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で売却益や配当等を受け取った際には、すでに税金が差し引かれているため、確定申告の対象外となり、申告しなければ金融所得は公的保険料には反映されない仕組みとなっている。
そこで政府は、金融所得の確定申告の有無に関わらず、社会保険料に反映するという方向で検討を進めている。保険料負担の不公平な取り扱いを是正することが目的のようだ。
なお、会社員は確定申告の有無にかかわらず、賃金に応じて保険料が決まる。これは、保険料は事業主と従業員の労使折半となるためだ。
また、NISA口座で運営している分に関しては、保険料反映の対象外となるようだ。
●年金収入+配当所得年50万円で、医療・介護保険料は年6.6万円増
厚生労働省の試算によると、70代後半の単身世帯で年金収入が270万円の場合、配当所得50万円があり、これまで確定申告をしていなかったとすると、その配当所得を公的保険料に反映した場合、医療・介護保険料は年間で約6万6000円増えることになる。
また、年金収入270万円のみの場合は、医療費の窓口負担は2割、介護保険料の利用者負担割合は1割となるが、配当所得を含めると介護保険料の利用者負担割合は2割に引き上がる。
この改正案について、最終的に2028年までに結論が出される見込みだが、これにより誰が影響を受けることになるのだろうか。小林拓未税理士に聞いた。
●国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者が影響を受けることに
ーーこの検討案により、保険料増などの影響を受けるのはどのような人になるのでしょうか。
個人事業主を対象とした国民健康保険、75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者が影響を受けることになります。ただし厚生労働省は、今のところ、会社員については慎重な姿勢を示しているようです。
ーー給与所得者等の現役世代にとっては、無関係だと考えてもよいのでしょうか。
従業員等の給与所得者については、会社から支給される給与と通勤交通費の合計金額によって社会保険料が決められています。
金融所得を社会保険料に反映させることは、会社が従業員の資産を把握しなければならず、仕組み的に難しいことや、プライバシーの侵害などの問題が起こる可能性がありますので、議論が進んでいません。したがって、今のところ無関係と考えられます。
●対象者をミニマムタックスに限定するか、窓口負担割合を増やすほうが現実的
ーー政府でまだ議論が始まったばかりですが、金融所得を公的保険に反映することについて、私見でけっこうですのでご意見をいただければ幸いです。
「個人事業主としての所得はほぼゼロだが、金融所得が1億円である」というような極端なケースを想定すると、金融所得を公的保険料に反映すること自体は、一見すると合理的なように思えます。
ただし、会社員に関しては金融所得が公的保険料に反映されないままであれば、この個人事業主は対抗策をとるかもしれません。例えば、マイクロ法人を設立して、少額な給与を設定して、公的保険料を抑えるといった方法が考えられます。
結局のところ、会社員の金融所得分にも公的保険料を反映させないと不公平感が生じます。ただしその場合は、仕組みや事務手続きが複雑になり、プライバシーの問題が残ります。地方自治体における公的保険料の算出にも事務負担が増加するため、実現するにはハードルが高いと言わざるを得ません。
対象者を、ミニマムタックス(特定の基準所得金額の課税の特例)対象者に限定するか、窓口負担割合を増やす方がはるかに現実的であると考えます。
【取材協力税理士】
小林 拓未(こばやし たくみ)税理士
2017年東京都中央区にて開業。「専門家として、長期的な視点で顧問先の発展に尽力する」ことを経営理念に掲げる。2018年から社会保険労務士業務開始。横浜、葛飾、板橋、品川、船橋に支店を開設し、業務拡大中。
事務所名 :税理士法人石川小林
事務所URL:https://www.ktaxac.com