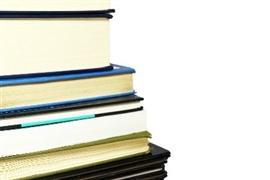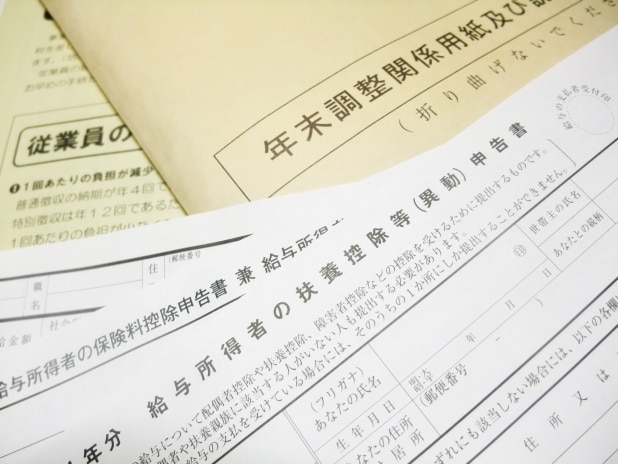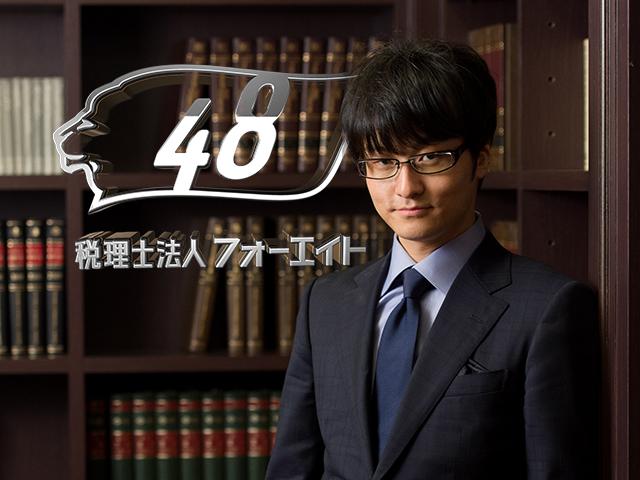「資産超過」で廃業は64.1%!黒字かつ資産を残して廃業する際の税務の注意点とは
確定申告
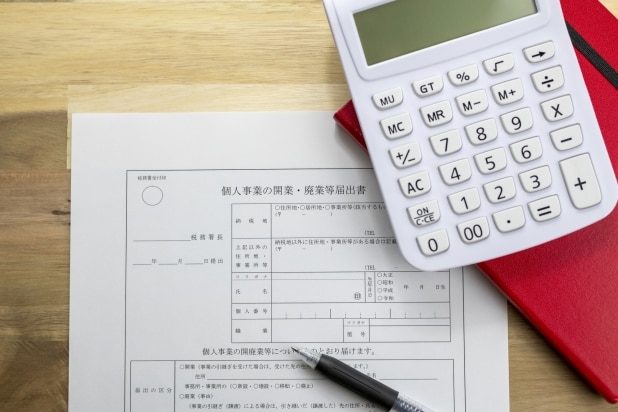
帝国データバンクの「全国企業『休廃業・解散』動向調査」によると、2025年1〜8月に全国で休業・廃業、解散を行った事業者(個人事業主を含む)は4万7078件となり、前年同期を9.3%上回り、3年連続で増加したことがわかった。
2025年1〜8月に休廃業等を行った事業者のうち、総資産が債務を上回る、いわゆる資産超過状態の割合は64.1%で、2016年以降で最高となったという。また、休廃業する直前期の決算で当期純損益が「黒字」だった割合は49.6%となり、集計を開始した2016年以降で過去最低を記録した。2025年の休廃業・解散動向は、直近の損益が悪化した事業者が多いことが特徴で、黒字かつ資産超過での休廃業の割合は16.2%となり、余力があるうちに休業・廃業する動きが顕著となった。
このように、「資産超過」かつ「黒字」で休業・廃業をした場合、税金はどうなるのだろうか。門田睦美税理士に聞いた。
●法人の場合、確定申告は「解散時」と「清算結了時」の2回
ーー黒字の状態で休業・廃業をした場合、どのような手続きが必要で、確定申告でどのような税金が課せられるのでしょうか。
まず、個人の場合は、廃業日を定めて関係当事者へ通知し、税務署へ各種届出を行います。その後通常通り、当該廃業日を含む年の確定申告を行い、所得税および消費税を納付します。その際、最終確定申告書に廃業日を記載します。
一方、法人が黒字で会社を清算して廃業する場合には、段階を踏んで手続きを行います。以下が具体的な手続きで、確定申告は解散手続き時と清算手続き時の2回行います。
1)解散手続き
営業を停止した後に、株主総会特別決議(株主の議決権数の3分の2以上の賛成が必要)を行い、清算人の選任をします。通常清算人は代表取締役が行い、会社解散の登記申請を行います。
次に、解散公告を行い、2か月以内に債権者が債権を申し出るよう通知します。
確定申告は、解散日より2か月以内に行います。営業停止までのすべての収益を含めて確定申告し、法人税および消費税、地方税を納付します。また同時に税務署へ各種届出を行います。
2)清算手続き
解散後は、債権回収や債務弁済などの整理を行います。なお、清算手続きは解散公告から2か月を経過するまで終了することはできません。残余財産(原則金銭)を確定し、株主に財産の分配をすると清算結了となり、その旨の登記を行います。
清算結了時に税務署への届出を行い、清算結了から1か月以内に清算に伴う確定申告をして、法人税等を納付します。
そして、株主に対する配当支払いに関して、源泉所得税の納付および支払調書の作成提出を行います。
●事業資産の売却・破棄した損益は、所得の計算に含まれる
ーー休業・廃業時に資産超過の状況である場合に、事業資産の売却あるいは破棄を行うと、税金面ではどうなるのでしょうか。
個人の場合、事業に直接関係のある保有資産の処分を行った場合には、その損益を所得の計算上全部または一部計算に含めることができる場合があります。
法人の場合、黒字で解散・清算する際は、資産は全て現金化し、株主へ配当可能な状態にする必要があります。そのため、原則処分した損益は、解散・清算時の所得の計算上含まれます。
なお、解散前の期に処分した場合には、当該期中の損益として計上されます。消費税課税業者の場合には、資産の売却も消費税の課税対象となります。
●法人を廃業する際の税務手続きは複雑
ーーその他、休業・廃業時における税金面での注意点があればお教えください。
個人の場合には、関係当事者への通知と税務署への届出という簡易な方法で廃業が可能ですが、法人は手続きが煩雑です。
法人税申告書の作成上、事業税の取り扱い、欠損金繰戻還付の特例、解散後の資産売却により黒字になった場合の過去の欠損金の取り扱いなど、困難な点が多くあります。期間に余裕をもって税理士に相談されることをおすすめします。
【取材協力税理士】
門田 睦美(かどた・むつみ)税理士
ワンストップで処理することが可能で、手続きごとに依頼を選ぶことの煩わしさが生じません。また、英語も堪能で、外資系監査法人の海外事務所での経験より、国際税務にも知識があります。報酬は、価格表によること、リモートスタッフの利用により安価に管理されリーズナブルになっています。
事務所名:門田睦美税理士・社労士事務所
事務所URL:https://kadotaltasroffice-lp.com/