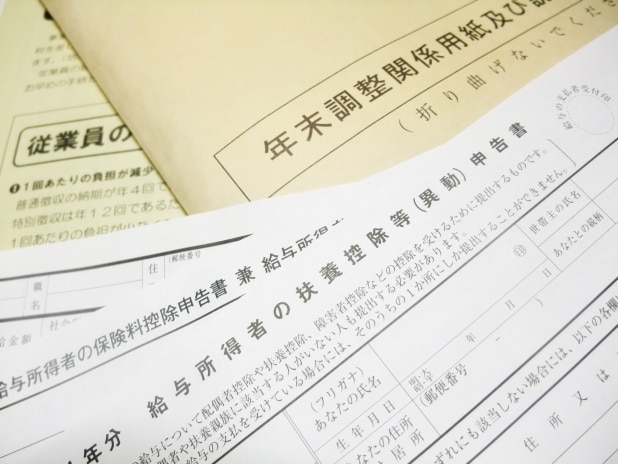加藤ローサの「離婚同居」。税金・手当の注意点は?
税金・お金

女優の加藤ローサさんがテレビ番組に出演し、サッカー元日本代表の松井大輔さんと離婚していたことを明かした。
なお、離婚後も同居していることについて、「父親と母親の役割を果たすことが共通の思い」と話した。また、離婚したことで「そもそも妻じゃないので、頑張らなくていいと思えるようになった」と続けた。
このように、子どもへの影響等を考え、離婚後も同居を続けるケースも一定数見られるが、税務や社会保障の面で注意すべき点はないのだろうか。蝦名和広税理士に聞いた。
●シングルで子どもを扶養する場合、税制優遇や手当が受けられる
ーー子どもがいる夫婦が離婚した場合、一般的なケースにおいて、税金面や手当面ではどのような変化があるのでしょうか。
離婚後は、税金や手当の取り扱いが大きく変わります。
まず、これまで「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用されていた人は、離婚により適用不可となります。一方で、子どもを扶養する親は、一定の要件を満たせば「扶養控除」に加え、「ひとり親控除」等の適用が受けられます。これにより所得税や住民税が軽減される可能性があります。
また手当面では、離婚などにより、ひとり親家庭となった場合は、申請要件を満たせば「児童扶養手当」が受給できます。なお「児童手当」については、離婚前と同様に受給可能ですが、受給者は子どもと同居している親となるため、離婚前と異なる場合には受給者変更の手続きが必要です。
●自身で健康保険への加入ほか、年金保険料などの経済的負担が生じることも
ーー社会保険や年金の面では、どのような扱いになるのでしょうか。
離婚が成立すると、今まで扶養されていた配偶者は健康保険の資格を失い、自身で国民健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。
また、年金面では、専業主婦・主夫であった場合は、離婚後に第3号被保険者から第1号または第2号への切り替えが必要です。
これにより、それまで保険料負担がなかった人も国民年金保険料を自ら納付するか、給与から厚生年金保険料が差し引かれることになり、経済的負担が増える点がデメリットといえます。
●事実上の婚姻関係と同様とみなされると、控除や手当が適用とならない場合も
ーー離婚しても同居していることで、税金面や手当面のデメリットはないのでしょうか。
離婚後も同居を続ける場合、事実上の婚姻関係とみなされると「ひとり親控除」が適用されません。
扶養親族がいる女性の方は、夫と離婚した後に婚姻をしておらず、かつ合計所得金額が500万円以下であれば「寡婦控除」が受けられますが、同居によって事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められると、寡婦控除の対象となりません。
また「児童扶養手当」は、所得制限のほか、生計を同じくしていると判断されると不支給となるおそれがあるため注意が必要です。
●離婚時の財産分与に際して贈与税が課せられるリスクも
ーーその他にもなにか税務上の注意点があればお教えください。
離婚後も同居する場合は、ひとり親控除や寡婦控除が受けられないケースがあるほか、贈与税の問題にも注意が必要です。
離婚時の財産分与は、通常贈与税の対象となりませんが、事実婚として婚姻関係を継続しているとみなされた場合は、離婚に伴う財産分与として扱われず、贈与税が課されるリスクがあります。
離婚後も同居を続ける場合には、住民票上の世帯分離を行い、家計もきちんと分けるなど、事実婚とみなされないよう注意しましょう。
【取材協力税理士】
蝦名 和広(えびな かずひろ)税理士
特定社会保険労務士・海事代理士・行政書士。北海学園大学経済学部卒業。札幌市西区で開業、税務、労務、新設法人支援まで、幅広くクライアントをサポート。趣味はジョギング、一児のパパ。
事務所名 :Aimパートナーズ総合会計事務所
事務所URL:https://office-ebina.com