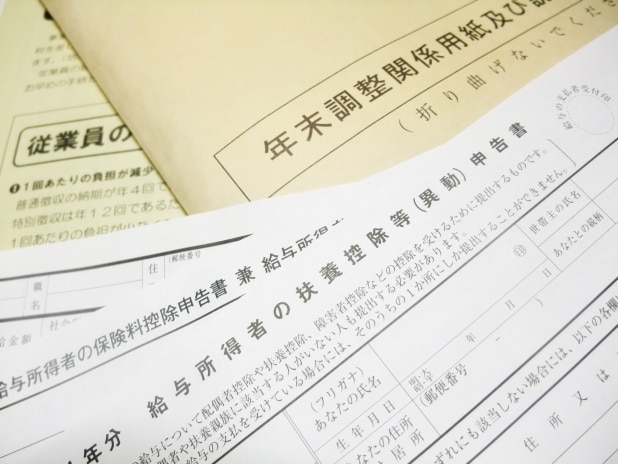「路線価」上昇で“不動産価値アップ”も、忍び寄る「増税」の影…対策はある?
相続税

国税庁は7月1日、税務における土地等の評価額の基準となる「路線価」(2025年分)をホームページで公開した。全国の平均変動率は前年比2.7%増で、4年連続で上昇した。
路線価は、道路に面している土地の1平方メートル当たりの評価額で、1月1日を評価時点として地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の8割程度を目途に定められる。
上昇した都道府県の数は35(前年比+6)で、都道府県別の上昇率は東京都(8.1%)が最大で、沖縄県(6.3%)、福岡県(6.0%)となった。報道などによると、インバウンド需要や住宅需要の高まり、駅周辺の開発などが地価上昇を押し上げているという。
毎年注目される東京・中央区銀座5丁目「銀座中央通り」の路線価は、1平方メートル当たり4808万円(前年比+384万円)で過去最高額となった。
路線価が上昇すれば、土地の資産価値も上昇する。土地のオーナーとしては悪くない話のようにも思えるが、このタイミングで相続が発生したら、課せられる「相続税」もアップしてしまうのだろうか。冨田建税理士に聞いた。
●相続税もアップするが…それよりも影響大きい「特例」の存在
──たとえば、2024年の路線価が「500万円/㎡」とされた土地(100平方メートル)があったとして、2025年の路線価が「5%上昇」だった場合、相続税はどの程度アップするのでしょうか。
仮に相続人が控除等の要件を有していない2人の兄弟で、便宜的に他の財産・債務の合計が4200万円であったとすると、基礎控除が4200万円ですので、土地が個別の格差補正要因のない整形地とすれば、基礎控除考慮後の相続財産の評価額が「(前年)5億円(500万円/㎡×100平方メートル)→(今年)5億2500万円」となります。
そして、この場合の相続税額は、2人合計で「(前年)1億7100万円→(今年)1億8225万円」となり、この額を実際に相続した財産の評価額の割合で按分して各自の相続税額として計算します。
ただし、仮にこの土地が自宅の土地であって、「特定居住用宅地等の特例」の適用要件を満たす人が相続する場合は、土地に関する相続財産の評価額が「2割」になり、「(前年)1億円→(今年)1億500万円」となります。
相続税額についても、2人合計で「(前年)1600万円→(今年)1750万円」となり、特例の適用が極めて大きいことがわかります。
●税理士がアドバイスする「相続への備え」
──路線価上昇による相続税アップに対策はあるのでしょうか。
路線価は国税庁側が定めるものですし、亡くなった時点の土地の価値を「機械的」に算定する制度ですので、明確な「アップへの対策」はありません。
強いて言えば、生前に相続時精算課税制度の活用を検討したり、遊休地に賃貸物件を建てたり、必要に応じて財産の組み換え等をするのが対策といえなくもないですが、あくまでも生前は親御さんの財産ですので対策をし過ぎるのもどうかと思います。
このような大都市部での地価の上昇は「相続人には止めようもないこと」なので、基本的に甘んじて受け入れるしかないです。
アドバイスするとすれば、以下のような内容が考えられます。
(1)前述の「特定居住用宅地等の特例」適用の有無は地価上昇よりも大きい効果があるので、「うかつに特例の適用要件を崩して税制上の損失を被ること」を避けるべきです。できれば、特例の適用の可否は生前から税理士等に相談するのが望ましいでしょう。
(2)相続税の話とは少し異なりますが、同じ財産配分の内容であっても不動産の価値が上がる程「不動産を相続する側」が有利と解釈できるので、自宅等の「不動産を相続する側」はまずは現状の土地の価値がどの程度かを把握しておきましょう。特に、遺産配分でもめることが予想され親御さんの協力が得られる場合は、可能なら公正証書遺言を作成しましょう。
【取材協力税理士】
冨田 建(とみた・けん)税理士・不動産鑑定士・公認会計士
43都道府県で不動産鑑定業務の傍ら、各種講演・執筆も行う。令和3年に「不動産評価のしくみがわかる本」(同文舘出版)を上梓し増刷。令和5年春には相続税・所得税等を解説する「図解でわかる 土地・建物の税金と評価」(日本実業出版社) を上梓した。
事務所名:冨田建不動産鑑定士・公認会計士・税理士事務所、冨田会計・不動産鑑定株式会社
事務所URL:https://tomitacparea.com