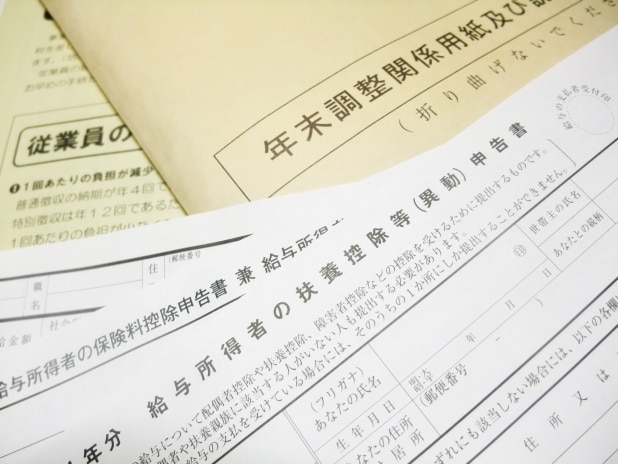10万円一律給付、「必要ない人」にも渡ってしまう問題、解決法はなかったのか
所得税

新型コロナウイルス拡大に対する経済対策として、安倍晋三首相は4月16日、所得が減った世帯に限定した30万円を給付するという当初の案を一転させ、所得制限を設けずに国民に一律10万円を給付する考えを表明しました。世論の不満を受け、修正を余儀なくされた形です。全国民にいきわたるという公平性がある一方で、本来は給付金が必要ない富裕層にも支払われることになります。租税法の専門家に評価と課題を聞きました。(ライター・国分瑠衣子)
●安倍首相「申請手続きを簡素化したい」
政府が30万円の給付を盛り込んだ緊急経済対策を閣議決定したのが4月7日です。新型コロナウイルスの影響で、住民税非課税以下の水準にまで所得が落ち込んだ世帯などを想定したもので、発表直後から国民からは「給付対象の線引きが分かりにくい」などと一律給付を求める声が上がっていました。
4月14日、自民党の二階俊博幹事長が「所得制限付きで、国民1人10万円の給付」を政府に求めることを表明し、流れは一気に変わりました。翌15日には公明党の山口那津男代表が、「所得制限なしで10万円給付」するよう補正予算案の組み換えを首相に求め、全国民に10万円が支払われることになりました。
給付される時期などは未定ですが、安倍晋三首相は「申請手続きを簡素化することで、できる限り早くお渡ししたい」と述べています。給付方法は郵送やオンラインを検討しているといいます。
●「真に必要としない人」にも渡ってしまうことの課題
30万円の現金給付案の段階から、一律給付を求めてきた香川大学法学部の青木丈教授(租税法)は「今回の給付には迅速性が求められることを鑑みれば、最もシンプルな『一律10万円』という給付に落ち着いた」と大枠を評価します。
ただし一律給付の場合は、富裕層にも同じ額が渡されることになり、「真に必要としない人」にまで給付されることになります。この問題を解消するためには、給付金を一時所得にして課税するという方法がありますが、日経新聞によると、10万円の給付金は非課税になると報道されています。
青木教授は「今回の給付金は課税対象にする必要がある。具体的にどうするかというと、所得税を課して超過累進税率を適用し、総合課税にする方法があります」と説明します。総合課税とは、1年間に稼いだ給与など総所得を全て合計して、税額を計算する仕組みです。
また、青木教授は給付金のもう一つの課題を指摘します。給付金は一時所得(所得税法34条)の扱いになります。課税額は、一時所得で得た収入金額から、所得を得るためにかかった経費と特別控除額の最大50万円を引き、2分の1を掛けます。一時所得の金額が経費を差し引いて50万円未満なら所得税は課税されません。
青木教授は「最大50万円の特別控除がある上、2分の1課税のため、しっかりと税金を徴収できないという課題もあります。給付の迅速性を優先すれば、今回は目をつぶるしかないと思いますが、今後はこのような非常時の給付金の課税のあり方について、特別控除などがない雑所得とするなどの検討をする必要がある」と話します。
●「マイナンバーを活用する方法も」
青木教授はまた、給付にあたってマイナンバーの活用を提言します。マイナンバーは、国内に住民票を置く全ての人に付番されています。「マイナンバーカードの普及率の低さが指摘されていますが、マイナンバーカード=マイナンバーではないので、カードが普及していないのなら、マイナンバーそのものの利用を考えてほしい」と訴えます。
マイナンバーは税や社会保障といった行政の事務手続きに使われていて、情報は政府も把握しています。青木教授は「だからこそ給付の手続きを自治体に丸投げするのではなく、政府主導で行うべき」と主張します。2018年1月からは、預金口座とマイナンバーを紐づける制度も始まっています。
青木教授は「マイナンバーを活用して、世帯主に自身の口座番号を届け出てもらうことで、その口座に給付金を送るという方法もある」とします。また、確定申告をしない多くの会社員は、勤務先がマイナンバーと紐づいているので、勤務先を介して給付金を支給するという方法もあるといいます。
マイナンバー制度は社会保障と税、災害対策の3分野で活用するために2016年に導入されました。しかし、「国の一方的な情報発信にとどまり、国民に利便性が伝わっていない」という不信感が根強く残っています。今回の新型コロナウイルスの感染拡大という「災害」で、政府がどう活用するかによって、マイナンバーに対する信頼度合いが深まるかもしれません。