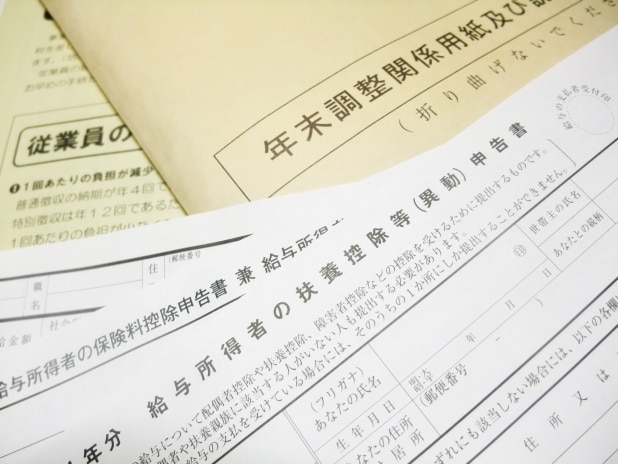哀れマイナンバー、緊急経済対策で活用される気配なし カードの交付率も低すぎて期待薄
税金・お金

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府が緊急経済対策を打ち出しました。対策では収入が減った世帯への30万円の給付や、今後の備えとしてマイナンバー制度の活用を強調していますが、実際にマイナンバーが活用される気配がありません。租税法の専門家からは「国のやる気が感じられない」と厳しい声が上がっています。(ライター・国分瑠衣子)
●緊急経済対策のあちこちに「マイナンバー」は出てくるが…
マイナンバー制度は社会保障と税、災害対策の3分野で活用するために2016年に導入され、以下の3つから成り立ちます。
(1)日本に住民票を置く全ての人に付番される12桁の番号「マイナンバー」
(2)オンラインの本人確認手段で、コンビニで住民票の写しなどを発行する時に必要な「マイナンバーカード」
(3)個人ごとに設定されるポータルサイトの「マイナポータル」
政府が4月7日に閣議決定した緊急経済対策を見ると、マイナンバーの文字があちこちに出てきます。減収世帯への30万円の現金給付を申請する時のマイナンバーカードの活用や、経済活動の回復のため「マイナポイント」を使った経済活性化策、今後への備えとしてマイナンバーカードを使った各種証明書のコンビニ交付の促進などです。
しかし、政府が出した緊急経済対策で、本当にマイナンバー制度が活躍するのかは疑問符がつきます。減収世帯への30万円の給付申請にマイナンバーカードを使う案ですが、3月1日現在で、全国のマイナンバーカードの交付枚数は1973万752枚、交付率は15.5%にとどまっています。
国はマイナンバーカードの普及を進めるため、健康保険証代わりに使えるようにしたり、消費増税に伴う消費活性化策として、最大5000円分のポイント還元を始めようとしたりしていますが、現状では交付率に大きな変化はありません。さらに新型コロナの感染拡大防止のため外出自粛が長期化すれば、カードの普及がますます進まない可能性もあります。
●現金給付にマイナンバーを使うことは困難
交付率が低いマイナンバーカードをどうやって活用するのか。給付金の受給条件などを決める本部が置かれた総務省に問い合わせましたが「マイナンバーカードを活用するかどうかも含めた検討を進めている段階です」(総務省広報室)との回答でした。
また、給付の方法を決める際、租税法の専門家からは所得が把握できるマイナンバーを使い、速やかな給付を促す意見が上がっていましたが、今回の給付ではマイナンバーは利用できそうにありません。政府の現金給付策は2020年2~6月の任意の収入が減った世帯です。
東京都杉並区の課税課の担当者は「会社員の場合、住民税は前年の収入を基に、5月中旬から6月中旬にかけて決まるので、現時点では2018年の住民税しか分かりません。今回の30万円の給付は、今年に入ってから収入が減少した人が対象なのでマイナンバーを使うことは難しい」と指摘しています。
●「持たないデメリットがないので普及しない」
ある政令指定都市で窓口業務を担当する職員は、マイナンバーカードが広がらない理由を「ポイント還元程度では住民は魅力を感じない。持たないデメリットがないので普及しない」と指摘します。マイナンバーを推進する、東京財団政策研究所の森信茂樹研究主幹は「12桁の番号が知られると、個人情報が漏洩されると誤解している人がいる。日本人の国に対する不信感もあるし、国のやる気も感じられない」と説明します。
マイナンバーの意義について国は「所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます」と説明していますが、森信氏は「これまでは国家への一方的な情報提供のみで、効果的な社会保障の給付に使われたことはない」と話し、「今こそマイナンバー制度を活用したセーフティーネットの構築が必要」と訴えます。