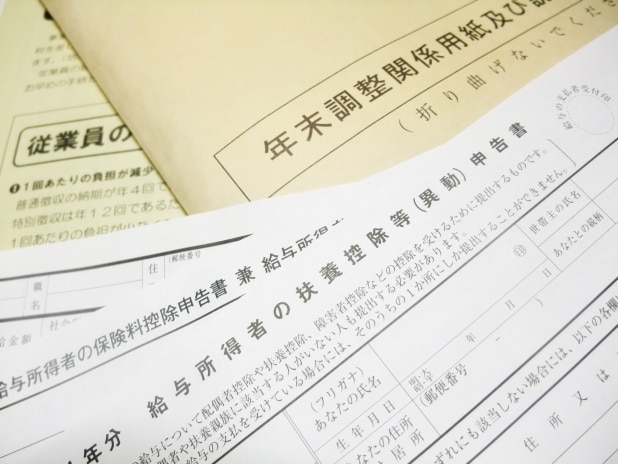ビールは値下げ、新ジャンルは値上げに。国の財政を支えてきた「酒税」ってどんな税金?
税金・お金

仕事終わりや休日の晩酌が楽しみだという人も多いだろう。「家計の都合でリーズナブルな発泡酒や新ジャンルのビール」、「特別な日はちょっと贅沢なビール」など、シチュエーションに応じて楽しんでいる人もいると思うが、2023年10月にビール系飲料の値段が変更になった。
ビール系飲料が種類によって値段が異なるのは、ビール、発泡酒、新ジャンルの区分ごとにかかる酒税の税率が異なるため。ところが酒税法の改正により、2023年10月から350mlあたりの税額が、ビール70円から63.35円(6.65円↓)に値下がり、新ジャンルは37.8円から46.99円(9.19円↑)に値上がりした。
ではそもそもなぜお酒には酒税がかかるのだろうか。三宅伸税理士に聞いた。
●嗜好品であるお酒は高い税率でも理解を得やすい傾向
ーー酒税法とはどのような税金なのでしょうか?
「酒税はアルコール飲料にかかる間接税で、その課税はアルコール度数が1度以上の飲料で行われます。酒税の歴史は古く、鎌倉時代にまで遡り、明治時代に近代的な酒税制度が導入されました。
その後、数回の改正を経て、現在の酒税制度ではお酒が発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、そして混成酒類の4つのカテゴリーに分類され、原料や製法、アルコール度数に応じて異なる税率が適用されています。話題のビールや新たなジャンルは『発泡性酒類』に分類されます。
お酒は嗜好品であり、安定的な消費量があるため、税収を確保しやすく、高い税率(※)でも一般的に受け入れられやすいため、世界各国で所得税に次ぐ税収の主要な源泉となっていた時代もありました。
20世紀初めには、日露戦争を契機に酒税が税収の第1位となり、国の財政を支えました。しかし、現在(2023年度の当初予算)では、税収に占める酒税の割合は約1%で、総額は1兆1,800億円です。」
※令和3年12月現在、代表的なビールの小売価格(税込・350ml)における、酒税額と消費税額を合わせた負担率は41.1%
参考 : 「財務省 お酒にはどれくらいの税金がかかっているのですか?」
(https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda010.html)
ーー今回の酒税法改正は、ビールメーカーにとってなんらかのメリットがあると思われますか。
「ビール類は特に人気が高いため、国は税収増加を狙い、2017年、2020年、2023年、2026年に段階的な税率の変更を行う改正を実施しています。2026年にはビール系飲料の税額は350mlあたり54.25円に一本化される予定です。
この改正により、ビールが減税され、新ジャンルは増税となるため、メーカーは市場拡大のチャンスと見て、ビールの新商品を積極的に投入する予定です。税率の変更を機に、大手メーカーなどが新商品の開発を進め、新たな味わいや選択肢が提供されることが期待されています。」
●酒税法改正はメーカーだけでなく、酒屋や飲食店も影響が
ーー酒税法改正で、一般消費者やビールメーカー以外にはどのような影響があるのでしょうか?
「本来、酒税はビールメーカーなどの製造工場から出荷されたお酒に課されますが、2023年10月1日の酒税法の改正の際には、ビールメーカーだけでなく、酒屋や飲食店も影響を受けました。流通段階にある酒税率が改正される酒類の在庫に対して、新旧税率の差額を調整する措置として手持品課税(戻税)が実施されたためです。
これにより、10月1日午前0時時点で引き上げ対象酒類を1,800リットル以上保有している場合、保有するお酒の種類によって納税が発生したり、戻税(還付)が行われることがあります。」
【取材協力税理士】
三宅伸(みやけ・しん)税理士
大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。クラウド会計の導入をすすめ、インボイス制度や電帳法にも対応できるストレスフリーな事務環境を提供。常にお客様の立場に立って考え共に成長していくことをモットーに法人及び個人の会計税務、補助金申請、起業支援、相続等と幅広く活動している。また、無申告や税務調査のサポート対応も行っている。
事務所名 :三宅伸税理士事務所
事務所URL:https://miyake-tax.jp/