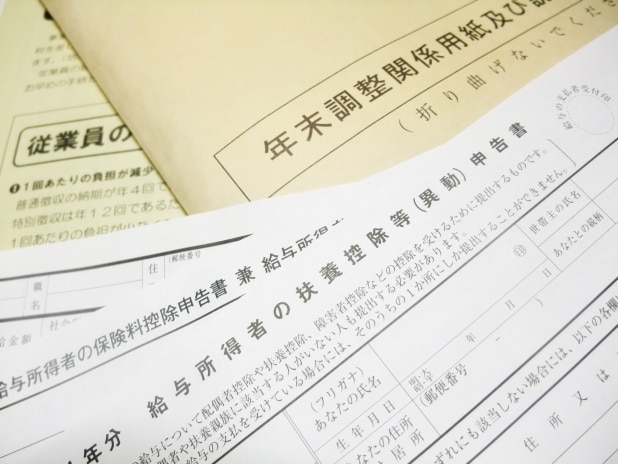「税制は物理法則じゃない。おかしいなら投票で変えるべき」三木義一氏、意識改革訴える
税金・お金

租税法の専門家で民間税制調査会のメンバーも務める、青山学院大学の三木義一学長が、7月に「税のタブー」(集英社インターナショナル)を上梓しました。宗教法人の原則非課税問題や、昔から続く印紙税の不合理性など、日本の税制が抱える課題について、鋭く切り込んでいます。三木学長は、私たち一人一人が、税の仕組みについて理解し、おかしいと感じる税制は投票へ行き、変えるべきだと訴えています。本に込めた思いを聞きました。(ライター・国分瑠衣子)
以前のインタビューはこちら
「『単一税率が世界の潮流、なぜ日本は逆行するのか』青学・三木学長、軽減税率を斬る」https://www.zeiri4.com/c_1076/n_838/
●会社員の年末調整をやめて、確定申告をすることで意識が変わる
――「税のタブー」では、暴力団の上納金に課税できるのか、政治団体の税金逃れの手法といった、これまでタブー視されてきた問題を取り上げています。
本のタイトルは、刺激的かもしれませんが、まじめに書きました。私は、宗教団体を批判する気は全くありません。ただ、課税の仕組みを正確に理解してもらいたかった。主張も入れましたが、反対論も意識して書いています。
最も伝えたかったことは、税制は国民が決めなければならないということです。おかしいところはおかしい、なぜおかしいのか理解して直さなければいけません。税制は、しょせん人間が作ったものです。宇宙の物理法則でもなんでもないのです。変えようと思えば変えられます。
――私たちが税について理解を深めるためには、どうしたらよいでしょうか。
会社員も年末調整をやめて、確定申告にすることです。会社員は、給料から税金が天引きされる源泉徴収です。会社の年末調整で済んでしまっているので、自分が納めた税金が何にどれだけ使われているのか、という意識が低くなっていると思います。
また、日本の年末調整は、必要経費の実額控除を認めていません。給与所得控除で、法律で決めた額しか控除できないようにしているのです。一方で、イギリスやドイツでは、サラリーマンも必要経費の実額控除、もしくはその選択が認められています。
●お金を取り戻す方法を考えることで、税制の問題点に気づく
――源泉徴収制度は必要でしょうか。
源泉徴収自体は必要です。フランスも2019年1月にようやく源泉徴収制度を導入しました。「源泉徴収制度は、アドルフ・ヒトラーが始めた悪魔の仕組み」と誤解する人がいますが、制度自体は、イギリスで所得税の導入とともに始まりました。納税者から見れば、支払いを受けるたびに少しずつ、支払者が国に払っておいてくれるので、負担が平準化されます。合理的な制度ですが、日本の制度は複雑すぎます。
私は、源泉徴収で給料から一律に3割を取り、確定申告をすれば税務署が還付するという仕組みを提案します。給料の受取額は減るので、つつましく生活することになりますが、2、3月に確定申告をすると、税金が戻ってきます。
そうすれば、皆が楽しみながら税金について一生懸命勉強して、どうにかして自分が稼いだお金を取り戻す方法を考えます。また、税制の問題点にも気が付くはずです。自分たちが納めた税金を国がどのように使っているかということも知ることになります。防衛費や、米国との貿易関連に充てられることが、税金の正しい使い道なのか考えるきっかけになるでしょう。
●世襲内閣は、税金を私物化してしまう
また、政治の問題もあります。財務省は政治家の顔色をうかがうので、政党や政治家がきちんと勉強して政策を実行するしかない。今は世襲政治家が多く、私情が絡んでいることが多い印象を受けます。どこかで世襲政治を断ち切らなければ、税金が私物化されかねないと危惧しています。
日本の財政は、いつおかしくなるか予測できません。あまり報道されていませんが、南米のベネズエラではハイパーインフレが起き、国家が破綻状態に陥りました。日本のような資本主義社会はどうしても格差が生じてしまいます。その格差を縮めるような政治が必要です。
●議論で終わらせずに投票に行こう
――「税のタブー」では印紙税の不合理さについても、指摘しています。過去には銀行が、住宅ローンの申込者に返信した「審査結果のお知らせ」の文書に印紙を貼っていなかったという理由で、追徴課税されたケースもあるのですね。
これが電子メールで送信した場合は、「文書の作成」に該当せずに課税されません。ファックスも文書が交付されていないという理由で課税対象外です。印紙税が日本で採用されたのは、1837年(明治6年)で、外国の制度に倣って導入しました。日本が“輸入”した税制の第一号が印紙税で、それが今でも続いているということになります。
経済界や専門家からは、廃止要望が出されていますが、財務省や与党は、税収のうちの印紙税の占める割合が多いため、廃止に踏み切りません。課税する合理的な理由がなくなっているのに、無理に課税しようとするから事業者も理解できずに、トラブルが絶えないのではないでしょうか。
このように税制の問題点はたくさんあります。議論だけで終わらせずに、おかしいと思ったら、皆さんに主権者として行動してもらいたいと思っています。税の集め方、使い方という視点から政治家たちの論調を精査し、投票という行動に移してほしいと願っています。
【プロフィール】三木義一(みき・よしかず)青山学院大学学長、弁護士、専門は税法等。