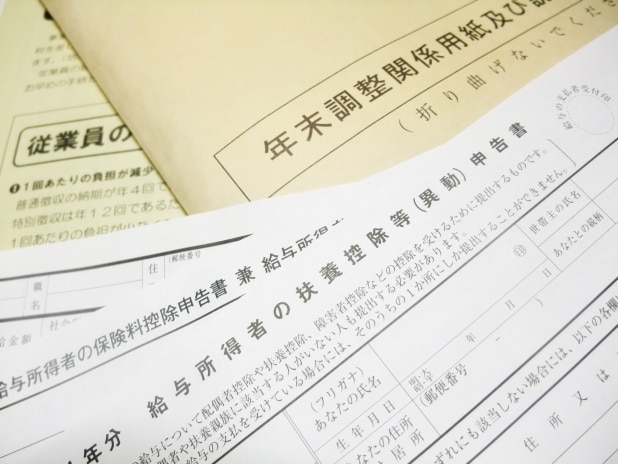飲食店の「テイクアウト酒屋」登場、町の酒屋はモヤモヤ 「酒販免許」を考える
税金・お金

新型コロナウイルスの感染拡大による経済対策で、国税庁は飲食店がテイクアウトでお酒を販売できるよう、期限付きの特例を設けることを決めました。営業時間短縮要請などが出されている飲食店への救済策で、免許が与えられた日から半年間に限り、お酒を販売できます。一方で、スーパーマーケットの価格攻勢や、コンビニエンスストアの利便性に押されてきた酒屋は複雑な思いを抱えています。静岡県内の酒屋の店主に今の心境を聞き、お酒の免許制度の歴史を振り返りました。(ライター・国分瑠衣子)
●萌え酒で独自性、静岡の銘酒も販売
「そのニュースは、酒屋の私としては思わず『町の酒屋もうダメかも…』と肩を落としてしまうものだった...」。期限付きの販売免許のニュースが流れた4月9日、静岡市の鈴木酒店の店主・鈴木誠さんはSNSとブログで、こう発信しました。ツイッター上のつぶやきには「今呑んでいるの空いたら酒屋に行くよ」「大丈夫!町の酒屋さんでも買うから」といった励ましの声が寄せられました。

鈴木酒店は創業94年。誠さんの代になって、静岡県の地酒、クラフトビール、リキュールなど地元のお酒に特に力を入れて販売しています。また、誠さんがアニメやゲームが好きということもあり、全国のアニメコラボのお酒や、静岡の地酒を使ったオリジナルの萌えキャララベルの萌え酒も扱っていて、インターネットでも販売しています。
今回の新型コロナウイルスで外出自粛要請が出され、家でお酒を飲む人が増え、量販店ではお酒の売り上げが伸びたという報道もあります。しかし、鈴木さんは「食品や生活用品などその場でいろんな買い物ができるスーパーやドラッグストアでは、同時にお酒も売れて追い風かもしれませんが、酒専門の町の酒屋に今回の家飲みの恩恵はないかもしれません。客足は減り、売り上げは減少傾向です。通販も増えていません。お財布の紐が固くなっていますね」と話します。
●「酒屋がつまらない思いをする可能性はある」
今回の飲食店の期限付き販売免許は、免許を受けた日から6カ月間、テークアウト用にお酒を販売できるというものです。手数料や登録免許税はかからず、既に開けたお酒の量り売りや、小分けの販売、宅配もできます。飲食店が所在する税務署の直接申請や、郵送、e-taxでも受け付けています。
鈴木さんは「新型コロナウイルスの影響で、飲食店への営業短縮要請が出されて、厳しさを増す中で、お酒を小売販売して利益を出すこと自体は賛成です」と話します。酒屋からお酒を仕入れている飲食店も多数あるので、一概に酒屋にとってダメージがあるとも言えません。
一方で「今回の特例免許で、立地の良い繁華街で自慢の料理とともにお酒もテイクアウトできる『飲食店の酒屋』が急増したり、郊外のファミレスなどもその流れとなってきたら、個人経営の酒屋はますます客足が遠のくのではという複雑な思いもあります。飲食店がお酒をどう仕入れ、いくらで売るか、などにもよるかと思いますが」と語ります。

国税庁が出す期限付きの酒類販売免許のQ&Aによると、飲食店が販売できるお酒の量に制限はなく、これまでの取引先から新たに仕入れて販売することが認められています。ですが、新規の取引先を開拓して仕入れることはできません。
そうは言いますが、新しくネット等で仕入れた稀少なお酒を売る飲食店が出てこないとも限りません。
販売価格についても「総販売原価を下回ったり、酒類業者の事業に影響を及ぼしたりしてはいけない」と規定されていますが、鈴木さんは「今まで実直に商いをしてきた酒屋がつまらない思いをしてしまうかもしれないという不安はあります。国税庁の見切り発車感を感じました。今回に限らず、国税庁には言いたいことはたくさんありますけどね」と笑った。
●明治期、国税のうち酒税の占める割合が3割を超えていた
そもそもお酒を販売するのに、なぜ国税庁の免許が必要なのでしょうか。それは日本の税の歴史に大きな関係があります。
明治、大正初期までは日本の税収の中心は酒と土地(地租)でした。1899年(明治32年)には国税に酒税の占める割合が3割を超えました。しかし、1918年(大正7年)には所得税が初めて酒税を抜き、税収のトップになりました。以降、酒税の占める割合は減少していき、2019年の国税収入64兆円のうち、酒税は1.3兆円と全体の2%にとどまっています。
国税庁は酒類販売免許制の公式理由を「酒税の保全」としています。ですが、租税法の専門家で前・青山学院大学長の三木義一氏は、著書「税のタブー」(インターナショナル新書)で、酒の販売免許制度が導入された背景を詳しく説明し、酒税の保全とする国の言い分に反論しています。
販売免許制度が導入されたのは、1938年(昭和13年)です。酒税の仕組みが、お酒を造った量に課税される「造石税制度」から、造っただけでは課税されず、倉庫から商品として出荷した量に対して課税される「庫出(くらだし)課税制度」に変わりました。
商品として小売業者に売ると、税金の問題が現実的になります。そこで小売業者は「庫出課税制度にするなら、取引相手の販売業者への売掛金が貸し倒れにならないよう、優良な小売業者だけお酒を扱えるように免許制にしてほしい」と訴えたのです。この要求により導入されたのが、お酒の販売免許制度の始まりです。
三木氏はまた、免許制度が始まったのは、当時の時代背景も関係しているといいます。1938年は、国家総動員法が制定され、戦時経済統制法制が本格的に導入された時期でした。経済統制の観点から、あらゆる小売業者に免許制を導入することが大きな政治課題になっていて、最終的には国家総動員法に基づく1941年(昭和16年)の企業許可令では、ほとんどの小売業が許可制のもとに置かれたのです。
●コンビニに押され、酒販店は3割まで減少
戦後、統制はなくなりましたが、お酒の販売免許制度は残りました。酒を販売できるのは多くが酒屋に限られていましたが、平成に入り、条件が緩和され、コンビニエンスストアやスーパーマーケットでもお酒が販売できるようになり、利便性や価格攻勢で押された酒屋は少しずつ姿を消しました。コンビニに姿を変えた酒屋もあります。
国税庁の「酒のしおり」によると、1995年度はお酒の販売店のうち約8割を占めていた一般酒販店は、2015年度は約3割にまで減っています。代わりにコンビニとスーパーが全体の約半分を占めています。
しかし、町の酒屋も指をくわえて見ているだけではありません。生き残りをかけて、稀少な酒をそろえて試飲会を開いたり、店で買った商品を片隅で飲める「角打ち」コーナーを設けたりしています。店主が独自の視点で仕入れた酒屋は、店ごとに違う品揃えを楽しめる魅力があります。新型コロナウイルスが収束したら、酒屋をめぐってみてはどうでしょうか。
【参考】三木義一著 「税のタブー」(インターナショナル新書)