農業における税理士報酬や税理士選びのポイントは?農園・農場を営む農家さん必見
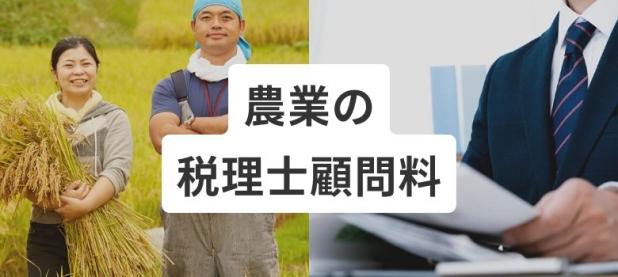
農業の経理では、他業種と比較して特殊な部分があるため、税理士選びにおいては農業に強みのある税理士を選ぶことが重要です。そこで、農業における税理士選びのポイントについて、Aimパートナーズ総合会計事務所の蝦名和広税理士にお話を伺いました。
また、実際に農業経営者の方はいくらで顧問契約しているのか、実例の一部もご紹介します。
目次
税理士費用、相場はどのくらい?
税理士に顧問を依頼するかどうか悩んだとき、まず気になるのが「報酬金額」ではないでしょうか。
税理士ドットコムでご契約された方の実績を見ると、農業を営む人が税理士に依頼したときの顧問料の平均は、個人事業主で約23万円、法人で約32万円となっています(2019年2月〜2022年11月集計)。
ただし、これはあくまで実績平均であり、実際は売上規模や、税理士に依頼する業務内容によって変わります。
実際いくら?農業の税理士報酬実例
では実際、農業を営む方がいくらで税理士と顧問契約しているのか、税理士ドットコムへのお問い合わせデータを元に実例を紹介します。
実例1)年間顧問料:150,000円
売上高700万円/農家 兼 会社役員(千葉県・個人事業主)
別法人の役員をしながら、業務委託で農業をされている方より、農業を法人化するため顧問税理士をお探しというケースです。
数人の候補の中から近くの税理士と面談され、確定申告料込みで年間15万円(税別)でご契約となりました。
実例2)年間顧問料:250,000円
売上高1500万円/農業(埼玉県・個人事業主)
経営者のお孫さんからのご依頼で、今まではご自身で青色申告されてきましたが、今後は税理士に一任したいとのご要望でした。
リモートでの対応も可能な税理士と面談され、記帳代行と税務相談、決算料込み年間25万円(税別)でご契約となりました。
実例3)年間顧問料:228,000円
売上高1440万円/農業・不動産賃貸業(東京都・個人事業主)
農業と不動産賃貸業を兼業されている個人事業主の方から、契約中の税理士のサービス内容に不満を感じ、税理士を変えたいというご要望があったケースです。
ご予算も含め希望に合う税理士と面談され、記帳代行と確定申告料込みで年間22万8000円(税別)でご契約となりました。
実例4)年間顧問料:170,000円
売上高600万円/ホップ栽培・小売(山梨県・法人)
法人設立に伴い、顧問税理士をお探しというケースです。設立直後のため、リモートでのサポートや自計化などで費用は抑えつつ、気軽に相談ができる税理士をご希望でした。
複数の税理士と面談され、希望の予算におさまり話がしやすい税理士事務所と、決算料込み年間17万円(税別)でご契約となりました。
実例5)年間顧問料:450,000円
売上高5000万円/酪農、畜産(岩手県・法人)
これまで顧問税理士はいなかったものの、設備投資した関係で経理関係が複雑になるため、この度初めて税理士をお探しされるというケースです。
ご予算も含めて希望に合う税理士と面談され、記帳代行と決算料込み年間45万円(税別)でご契約となりました。
顧問契約のメリット
実際の顧問料の予算感がわかった一方で、「思ったより金額が高かった」と感じる方もいるかもしれません。
顧問税理士をつけるかどうかは報酬金額だけではなく、そのメリットも確認した上で検討するとよいでしょう。そこでAimパートナーズ総合会計事務所の蝦名和広税理士に顧問契約のメリットについてお聞きしました。
農業経営者が顧問税理士をつけるメリットはなんでしょう?
ー 蝦名 和広税理士
まず挙げられるのは経理事務の負担軽減です。帳簿の記帳や確定申告について、税理士に代行してもらうことにより、農業に従事する時間が確保できて売上増加にも繋がります。
次に、効果的な節税対策ができることもメリットとして挙げられます。顧問契約することで最新の経営状態を常に把握することになるので、正しく確実な節税対策が行えます。
また、経営アドバイスがもらえることもあります。税理士は、事業や財務状況を把握しているため、的確な経営アドバイスを受けたり、経営上の相談相手になってもらえます。これは、農業だけでなく他の事業を兼業で行っていたり、副業で農業をされてる方も同様です。
税務処理だけでなく、節税や資金調達についても積極的にアドバイスがもらえれば、コスト以上のメリットが得られるでしょう。
「青色申告」ならこんなメリットも
顧問税理士をつけるのであれば、面倒な複式簿記での帳簿付けもお願いできるため、自力で行うより「青色申告」のハードルが低くなります。
青色申告のメリットとして「最高65万円の所得控除」がありますが、そのほか「収入保険(農業経営収入保険制度)に加入できる」「農業経営基盤強化準備金制度を受けられる」といった農業者ならではのメリットもあります。
農業に専念しつつ青色申告の各種メリットを受けたいのであれば、顧問税理士をつけ、記帳から申告までおまかせするのもひとつの手段といえるでしょう。
他業種とここが違う!農業の会計・税務
農業では経理面で特殊な部分があると聞きますが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
農業における会計・税務の特殊性について教えてください
ー 蝦名 和広税理士
農業と他の業種とでは会計・税務的に、次の4つのような違いがあります。
1)農業特有の専用勘定科目
農業簿記には、一般的な簿記では利用しない農業特有の専用勘定科目があります。
- 種苗費: 種子や苗、種芋などの購入費用
- 素畜費:育成や子豚の購入費用や引き取り運賃
- 飼料費:飼料や飼料添加物の費用
- 小作料:小作地の使用料金
- 土地改良費:水田や畑などの区画整理などの土地改良にかかった負担金額
2)棚卸しの方法
生産資材や収穫前後の農産物など、農家の方はさまざまな種類の在庫を抱えているため、種類ごとに分類して棚卸しを行います。
農業簿記の棚卸しは、次の4種類に分類して行います。
- 農産物
農産物とは、販売目的で生産した物品のことで、収穫済みの農産物や未販売で在庫として抱えているものが該当します。 - 仕掛品
仕掛品とは、農産物を生産するために栽培しているものや育成中の物品のことです。栽培中や未収穫の農産物、販売目的で飼育している動物などが該当します。 - 原材料
原材料とは、生産目的に費消される物品のことで、種子や飼料、農薬などが該当します。 - 貯蔵品
貯蔵品とは、生産や販売目的以外の用途で貯蔵されている物品のことで、燃料や包装資材などが該当します。
3)生物(果樹・牧畜)資産の管理方法
農業簿記では、搾乳牛や繁殖豚、成熟した果樹など、生産活動を行っている状態の家畜や果樹は固定資産として減価償却の会計処理を行います。
その際「生物」という勘定科目を使い、生産活動を始めるまでに要した育成費用の合計金額を固定資産の取得価額とし会計処理します。
4)個人農業者における収穫基準
農業所得の中でも「農作物」については、収穫が完了し、販売できる状態になったときに収益計上する収穫基準が適用されます。
農業に強い税理士の特徴
以上のように、本業の忙しさや経理面の特殊性を考えると、やはり顧問税理士がいると心強いでしょう。最後に「農業における税理士選びのポイント」について確認しましょう。
農業を営む方はどんな税理士を選べばよいでしょう?
ー 蝦名 和広税理士
農業経営には、通常の会計や税務処理に加えて、(1)法人化の検討(2)経営改善(3)資金調達(4)農地の相続や譲渡などのアドバイスが求められる場合があります。
このような業務には、さまざまな法律や制度が関係しているため、複合的なサポートができる税理士が求められます。
このため農業経営者は、以下のような点を考慮して自分の要望に合致しそうな税理士を選ぶとよいでしょう。
- 農業分野における実績と経験が多い
- 税理士自体が複数の資格を持っている
- 助成金や補助金などの制度に詳しい
農業に強い税理士をお探しのときは
「顧問先に農業がいる税理士事務所が良い」「法人化のサポートをしてほしい」など税理士選びでお悩みの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!
