遺産分割対象外でも相続税が課税される「みなし相続財産」とは?
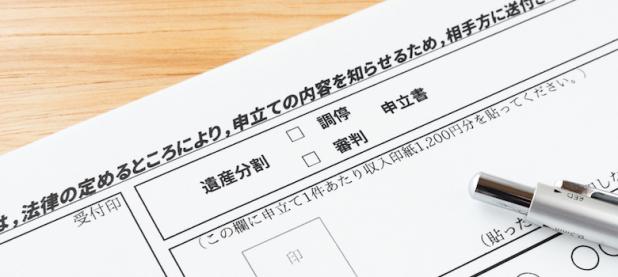
相続税の申告は、遺産分割協議で決まった分割した内容に沿って申告すればよいと考えている方が多いのですが、実はそうとは限りません。
相続税の課税対象となる財産の中には、遺産分割の対象から外れる「みなし相続財産」というものがあります。みなし相続財産は、遺産分割の必要はありませんが、相続財産の申告が必要となります。
これを見落としてしまうと、申告漏れとなることがあるため注意が必要です。そこで今回は、相続税の申告漏れの原因になりやすい「みなし相続財産」について解説したいと思います。
目次
みなし相続財産とは何か
相続財産とは、預金や不動産、有価証券など亡くなられた方が「所有」していたすべての財産のことをいい、遺産分割の対象であるとともに、相続税の課税対象財産でもあります。
一方で「みなし相続財産」とは、亡くなられた方が加入していた生命保険から受けとれる死亡保険金など、相続によって生じる「利益」のことで、亡くなられた方固有の財産ではありません。
しかし、税法上では相続財産とみなされ、他の相続財産と同様に「相続税」が課税されます。
みなし相続財産は、通常の相続財産とは違い、利益を受け取る人が契約などによって予め決まっているため、遺産分割の対象にはなりません。
そのため、みなし相続財産が相続税の課税対象であるという認識が低くなりがちで、相続税の申告漏れが起きやすいのです。
そのほか相続税がかかる財産
相続税を節税する目的で、亡くなる直前になって慌ただしく贈与するケースを防止するため、「亡くなる前3年以内」に贈与された財産についても、相続税の課税対象となります。
ただし、贈与した際に納めている贈与税については、その分相続税から控除できるため、贈与税と二重の負担になることはありません。
見落としやすい、代表的な「みなし相続財産」
相続税申告において、見落としやすい「みなし相続財産」についてまとめてみました。なお、みなし相続財産を相続人以外の者が受け取った場合は、その受取人にも相続税の納税義務が発生します。
死亡保険金
亡くなった人が保険料を負担して生命保険に加入していた場合、死亡によって支払われる死亡保険金については「みなし相続財産」として課税されます。
この際、受取人が相続人以外の者に指定されている場合は、自身にも相続税の納税義務があることを認識していない可能性が高いため注意が必要です。
例えば、亡くなった方の愛人が保険金の受取人である場合、相続人に対し保険金を受け取ったことを隠そうとする場合があります。そうなると、相続人はみなし相続財産である保険金が漏れた相続税申告をしてしまうことになるのです。
亡くなった方が生命保険に加入していた場合は、保険金が誰にいくら支払われているのか必ず確認しましょう。
死亡退職金
在職中に亡くなられた場合は、会社の規定に従って遺族に対して死亡退職金が支払われることがありますが、これもみなし相続財産に該当します。
会社によって「死亡手当金」や「功労金」など、名目は様々です。原則として亡くなられてから3年以内に支給が確定しているものについては、名目を問わず相続税の課税対象となります。
定期金
個人年金保険や収入保障保険の保険金など、定期的に一定額が給付される保険についても、相続税の課税対象となります。
一括で受け取る死亡保険金とは違い、課税対象となる評価額は、契約内容などによって違ってくるため確認が必要です。
遺言書の記載で該当するケース
発見した遺言書に、次のような遺言内容が書かれていた場合については、みなし相続財産として相続税が課税されます。
債務の免除
遺言によって借金を免除された相続人は、免除された金額を贈与されたのと同等であるとみなして、免除された金額に対して相続税が課税されます。
低額による譲除
時価とかけ離れた低い金額で財産を譲渡する旨が遺言書に記載されている場合は、時価との差額に対して相続税が課税されます。
おわりに
このように「みなし相続財産」は、入念に財産調査を行ったとしても、一見すると相続財産とは判別しにくいものもあるため、見落としてしまう可能性 があります。
相続税申告を経験豊富な税理士に依頼すれば、初心者では見落としやすい「みなし相続財産」についても、漏れなく申告することが可能です。
万が一、「みなし相続財産」が漏れたまま相続税申告を終えてしまうと、あとで税務調査が入って、過少申告加算税や延滞税などの重いペナルティを受ける可能性もありますので、リスクを回避するためにも、税理士に依頼することをおすすめします。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!
