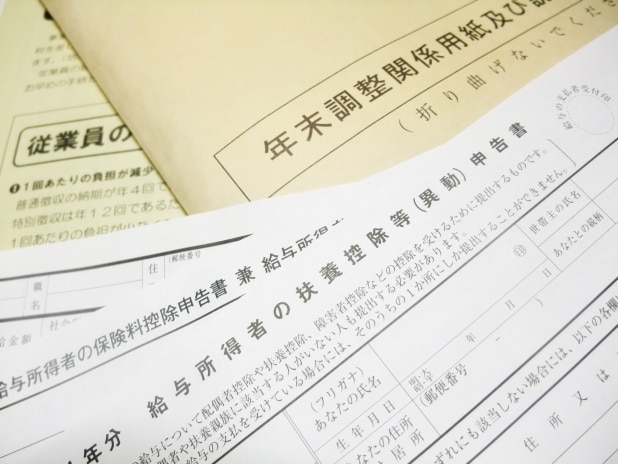軽減税率、真の混乱はこれから 適用拡大へ利権争奪戦、人も食べられるペットフードなど「変な商品」登場も
消費税

消費税増税に伴い、軽減税率制度が導入され、複数税率の運用の難しさがクローズアップされています。これまでに外食の場面でイートインとテイクアウトの複雑さや、コンビニエンスストアでイートインと申告せずに8%の税率で店内飲食をする問題が表面化しています。大蔵省(現・財務省)で主税局総務課長などを歴任し、消費税に詳しい東京財団政策研究所の森信茂樹研究主幹は「軽減税率が及ぼす影響が深刻になるのは、税率が10%以上になるこれから起きる」と指摘します。軽減税率はどのような問題点を抱えているのか聞きました。(ライター・国分瑠衣子)
●あらゆる業界団体が陳情合戦、政治家との癒着が生まれる懸念
――事業者、消費者の双方から「軽減税率は複雑すぎる」などの声が上がっています。
制度の本質的な問題が浮き彫りになるのはこれからだと思います。今も外食の場面で、イートインとテイクアウトの線引きがややこしいなどの問題が出ていますが、これは軽減税率の導入が決まる前から指摘されていたことです。後述しますが、政治的圧力によって代替案がつぶされた経緯があります。
今は軽減税率と消費税率は2%しか差がないので、それほど負担を感じないでしょう。しかし、これから消費税率が上がってくると、価格の差は当然大きくなる。例えば消費税が15%に上がれば、どのようなことが起きるでしょうか。外食産業や医療業界など今、軽減税率の対象になっていないあらゆる業界団体が「自分たちも対象に入れてほしい」と政治家に陳情するようになるでしょう。政治との癒着も懸念されます。海外では、選挙のたびに軽減税率の品目が増えている国もあります。
また、賃貸事業や学校法人といった非課税の事業者が、仕入れ税額控除を狙って軽減税率の対象になるように求めることも想定されます。不動産では住宅の貸付は非課税だし、大学の入学金や施設設備にかかる費用も非課税で、仕入れ税額控除ができません。
さらに、軽減税率が適用されるかどうか線引きに迷う商品が生まれることも考えられます。例えばペットフードは現在10%ですが、8%の適用を受けるために「人間も食べられるペットフード」が出てくるかもしれません(笑)。
また、生産・流通の面でも混乱をきたします。輸入貨物でも飲食料品に該当するものは軽減税率が適用されますが、それ以外だと10%です。大豆を輸入する場合、豆腐などの食用であれば、8%になる。しかし、飼料用だと10%になる。コメは8%ですが、飼料用米だと10%です。この線引きが明確に行われているかは疑問です。
●インボイスは税の透明化につながる
――問題が多い軽減税率制度ですが、メリットはあるのでしょうか。
2つあります。1つは2023年10月にインボイス制度が導入されることです。これまで、BtoBの世界では消費税分を適正に転嫁しにくいケースがままありました。例えば、増税後も、税込みの価格を据え置きにして、買い叩きが起きるような状況です。
インボイス制度が導入されると、事業者が売り買いする商品のそれぞれの価格や税率、税額を明記するので、転嫁が容易になります。税務署から割り振られる登録番号も記載するので、売り手、買い手、税務署の間で税金の流れが分かりやすくなります。
もう一つは、軽減税率制度の導入で、複数税率に対応するためのPOSレジが広がったことです。これまでPOSレジは半分ぐらいしか入っておらず、特に年配の人が経営している小売業などで顕著でした。POSレジが入ったことは、生産性を高め、近代化につながると思います。
●議論もされぬまま消えた「給付付き税額控除」
――そもそも軽減税率導入はどのような経緯で決まったのでしょうか。
もともとの税制抜本改革法では税金から一定額を控除する「給付付き税額控除」と軽減税率制度の2つを議論すると明記されています。給付付き税額控除とは、課税額が控除額より大きい時に、その差額を現金で支給する制度で、低所得者に限定できるので、有効と言われていました。
ただ、給付付き税額控除を行うためには、マイナンバーが必要でした。当時はマイナンバーが発行されておらず、簡素な給付措置でつなぎながら、給付付き税額控除に向けて動いていこうという考えでした。これが民主党政権(2009年9月~2012年11月)の最後のほうです。
ところが、自民党政権になり、公明党が与党になったことで、軽減税率が表に出てきました。本来なら法律に明記されているので、給付付き税額控除なのか、軽減税率なのかの議論が必要でした。マスコミも双方のメリット、デメリットについて論じるべきでしたが、私が見る限りでは一切ありませんでした。なぜか。それは、新聞が軽減税率の対象だったからです。
その後の2015年、財務省が「日本型軽減税率」という案を出しました。店頭ではいったん10%の税率を支払い、後でマイナンバーカードを使って低所得者に一部が還付される仕組みです。非常に優れた案でしたが、これもお蔵入りになりました。「カードを使っていると低所得者だと分かるので、使わないのでは」などの反対意見が出たためです。
でも今、政府は、2020年7月からマイナンバーカードを使ったキャッシュレスのポイント還元制度を始めようとしています。今振り返れば、結論ありきの「為にする議論」だったのだと思えてなりません。
●れいわ新選組に言いたい 「消費税廃止は無理」
――消費税自体は必要でしょうか。法人税を上げるなど他の財源でまかなえませんか。
党の政策として消費税廃止を訴えている、れいわ新選組の山本太郎代表に言いたいのですが、消費税の兆単位の財源を他の財源でまかなうことは不可能です。消費税と同じぐらいの兆単位の税収が期待できるのは、所得税ですが、所得税を上げれば勤労意欲をそぐでしょうし、負担が勤労世帯に偏ってしまいます。そもそも所得税最高税率を1%上げて得られる増収効果は300億円ほどと試算されています。
「だったら法人税を上げろ」という声もありますが、国際的にこれだけ税源浸食と利益の移転(BEPS)が問題になっている時に現実的ではありません。法人税を上げれば、軽税率の国に所得を集中させる課税逃れの動きが加速してしまい、国際的な批判が高まるでしょう。
――段階を踏みながら、消費税を引き上げていくのはやむを得ないと。
政治的には数年間は上げられないと思いますが、団塊の世代が後期高齢者になる2025年までに引き上げなければ、財政は持たないでしょう。生産性向上の範囲内で、1%でも0.7%上げでもいいのです。高齢者は資産はあっても所得が少ない例が多いので、所得課税することは難しい。課税できるのは消費税しかないのです。消費税を財源として、幼児教育の無償化などで子育て世代に返すというメカニズムです。消費税は社会保障目的税としての大きな機能を持っているのです。
また、市場の需要に応じてモノの価格を変える「ダイナミックプライシング」が浸透すれば、モノの値段に対する人の受け止め方は変わり、外税表示は少なくなると思います。スポーツ観戦やホテルなどでは既にダイナミックプライシングが導入されていますが、この動きが広がれば消費税もコストとしてモノの価格に溶け込むようになるでしょう。
【プロフィール】森信茂樹(もりのぶ・しげき) 東京財団政策研究所研究主幹、中央大学法科大学院特任教授。専門は租税法。近著は企業の租税回避問題を論じた「デジタル経済と税」(日本経済新聞出版社)。