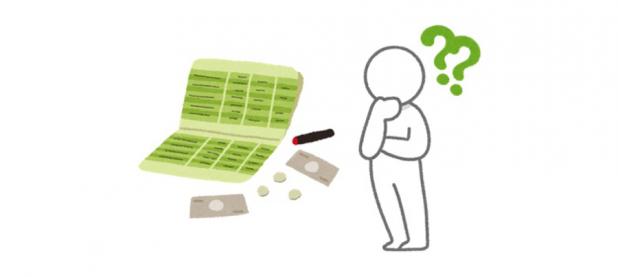自分の死後の家族への相続割振りについて
4人家族で自分の死後、通常、配偶者50%・子供2人で50%と図解がありますが、どこまで基本パターンから外れることが可能なのでしょうか?
また、無税の範囲は、基礎控除3000万、相続人600万×人数、保険控除500万×人数とありますが、相続人の中での全体金額が決まっているだけで、内訳は関係ないのでしょうか?
例えば、相続資産を配偶者10%+子供①50%+子供②40%と振り分け、発生する相続税は全て配偶者負担、というのも可能なのでしょうか?
また、遺産分割協議書は、各銀行口座、各生保会社、1つ1つに作成することが必要なのでしょうか?
それとも、生命保険で死後受取人が指定してある場合は、協議書は必要ないのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
遺言書であれば、本人(被相続人)の裁量で、遺産分割協であれば、相続人の協議で自由に遺産分割をすることはできます。
但しトラブルを避けるためには、各人の遺留分(法定相続分1/2)を配慮した遺言書を作成することがベストであると思います。
相続財産の分割がどのようにされたとしても、基礎控除額は変わりません。仮に一人だけ相続した場合であっても、基礎控除額が減少するようなことはありません。
相続税の計算は
① 各人ごと、相続財産から、過去に受けた贈与の額を加えたり葬儀費用の負担した額などを控除するなどして「各人ごとの課税価額」を算出します。
② 相続人全員の「各人ごとの課税価額」合計し「課税遺産の総額」を算出します」
③ 課税遺産の総額から基礎控除額を控除した額に税率を掛けて「相続税の総額」」を算出します。(細かい計算は割愛します)
③ 各相続人は、相続税の総額から、自分の相続分に従いそれぞれ「各相続人ごとの税額」を算出します。
※税率の加算がある場合は、この後加算されます。
そのため、各相続人ごとの税額=各相続人が負担すべき税額を、誰か一人が納税。負担した場合には、当該金額は「みなしし贈与」とされ「贈与税の対象」になりますので注意が必要です。
遺産分割協議書(遺言書の場合も含む)、財産を特定したうえで、誰に相続するかを記載します。
曖昧にしますと、争いの元となりますのでご注意ください。
ただし、死亡(生命)保険金に関しては、相続税の課税対象となりますが、民法上の相続財産ではないため、遺産分割協議者や遺言書に記載する必要はありません。
国税庁HPから参考箇所をご案内します
「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
「相続税の課税対象となる死亡保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
早々に、またとても丁寧に回答いただき、どうもありがとうございます。
税金のことを考えれば、単純に、プラスはほとんど子供に、マイナスは配偶者担当というわけにはいかないのですね。
ご回答いただいた税金との絡みを踏まえ、割振りを検討させていただきます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
御元気なうちに相続の事を考えていただき、「遺産のリスト化」と「遺言書」も含め準備をして頂くことは、ご家族の方にとってはそれだけでも負担が軽くなります。(分割の前に、相続財産の総額を確定することがそもそも難しいことがあります。)
奥様とも相談の上、割り振りをご検討ください。
本投稿は、2022年06月22日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。