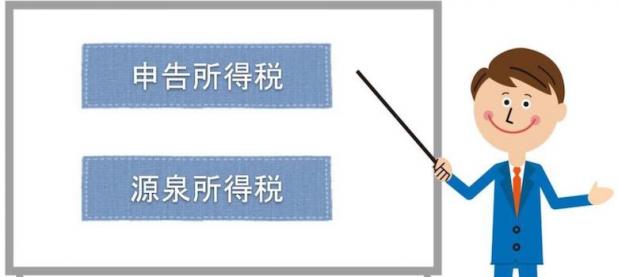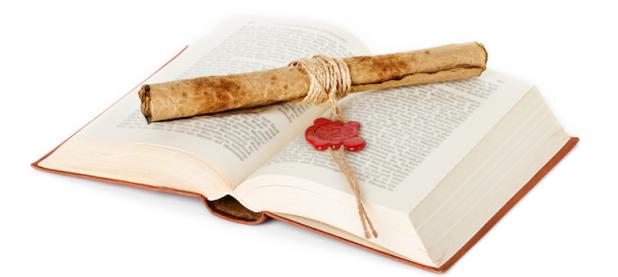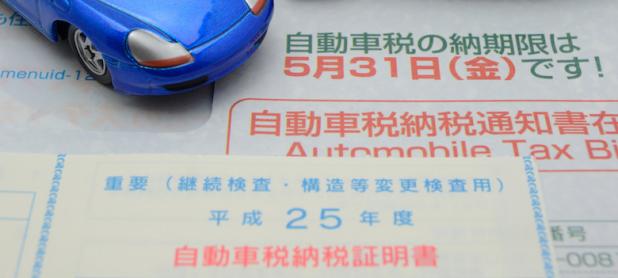確定拠出年金の毎月の拠出の最適額について
企業型の確定拠出年金の月額供出について質問がございます。
税制の優遇があるのは理解しておりますが、年金受給額に影響があるとの記載を見ました。
例えば65万円が標準報酬月額の上限かと思うのですが、
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/05.pdf こちらによると
将来の受給額を下回らないようにするには額面の給与が拠出分を差し引いて
635,000円を下回らなければ良いのでしょうか?
そうなると、例えば70万もらっている人は、65,000円までは積み立てても
将来の年金受給額は変わらないという理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
企業型確定拠出年金は、3階建て年金といわれるように「厚生年金」とは別物です。「掛金は企業が負担してくれるが、運用の結果はあくまで従業員の自己責任である」という年金で、運用成績によって将来受け取れる退職金・年金の額が変動します。
また、企業型確定拠出年金の掛金の額は会社での役職等に応じて決まりますが、制度上、掛金の上限額は以下のように定められており、この上限額を超えて企業が掛金を出すことは認められていません。
・他の企業年金がある場合 月額2万7500円
・他の企業年金がない場合 月額5万5000円
※他の企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金など。
よって、厚生年金の標準報酬月額とは何のかかわりもありません。
なお、厚生年金は標準報酬月額によって将来の年金額が決まりますが、635,000円以上の報酬になるともらえる年金額は増えません。
すみません。質問の意図が伝わってなかったかもしれません。
年金を積み立てると社会保険料が減るので将来受け取れる厚生年金が変わってくるので、そちらが減らない範囲で年収を下げたいと思っています。
逆にいうと635,000円を下回ると将来受け取れる年金が減るということでしょうか。

土師弘之
このサイトは、最近はやっている「選択制DC」の説明です。以前からある企業型確定拠出年金(DC)とは少し考え方を変えた制度になります。
企業型確定拠出年金(DC)の掛け金は企業が負担しますので、給料以外にそのDCの掛金も負担となります。
そこで、従業員に対する負担を変えずに、従業員に対する給料の金額の一部をDCの掛金に回してもらうかを従業員が選択できるようにした制度が「選択制DC」です。
その結果、企業の負担は給料の金額が限度となります。言い換えると、選択制DCを導入しなければ、従業員の給料は変わらず、DCの掛金がさらに企業の負担となります。
ですので、そのサイトにあるように、
本来30万円の月給である従業員が、そのうちの2万円を選択制DCに回してしてもらうように申請すると、当然、給料は28万円となってしまいますので、厚生年金の掛け金も減り、将来もらえる厚生年金も減ることになります。選択しなければ給料30万円は変わりません。
「つまり、現役引退後に年金(もしくは一時金)として受け取るために企業型DCの掛金として使うか、今すぐに現金として受け取って自分でその使いみちを考えるか、自分で選択できる制度というわけです。
後者の場合、現金で受け取ったものをそのまますぐに生活費として使ってしまうと、老後への備えが不十分になってしまう可能性もありますから、ご自身でライフプランニングをしていく必要性が高まるかと思います。」とサイトでは説明しています。
給料30万円を全額現金でもらいたいのか、2万円をDCにしてうまく運用できれば将来、30万円を厚生年金対象とした場合よりも多くもらえるようにしたいのか、いずれかを従業員が選択できるようにするといいものです。(所得税、社会保険料等の控除は度外視しています)
年収を下げるかどうかという問題ではなく、企業が負担する金額を変えずにDCに加入したい場合の制度ですので、企業がDCの掛金をいくらでも負担することができるのであれば、法律で定められた上限(2万7500円or5万5000円)を限度に掛金を負担すればいいということになります。
したがって、DCとは別に、厚生年金について、掛金の面から見た損得を考えるのであれば、最初に説明した通り、635,000円以上の報酬はいくら多くても将来の受け取る月額の年金は変わりません。
ありがとうございました。選択制DCでしたので、分かりやすい解説ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月25日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。