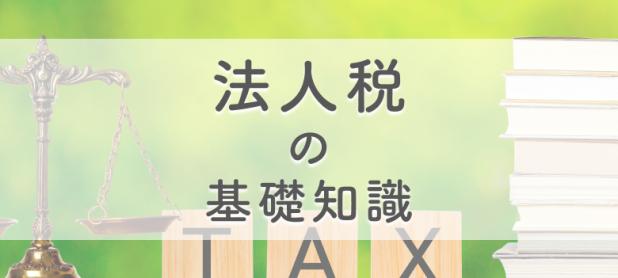地目が農地なのに長年介在農地で課税
私の土地は、昭和50年7月21日、譲渡人Aが農地法第5条第1項第3号の農地転用許可を受けた後、宅地への転用がなされないまま昭和50年8月1日、被相続人である叔父Bが売買によって所有権移転の登記完了。農地転用されないまま、昭和53年7月24日、B死去、Bの相続人C(Bの配偶者、私の叔母)も宅地に転用することなく、平成17年11月14日死去、現況、地目とも畑のままCの甥である私が平成17年11月14日相続による所有権移転登記をしたものです。
平成26年10月に宅地で課税されていることに気が付き、市に問い合わせたところ、平成27年から農地(畑)の課税に変更するとの回答でした(過去分は、見直ししない)。
理由は、「農地転用許可取り下げ申請」が出されていないため、市ではそのまま課税していましたとの回答です。
市には、平成17年11月14日に私が相続による所有権移転登記したことで登記情報が届いており、その情報に基づいて、新たな所有者である私に納税通知を発出しているにおも拘らず、登記情報の地目が畑の確認を怠り、その上、農地転用許可を受けて所有権登記したBと私は明らかに別人であることの確認もおこたり、漫然と従前の宅地で課税を続けてきたものです。さらに、地方税法第408条には、「市町村長は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければならない。」となっており、固定資産税は、現況に従って課税するのが原則であり、農地転用許可前から現在まで、航空写真等で畑であることは確認できるにも拘らず、本来、畑地で課税すべきところ、市の確認ミスにより漫然と宅地で課税してきたものですので、過払い金の返還は当然と考えですがいかがでしょうか。
国家賠償請求により過払い金の返還請求が出来るのかご意見を下さい。
以上
税理士の回答
固定資産税は「台帳課税主義」に基づいており、固定資産課税台帳のデータの修正がない年度については原則として還付等できないこととなっております。
納税者側の権利として、納税通知書の交付を受けた日の翌日から60日以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることにより、評価額についての協議を促すことができることとなっており、この権利行使がなかった場合には当年度の税額については修正ができないこととなっています。
ただし、例外的なケースですが、客観的にみて、明らかに課税側のミスにより固定資産の評価額が間違っているような場合には、直ちに評価額を修正することとなり、このようなケースであれば過年度の過大税額分を還付で取り戻すことも可能となります。
市町村側は基本的に自分達の非を認めることはしないと思いますので、事実関係を基に粘り強く担当者と交渉し、過年度の土地の評価について市町村側の過失を認めさせるか、どうしても認めない場合には訴訟を起こすことになるものと考えます。
訴訟を起こす際の根拠が、国家賠償法第1条になるのではないかと思います。
なお、法的な解釈や手段等につきましては、弁護士の先生にご相談頂ければと存じます。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2015年01月07日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。