納税証明書や課税証明書って何? 違いや取得の方法を解説!
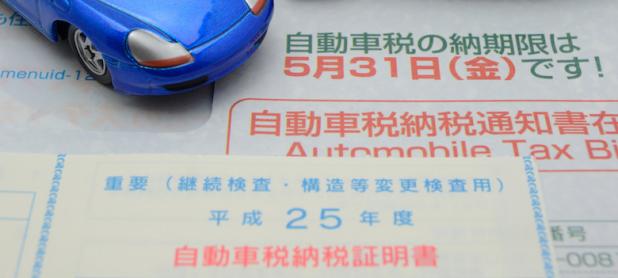
所得額や納税額等を証明する書類として「納税証明書」や「課税証明書」がありますが、これらの違いは何なのでしょうか。
今回はこれらの証明書の違いと取得方法などについて解説します。何かの場面で必要になった際に、間違わずに取得できるようにしておきましょう。
目次
納税証明書と課税証明書の違いとは?
納税証明書や課税証明書は、各種手当ての申請や奨学金・ローンの契約、保育園の入園選考などで必要になることが多い書類です。
ただし、これら2つの証明書は異なる内容が記載されており、発行元も違っています。簡単にまとめると下記のとおりです。所得税のように、自分で(もしくは自分の所属している会社が)税額を計算し、申告・納税しているものは「納税証明書」が、個人住民税のように、役所が税金を計算して通知してくるものについては「課税証明書」が発行されることになります。
- 納税証明書:主に税務署が発行する所得税額や未納状態などを証明する書類
- 課税証明書:市区町村が発行する住民税額や扶養家族の人数などを証明する書類
納税証明書の種類と取得方法
所得税や法人税といった国税に関する「納税証明書」が必要になったら、どのように取得すればよいのでしょうか? 納税証明書の種類と取得方法について説明します。
納税証明書には4つの種類がある
納税証明書とは確定申告書などを提出した方の納税額や未納税額等を証明するための書類です。そして、この納税証明書は以下の4種類に分けることができます。
- 納税証明書その1:納付すべき税額と納付した税額、未納税額などを証明する書類
- 納税証明書その2:申告した所得金額を証明する書類
- 納税証明書その3:過去に未納税額がないことを証明する書類
- 納税証明書その4:証明を受けるまでの間に、滞納処分がないことを証明する書類
このようにそれぞれの証明書で記載内容が異なるので、「どういった内容を証明したいのか」をあらかじめ確認しておく必要があります。そして、枚数等を確認した上で、間違いがないように手続きを行うことが大切です。
納税証明書を取得する3つの方法
国税に関する納税証明書を取得するには、下記の通りで3種類あります。
- オンライン(e-Tax)で交付請求の手続きを行い、窓口や郵送などで受け取る方法
- 郵送で納税証明書交付請求書を送付して、税務署から返送してもらう方法
- 窓口で納税証明書交付請求書を提出して、その場で受け取る方法
まず1つ目の「オンラインで取得する方法」ですが、これはe-Taxソフト(Web版)を利用した手続き方法です。
専用ページにて必要事項を入力して、それを送信するだけで納税証明書を受け取ることができます。なお、受取方法には「窓口」、「郵送」、「電子ファイル」の3つから選べ、「窓口」であれば電子証明書とICカードリーダが不要です。
続いて2つ目の「郵送で取得する方法」ですが、これは納税証明書交付請求書を郵送し、税務署から返送してもらう方法です。
郵送で請求する場合は請求書に加えて、「手数料(1枚400円~)相当の収入印紙」、「返信用封筒(要切手)」、「個人番号確認書類・本人確認書類の写し」も同封する必要があります。
そして3つ目の「窓口で取得する方法」ですが、これは税務署の窓口にて請求書を提出する方法です。
窓口の場合は請求書のほかに、手数料と個人番号確認書類・本人確認書類が必要になります。なお、窓口での受付時間は平日8時半から17時までです。
課税証明書の種類と取得方法
続いて、課税証明書が必要になった場合の取得方法について説明します。
なお、課税証明書の種類などは自治体によって異なる場合もあるので、詳しくはお住まいの市区町村のホームページなどを確認するとよいでしょう。
課税証明書の種類は自治体によって異なる
課税証明書とは主に住民税額といった課税額を証明する書類のことです。課税証明書には自治体によって異なり、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 課税証明書:所得金額や住民税額などを証明する書類
- 全項目証明:所得額や住民税額に加え、控除内訳、扶養家族も証明する書類
- 非課税証明書:住民税が課税されていないことを証明する書類
- 課標証明:住民税額と課税標準額を証明する書類
課税証明書の場合も書類によって証明内容が異なるので、利用目的などを確認した上で請求手続きを行うようにしましょう。
課税証明書を取得する3つの方法
課税証明書を取得するには、以下のように3つの方法があります。
- 窓口で住民税証明書交付申請書を提出して、その場で受け取る方法
- 郵送で住民税証明書交付申請書を郵送して、返送してもらう方法
- コンビニなどのマルチコピー機を使って申請手続きを行う方法
まず1つ目の「窓口で取得する方法」は、自治体の窓口にて住民税証明書交付申請書(自治体によって呼び名は異なります)を提出します。
交付を受ける際には、基本的に本人確認書類と発行手数料が必要になります。なお、申請できる場所は自治体によって異なるので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
続いて2つ目の「郵送で取得する方法」では、申請書を自治体が定める所定の住所に送付します。
同封するものには「手数料分の定額小為替」や「返信用封筒(要切手)」、「本人証明書類の写し」などが必要です。
最後の「マルチコピー機で取得する方法」とは、コンビニなどに置かれているマルチコピー機の「行政サービス」を利用する方法です。
こちらはマイナンバーカードや住基カードなどを持っている方が利用できます。なお、自治体によって対応している地域としていない地域があるので、事前に確認をしてから申請手続きを行いましょう。
おわりに
納税証明書と課税証明書はいずれも課税額や所得金額などを証明する書類です。ただし、その証明内容は異なるので、申請時には必要なものを取得するように注意することが大切だと言えます。なお、一般的には課税証明書が求められることが多いので、その際はお住まいの自治体に確認をしてから取得するようにしてください。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!
