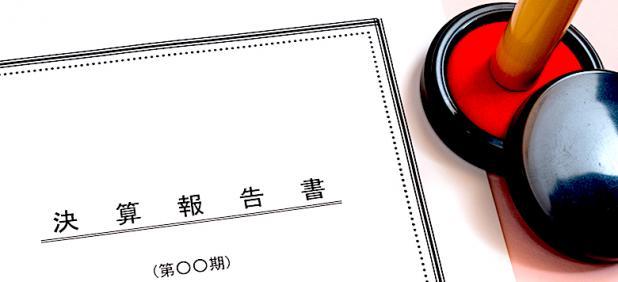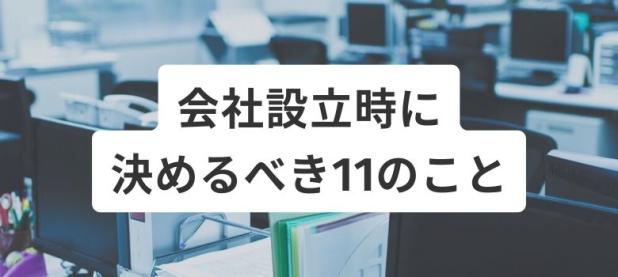売上を個人と法人に分けることはできますか?
農家をしていて、農協や市場に出荷しています
非営利型の一般社団法人だと農産物などを農協などに出荷すると非課税になると聞いたので法人設立を検討しています
法人から報酬を得ると年金事務所への加入必要となりますが、できれば加入したくありません
できるのであれば、売上を個人と法人で分けたいと考えています
そのようなことはできるのでしょうか?
または、何か良いアイディアはあるでしょうか?
畑とハウスは親戚のものを借りています
売上は個人名義の営農口座に振り込まれます
法人口座の開設は間に合わない可能性があるので、1年は個人名義の口座を使うつもりです
もしかしたら、質問自体が脱税に関する内容なのかもしれませんが、脱税の意図は全くありません。無知をご了承ください。
よろしくお願いします
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
社団法人の収益事業については、個別具体的に判断が必要となるため、売上を個人と法人とに分けることが可能かという点につき、一般的なご回答を以下の通りご提示させて頂きます。
1. 売上を個人と法人とに分けることは可能か
売上を分けることが可能かという点については、売上の発生時点より、個人としての売上か、法人としての売上かが明確に実体として区別されていれば問題ありませんが、実体としての帰属によらずに個人、法人とに売上を分散することは原則として認められないものと思われます。
納税義務の成立要件である、課税要件として、課税物件の帰属があります。これは、その売上が個人に帰属しているのか、法人に帰属しているかという問題です。この帰属に応じて、課税がなされるため、帰属が異なるのであれば、意思に関わらず、個人、法人とに課税は分離されることとなります。
2. 売上を個人と法人とに分けるには
課税物件の帰属で特に問題となるのは、取引や契約の名義・形式と実体・実質が異なる場合でありますが、この点に関し、法では実質所得者課税の原則を規定しており、銀行口座の名義等に関わらず、実体判断となります。そのため、外形的な状況だけでは判断は難しいですが、例えば売上の受注・発生時点から帰属を明確に区別し、実体としてその売上の帰属が異なるようにすることが必要と思われます。
3. 解決策
売上を分けるという点については前述の通りですが、法人からの報酬を受けたくないというのは社会保険加入が必要となる給与を受けたくないという意味でよろしいでしょうか?
その意味では、法人で売上を計上し、個人については法人の業務受託者として個人で売上を計上できる可能性はございます。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
お返事ありがとうございます
おっしゃる通り、社会保険加入をしたくないという意味です
業務受託者は、自分が代表理事を務める会社の仕事を自分で業務受託する、という意味でよろしいでしょうか?
加入せずにすむのであれば、シンプルそうですし、それをしたいと思います
先程、税務署で次のように言われました
「苗を育てるための経費を個人で支払っているので、収穫の売上は個人に入ることになる。今から会社を作っても経費を支払ってないから会社に売上は入れられない」
ですが、「絶対に個人に売上が入る」、というより、「その方がハッキリしてていいよね」といったニュアンスでした
これから会社を設立して会社に売上を入れて自分で業務受託する、といった流れがベストだと思うのですがどうでしょうか?
また、できない可能性もあるのでしょうか?
よろしくお願いします

村井隆紘
社会保険に加入したくないのが相談者様だけであるかや、相談者様の役職、その他の役員・従業員数、必要な報酬額、法人の売上等、ご状況により最適な対応や対応の可否が大きく異なります。
たとえば、相談者様だけが役員の1人会社の場合には、報酬をゼロとして業務受託を受けるとすることは一般的に難しくなります。報酬を自由に設定できるご状況であれば、社会保険料が発生しない水準で、適正な範囲内の報酬を設定することが可能です。トータルの税額を低くできれば良いということであれば、法人の売上等によっては社会保険料が発生したとしても税額を低くできる水準で報酬を設定できる可能性もございます。
法人の設立を専門家へ依頼されるご予定でしたら、当該専門家へ相談者様のご状況をあわせてご相談されれば最適な法人設立をご提案頂けるのではないかと思います。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
非営利型の一般社団法人の予定なので、社員は理事会3人+監事1人で、実際に働くのは私だけです。
この場合だと、報酬0⇛業務委託で社会保険加入しない、というのはムリということですね?
報酬は私が自由に設定できるのですが、報酬が1円でもあれば社会保険加入義務が生じるのではないでしょうか?社会保険料が発生しない水準の報酬であれば加入せずに済むのでしょうか?

村井隆紘
ご相談者様ご認識の通り、社会保険の加入義務は報酬額で決まる訳ではありません。健康保険法、厚生年金保険法では適用事業所に使用される者に加入義務があるとされております。
このため、理事や役員については使用されるものではないと解すと社会保険の加入義務はそもそもないものと考えられますが、ここについては「法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、被保険者の資格を取得すべき」との通達があることから、役員、理事等についても社会保険の加入義務があるものとして取り扱うことが多いです。
ただし、通達はあくまで通達であり、役員、理事等の社会保険加入義務は見解がわかれるところです。報酬や勤労状況等を総合的に勘案して適用事業所に使用される者であると判断されるのであれば、社会保険の加入義務があるものと取り扱うべきと思われます。報酬をゼロとし業務委託としたとしても、それが実質的には報酬であると判断される可能性もあるかと思います。
そのため、外形だけでの判断は難しく、万全を期するのであれば法人設立時に専門家へ相談をし、所轄の税務署に事前確認を取ることが望ましいと思われます。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
非常にわかりやすい丁寧な説明で本当に助かりました。
ありがとうございました。

村井隆紘
お役に立てて幸いでございます。
また何かご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
本投稿は、2016年10月19日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。