相続税の申告を期限内に終えるには?準備の手順と必要な書類
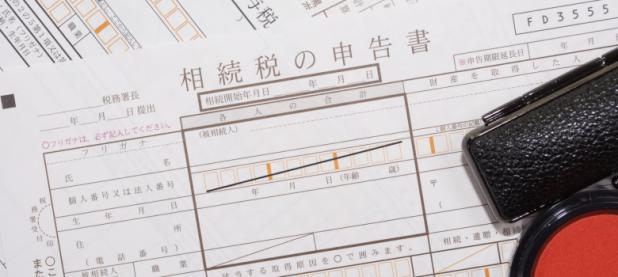
相続税の申告手続きがどのようになっているのかご存知でしょうか。相続が起こった時に、税金が発生した場合には所定の期間内に相続税を申告しなければいけません。しかしながら、相続税に関する書類を準備することは簡単なことではありません。
以下の記事をご覧頂き、少しでもご自身では難しいと考えられた方は、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
目次
相続税を申告する際に気をつけること
たいていの人は相続税を申告する経験は初めてではないでしょうか。相続が生じた場合には、お葬式の手続きに追われることもありますので、なかなかスケジュールを組んで相続手続きにまで手が回らないという方が正直なところでしょう。
提出期限を厳守する
相続税は、相続が生じた翌日から10か月以内に申告をする必要があります。
相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から計算して10か月以内に、管轄の税務署に対して行わなくてはなりません。

相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から計算して10か月以内に、管轄の税務署に対して行わなくてはなりません。相続税の申告期限は「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月目の日」となっています。
仮に、故人が1月1日に亡くなった場合は、その年の11月1日が申告期限日になります。期限日が土・日・祝日だった場合は、次の平日が期限日です。
「相続があったことを知った」というのは、簡単にいうと親族が亡くなったことを知った日のことです。
遠方に住んでいたり、疎遠となっていたりする場合には、親族が亡くなってかなりの期間がたってから相続の発生を知るということも決して珍しいことではありません。
その場合、お葬式の通知や相続財産の分割協議を行う旨の通知を受けた日の翌日から相続税の申告期限についての日数計算がスタートすることになります。
なお、税金の納付期限も申告期限と同じ日となります。
10か月というと、十分な期限があるのではないかと考えてしまいがちですが、実際にはそうではありません。遺産分割協議をするために、相続人に関する情報を集め、相続財産にはどのようなものがあるのか把握をしなければいけません。しっかりと段取りを組んで早め早めに行動するようにしましょう。
手続きの流れについて
それでは、相続税を申告するための具体的な手続きの流れについて押さえておきましょう。
- 書類作成に必要な資料を集める
- 資料を読み解き、申告書を記載していく
- 税務署に相続税を申告する
相続税を支払うべき場合とは?
相続が発生したとしても相続税を支払うべき人とそうでない人がいます。相続税には、基礎控除の制度が設けられており、この基礎控除以内の相続価額である場合には、そもそも税金を支払う必要がないことになっています。
基礎控除は、次の式で算出することが出来ます。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
一方で、相続税を抑えるための制度として、配偶者に対する特例制度もあるのですが、これを利用する場合には、たとえ納める税額がない場合にも申告をしなければいけませんので覚えておきましょう。
どこに申告すべき?
相続税申告の準備が整えば、申告書を亡くなった方の最後にお住いの住所地を管轄する税務署に申請をすることになっています。最寄りの税務署に申請すればよいという訳ではありませんのでご注意ください。また、きちんと税務申告を行わないと税務署より追徴を要求される場合がありますので注意をしてください。
場合によっては、税務調査の対象となることも
相続税申告で一番怖いのは、税務調査の対象となることです。実は、税務調査をされるとほぼ100%申告情報に漏れや不十分な点が指摘されることになります。例えば、相続税を抑えるために財産を隠していた場合などが典型例です。
税務調査の対象となりやすい人には、以下のような特徴があります。
- 所有する不動産の評価額が5,000万円以上であること
- 相続財産を約3億円以上保有していること
- 所得税申告金額が2,000万円以上であること、かつ「財産及び債務の明細書」を提出していること
上記以外にも、申告書の記載に整合性がとれないことなど怪しまれる点が多い場合にも税務調査を受けやすい傾向にありますので注意をするようにしましょう。
万一、税務調査の確認が入った場合には、虚偽情報を伝えないようにしましょう。ご自宅にある価値の高い財産についてはすべてチェックがなされ、また財産を隠していることをにおわす情報について独自のノウハウをもとに調査されることになりますので素直にお話しするようにしましょう。
専門家に相談をして、相続税申告を行う
相続申告書の作成及び提出について、問題なく手続きを行うようにするためには、やはり素人の方ではなかなか難しいものがあります。そこで、相続税申告には、やはり専門家に相談をすることが一番であるように思います。
相続税を申告する際には、相続をする財産によって申告書の様式が変わります。申告書にはどのようなものがあるのか確認をしていきましょう。
申告書の種類
相続税の申告書は第1表から第15表まで全部で15の様式がありますが、実際に使用するのは一つ目の様式だけになり、その他は添付書類を提出すればよいことになっています。
申告書の記載方法
申告書を記載するためには、きちんと順番が決められています。具体的には、以下の順番で作成をしていくようにしてください。
- 第9表 (生命保険金などの明細書)
- 第10表 (退職手当金などの明細書)
- 第11表の付表 (小規模宅地等、特定山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書)
第11の2表 (相続時精算課税適用財産の明細書、相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書) - 第11表 (相続税が発生する財産の明細書)
- 第12表 (納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書)
- 第13表 (債務及び葬式費用の明細書)
- 第14表 (純資産価額に加算される暦年課税)
- 第15表 (相続財産の種類別価額表)
- 第4表 (相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書)
- 第5表 (配偶者の税額軽減額の計算書)
- 第6表 (未成年者控除額・障害者控除額の計算書)
- 第7表 (相次相続控除額の計算書)
- 第8表 (外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書)
- 第1表 (相続税の申告書)
- 第2表 (相続税の総額の計算書)
- 第3表 (財産を取得した人の中で農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書)
申告書は専門家に依頼する
申告書を配布の手引きの通りに作成をしていくと、恐らく時間をかければ完成して提出をすることが出来るでしょう。しかしながら、その申告書について、事後的に申告漏れが発生するリスクを考えると、相続税においては専門家に依頼をすることが無難なのではないでしょうか。例えば、税理士や弁護士であれば相続税の申告に対応してもらうこともできます。
実印は不要
相続税の申告をする際には、ご氏名の右隣に印鑑を押す必要があります。ところが、実印を使用するとなると少々抵抗があるという方も少なくはないでしょう。幸いなことに、相続税申告書に押印すべき印鑑は、認印でも良いとされています。
用意すべき添付書類とは?
相続税の申告書には、申告書記載内容を証するために添付書類を用意することが求められています。以下で、どのような添付書類を用意すればよいのかについて確認をしていきましょう。
財産を証明する書類
相続人が取得した以下のような情報を集める必要があります。
| 財産に関係する添付書類 | |
|---|---|
| 預貯金 | 預金証書、預貯金通帳、残高証明書 |
| 不動産 | 固定資産税の評価証明書、登記事項証明書 |
| 株式 | 株主名簿、銘柄一覧表など |
| その他 | その他の証明書など |
債務を表す書類
亡くなった方に債務あることを確認するために、以下のような書類を集める必要があります。
| 債務に関係する添付書類 | |
|---|---|
| 公租公課 | 課税通知書、納付書 |
| 借入金 | 借入金残高証明書、金銭消費貸借契約書 |
| 葬式費用 | 領収書、葬式費用出納帳 |
| 未払い金 | 領収書・請求書 |
法的地位を証するための書類
亡くなった方及び相続人の相続関係を証するための以下のような書類を集める必要があります。
- 相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票
- 亡くなった方の戸籍・除籍謄本・戸籍の附票
- 相続人全員の住民票
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の身分証明書(マイナンバーカードなど)
場合により必要となる書類
相続の状況によっては、以下のような書類が必要になることがあります。
- 遺産分割協議書(写し)
- 相続放棄申述の証明書
- 遺言書(写し)
- 被相続人の略歴
- 特別代理人の専任申立書
- 相続人全員の職業と電話番号
- 介護保険の被保険者証などの写し
- 障害者手帳(写し)
おわりに
相続税の申告をするには、上記のような様々な書類を集めていかなければいけませんし、申告書に記載する内容にミスがあれば税務署から税務調査の対象になることも考えられます。申告期限通りに、問題なく手続きを完了できるように、相続税の専門家に依頼をすることも検討をしましょう。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!
