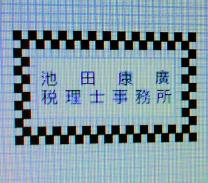相続税と分筆する時期について
父が亡くなり、変則的に2つに分筆された土地(300㎡)とその土地に跨って建つ家を相続します。他に財産はありません。
・相続人:母、長男、長女
・亡父/母と長女は同居。長男は別居(マンション保有)
相続について、現在の変則的に分けられた土地を合筆し、そして改めて均等に二つに分筆する必要があると考えています。
将来的には、二つに均等に分筆された土地を、それぞれ長男と長女名義に登記したいと考えています。
相続については、小規模宅地等の特例を活用(母、長女について)したいため、以下を予定しています。
① 土地は、母2/4,長女1/4、長男1/4を相続。現在の古い家は母が相続。
② その後、古い家を取り壊し、長女(母と同居)と長男の自宅(各自保有)をそれぞれ建設。
③ 将来、母の死後は、土地は各1/2で相続
(質問)
土地の分筆登記は、「①の前」に行うのが一番良いように思いますが、「①の後」、「②の後」、に行った場合で、相続税に違いはあるのでしょうか。
また、分筆の時期によっては、上記①~③の相続ができない場合もあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続税の申告期限は被相続人の死亡後、10ケ月以内なので、申告期限までに分筆して、それぞれの部分の所有者が分割協議により確定していれば各人の所有部分ごとに評価しますが、分筆しただけでは全体の評価額×持分で評価します。上記①~③の状況では分筆するとはおっしゃっていないので、相続時点では全体の評価額×お母さんの持分で評価し、⓶の場合、小規模宅地の対象面積は、ご兄弟の家屋の面積が同面積とした場合、300㎡×お母さんの持分1/2×土地に関する長女の居住割合1/2(残1/2は長男居住のため)=75㎡となります。
分筆の時期について、お母さんの死亡後、相続税の申告期限までにご兄弟2名で分割協議がまとまっていればそれぞれの部分に対する評価額によって評価します。よって、分筆の仕方によっては、それぞれの分割後の評価額に差異が生じる場合があります。(分筆前が角地で分筆後が角地と一路線に面した土地・分筆前が一路線に面した土地で分筆後が一路線に面した土地と無道路地)このように、評価額に差異が生じる場合は、差額について評価額が上昇した土地の取得者に贈与税が課税されます。前述のように分筆ののしかたによる贈与税の課税の発生する場合がありますが、時期により相続できないということはありません。
ありがとうございます。もう少し教えてください。
父の死後、以下のように土地を分筆し、以下のように相続することは可能ですか。
また、可能な場合、以下の課税総資産額の計算は正しいでしょうか。
相続資産は、土地のみ。亡父、母と長女は以前から同居。分筆後も評価額は変わらないもととします。
・土地評価額:1億5000万円(300㎡)
=土地A(7500万円、150㎡)+土地B(7500万円、150㎡)
<1次相続>
・母→土地Aと土地Bそれぞれの50%
・長女→土地Aの50%
・長男→土地Bの50%
(相続税計算)
① 資産価額:6000万円
・母:1500万円=(7500万円×0.5×特例0.2)×2(土地AとB)
・長女:750万円=(7500万円×0.5×特例0.2
・長男:3750万円=(7500万円×0.5)
② 基礎控除:4800万円=3000万円+(600万円×3)
③ 課税総資産額:1200万円=①-②
※その後、長女は土地Aへ、長男は土地Bへそれぞれ自己資金で家を新築。
長女は引き続き母と同居。
<2次相続>母が亡くなった後、以下の割合で相続。
・長女→土地Aの母の保有分
・長男→土地Bの母の保有分
(相続税計算)
① 資産総額:4500万円
・長女:土地A750万円=(7500万円×0.5×特例0.2)
・長男:土地B3750万円=(7500万年×0.5)
② 基礎控除:4200万円=3000万円+(600万円×2)
③課税総資産:300万円=①-②
第1次相続時土地A・Bが一体として利用(境界に塀・柵がない)している場合はご質問のとおりとなります。また、余談ですが、仮に長男がB土地に建築した家を他人に賃貸してから3年超経過した後に第2次相続が発生した場合、B土地は「貸付事業用宅地として50%の減額をすることができます。
なお、B土地に建築した家に長男が第2次相続の前から居住しても、他に居住用マンションを所有しているため、B土地の持分1/2については小規模宅地の課税の特例を適用することはできません。
ありがとうございます。
何度も申し訳ございませんが、頂いた以下のご説明について教えてください。
↓↓↓↓
/-----------------------------
なお、B土地に建築した家に長男が第2次相続の前から居住しても、他に居住用マンションを所有しているため、B土地の持分1/2については小規模宅地の課税の特例を適用することはできません。
--------------------------------------------------------/
<質問>
2次相続の前に、長男は土地Bへ家を新築し、そこに居住します(母は長女の家に同居)。
その際には、マンションは売却の予定です。
ご説明から推測すると、「マンションを保有していなければ」、「2次相続時」に長男も、「小規模宅地等の特例」を適用でき、相続税計算における土地Bの資産価額も、次のようになるとの理解でよいですか。
↓↓↓↓
・長男:土地B:750万円=(7500万年×0.5×特例0.2)
訂正します。土地Bのお母さんの持分1/2については特定居住用にはなりません。仮にお母さんの持分1/2についての地代を払えば貸付事業用宅地として50%となります。
それよりおすすめしたい方法があります。
①第1次相続時
土地Aを長女(持分3/4)長男(持分1/4)、土地Bをお母さん(持分3/4)長男(持分1/4)で相続する。
お母さん 土地B 7500万円×持分3/4×小規模宅地0.2=
1125万円
長男 土地A 7500万円×持分1/4=1875万円
土地B 7500万円×持分1/4=1875万円
長女 土地A 7500万円×持分3/4×0.2=1125万円
合計 6000万円
課税価格
6000万円-(基礎控除3000万円+600万円×3人)=
1200万円
お母さんは配偶者軽減により税額0円
⓶ その後
土地Aの長男の持分1/4と土地Bのお母さんの持分1/4を交換
この結果
土地A お母さん(持分1/4)長女(持分3/4)
土地B お母さん(持分2/4)長男(持分2/4)
③第2次相続時(これまでに長男はマンションを売却、土地Bに家屋建築の
上、長男居住となっているが、居住しなくても良い))
土地A 長女 7500万円×1/4×0.2=375万円
土地B 長男 7500万円×2/4=3750万円
合計 4125万円
基礎控除 3000万円+600万円×2人=4200万円
したがって、第2次相続では非課税となります。
本投稿は、2022年07月27日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。