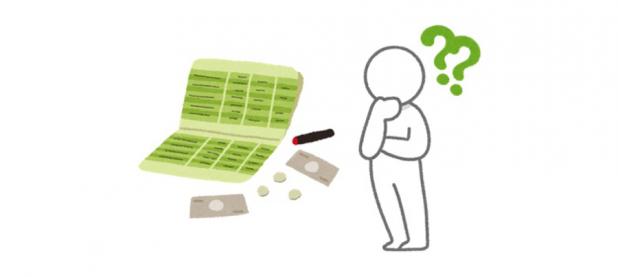贈与?借金? 夫婦間で借りたお金で株式と投資信託等
夫からお金を借りて投資等をする場合、貸した借りたという証拠の借用書があれば期日通りに返済すれば贈与とみなされる事はないと思われます。という回答を参考にさせていただきました。
利息ありの一括返済の借用書を作ってあり返済期間は5年です。
2019年分と2020年分の2通の借用書を作りました。
借りた額は
・2019年 10/18まで数回に分けて171万円(利息◯円×5年)
・2020年10/14まで数回に分けて680万円(利息◯円×4年)
合計額を2024年10/14に元金と利息分を一括返済する予定です。
質問がいくつかあり、どうぞご教示お願いいたします。
①利息1.6%にしましたが、妥当な利息でしょうか?
平均的な利息が知りたいので、離れ過ぎている場合、利息を修正しようと思います。
②借用書は、数回振り込みがあった都度で作った方が良かったでしょうか?
③2020年6月からネット証券で取り引きを始め6月から12月まで数回の取引を行いましたが、夫から借りた額を超える額ではありません。
問題はありますでしょうか?
④同じネット証券から生前贈与書類の書類を送付してもらい、2020年に買った株を2021年に成人の息子に110万円贈与して、生前贈与契約書も作ってありますが、問題はありますか?
⑤借金返済期間中の生前贈与は出来ませんか?
契約書を作成して生前贈与を現金で息子2人に移しています(補足ですが長男が障害者手帳3級を持っており今のところ一度休職はしましたが働けているので障害年金は貰っておりません)
⑥借金返済後から生前贈与を開始しないといけませんか?
⑦一括返済が完了したら、自分の口座名義として運用して行く事に問題はありますか?
返済期日が近いので、早めのご回答をいただけますと、大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
これらの質問は複雑な法律問題を含んでおり、個別の状況に応じた弁護士のアドバイスが必要です。一般的な情報としては以下の通りですが、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
①利息1.6%は、現在の低金利環境を考えると妥当な範囲内と思われます。国税庁が定める特例基準割合(令和5年:1.6%)と同等です。
②理想的には各取引ごとに借用書を作成することが望ましいですが、実務上は困難な場合もあります。重要なのは、取引の実態を正確に反映することです。
③借入金の使途に制限はありませんが、投資リスクと返済義務のバランスに注意が必要です。
④贈与税の基礎控除(年間110万円)内であれば、一般的に問題ありません。ただし、贈与の事実を明確にする書類の保管が重要です。
⑤法的には借金返済期間中でも贈与は可能です。ただし、返済能力に影響を与えない範囲で行うべきです。
⑥借金返済後でなければ贈与できないという法的制限はありませんが、返済能力を優先すべきです。
⑦一括返済完了後、自己名義での運用は一般的に問題ありません。ただし、取引の透明性を確保することが重要です。
石割先生、ご回答ありがとうございます。
返済能力に関しては、返済分のお金の準備はできていて銀行に移してあり、返済日に確実に振り込む予定です(結婚前20代から社債等に投資をしてきた外貨を円転したお金もあります)
①夫が雑所得の確定申告は面倒だと言っていて、今年と来年の2回に分けて返済する事に問題はありますか?
親族間でも返済期間が長くなると返済意志があるのか?という文説も読みますが、5〜6年、利息払い無しで返済日に一括払いで問題ないでしょうか?
②知り合いから紹介いただいた税理士さんと一度話しただけなのですが、金銭消費貸借契約書がいいとの事でしたが、利息を払っていない事は伝わっておらず(もう一度、聞き直すつもりです)返済期間が長く、利息を払っていない場合、
金銭消費貸借書を元に、債務承認弁済契約書を行政書士さんに依頼して、
返済日までに作成しておけば、いいのでしょうか?
②複雑な法律問題を含むとは、どんな問題が考えられるのか?を、ご教示いただければ助かります。
法律に違反する可能性があるのでしょうか?
この内容の相談が必要な場合、大体いくら位の費用がかかるのでしょうか?
③知り合いから、紹介して頂く事になるかもしれないですが、法律事務所にご相談すればいいのでしょうか?
※息子が障害者手帳3級で障害者年金ももらっていないので、将来、障害のある息子に障害者用の特定贈与信託に預ける事も一応考えたりしております。
お手数ですが、またご教示いただれば、大変助かります。
よろしくお願いします。

石割由紀人
借用書は貸借の都度作成するのが望ましいですが、後日まとめて作成することも可能です。返済方法の変更(分割返済への変更など)は、両者の合意があれば可能です。
実際に返済が行われるのであれば、法律に抵触する問題はないと考えられます。
弁護士に相談する場合、初回相談で1万円〜3万円程ではないかと思われます。
障害者用の特定贈与信託を考えることは、将来の息子様の生活を安心させるために有効な手段です。
以下のポイントを考慮することをお勧めします。
信託の目的と内容: 特定贈与信託は、障害者の生活や福祉のために資金を保護する目的で設定されます。息子さんの将来の生活費、医療費、ケア費用などを支えるために信託契約を詳細に設計しましょう。
信託の設計と受託者の選定: 信託契約を設定する際には、信託財産を管理する受託者(通常は信託銀行など)を慎重に選ぶ必要があります。また、信託の運用や引き出しの条件などを明確に定めることが重要です。
税務面の考慮: 特定贈与信託は、贈与税の非課税枠が適用されますが、条件や上限額などについて理解しておくことが大切です。信託契約の設計に際して、専門の弁護士と相談することをお勧めします。
将来の対応策: 信託契約は長期にわたるものであり、息子様の生活状況や法律の変化に柔軟に対応できるよう、定期的な見直しを行うことが重要です。
受給する障害者年金等との調整: 将来的に障害者年金を受給する可能性がある場合、その受給額や受給条件に信託の設計が影響しないように配慮する必要があります。
石割先生、ご回答いただき本当にありがとうございます。
特定贈与信託は、一度契約すると戻れないらしいので、息子の将来を見据え進めて行きたいと思います。
何度も申し訳ありません。
分割について、主人と話したところ、
2019年に私の母が他界し、2020年は障害のある息子が就職し引越しており、それを借りたお金から立て替えて払っていたので、2020年に主人から借りた額は450万円になりました。
主人は2020年は利息1.1.%でいいと言っておりますが、何か問題があるか?が知りたいとの事でした。
2019年は利息1.6%、2020年は利息1.1.%にする事に問題はありますでしょうか?
何度も本当に申し訳ありません、お手数おかけしますが、ご教示いただれば、大変助かります。
よろしくお願いいたします。
言葉が足りておらず、すみません。
※借りた額と投資の取引きの時期の実態に問題はないです。2020年より2021年から始めているものがほとんどです。
※将来的には、コツコツと貯めていき、自分の貯金も合わせて、相続時精算課税制度なども利用して行ければと考えております。
お手数おかけいたしますが、ご教示いただけますと、大変助かります。
よろしくお願いいたします。

石割由紀人
主人は2020年は利息1.1.%でいいと言っておりますが、何か問題があるか?が知りたいとの事でした。
2019年は利息1.6%、2020年は利息1.1.%にする事に問題はありますでしょうか?
↓
問題無いと思います。
重ねて何度もすみません。
2019年分を2025年に返済して、2020年分を2024年分に返済をする事に、問題はありますでしょうか?
(親族間においては1〜2%までの金利でも大丈夫と弁護士さんのサイトで読みました)
利息1%でも大丈夫という話もあり、利息が気になっております。

石割由紀人
2019年分を2025年に返済して、2020年分を2024年分に返済をする事に、問題はありますでしょうか?
対応する金利を支払えばいいと思います。
利息1%でも大丈夫と思われます。
最後まで何度もご教示いただきまして、心より感謝しております。
息子の将来にも希望を持って、私もコツコツと努力を続け、これからも頑張って行きたいと思います。
本当に、本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年08月18日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。