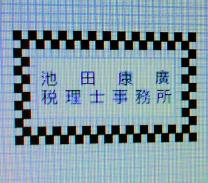一次相続、相続税申告を、しなくても良かったのか?
数年前に、父が亡くなったのですが、財産を全て母が相続して、私は遺産協議書で取り分を0にして、二次相続の時に全て私に相続するという取り決めをして、母が相続税申告をしました。税理士さんに勧められ、配偶者特別控除が使えて、相続税を全く払わなくて有利だと言われて、確かに相続税は払わなかったけれど、二次相続の時にドカンと来て、逆に不利なのでは?と今更ながら疑問です。しかも、配偶者特別控除が1億6千万なので、余裕で払わなくて良かったんですが、二次相続では母の預貯金もあるし、払わないといけないかもです。税率も高そうですし。そもそも、一次相続で払わなくても良かったのに、相続税申告をしなくても良かったんじゃないか?と疑問です。税理士が全く動かないひとで、戸籍謄本を取り寄せるのが、全て私で、色々複雑でめちゃめちゃ大変だったので、そもそも相続税申告の義務はなかったんでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
税理士が全く動かないひとで、戸籍謄本を取り寄せるのが、全て私で、色々複雑でめちゃめちゃ大変だったので
上記は一般的です。税理士がとるとその分を+で報酬を請求します。
、そもそも相続税申告の義務はなかったんでしょうか?
遺産の総額が、3,000万円+600万円×相続人の人数=
を超えれば、結果相続税を支払わないことになっても、申告義務はあります。
今回はそうであったと思われます。
それと二次相続した時に、どうなるかのことは別のことです。
そのことを税理士さんは、相続人に説明して、どう選択をするのかを、相続人に決定させる。
それは重要なことです。
今回はそれがなかったのでしょうか・・・。その説明がなかったのでしょうか・・・。
普通なた説明します。
なので、
確かに相続税は払わなかったけれど、二次相続の時にドカンと来て、逆に不利なのでは?と今更ながら疑問です。
という、ことになったのでしょう。
申訳ない次第です。
お父さんがお亡くなりになった第1次相続が平成26年12月31日以前であれば相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人数ですが、平成27年1月1日以降であれば、3,000万円+600万円×法定相続人数です。財産額が基礎控除を超えても、配偶者が相続する財産については、「配偶者軽減」の制度があり、配偶者の相続額が全財産の1/2または1億6,000万円までは相続税は課税されません。ただし、この「配偶者軽減」の制度を適用するためには、相続人全員による「遺産分割協議」の成立が条件となります。
第1次相続では、すべての財産をお母さんが相続されたとのことですので、
相続税は課税されなかったと推測されますが、この「配偶者軽減」を受けるためには申告書を提出することが要件となります。財産の総額が前述した基礎控除以内の額であれば申告は必要ありません。
配偶者軽減の趣旨は、相続後の配偶者の生活保障と近い将来に発生する相続による同じ財産に対する二重課税の防止という点です。
戸籍謄本などの必要書類は税理士との契約内容にもよりますが、相続人本人でないと交付されないものもあるため、原則的には納税者が準備するものと考えます。
お返事ありがとうございます。私が当時、めちゃめちゃ忙しかったので、報酬に追加されても戸籍の取り寄せをやってもらいたかったんですが、ダメとのことでした。その税理士からは二次相続の話はありませんでしたね。配偶者特別控除の話だけ、強調されました。私のような一般人はやはり、その道の税理士さんを信じてしまうわけで。それでなくても、大切な家族が亡くなって、しんどい時にする相続税申告はとても負担です。その税理士に不信感があったから、しなくていい申告をわざわざざさせられたかと思ったんですが、非課税枠は超えてたから、申告は義務でやって良かったんですね。二次相続では、相続人がわたし一人になるのですが、3600万を越えたら、かなりの税率で取られるんでしょうか?良い節税みたいのは、あるんでしょうか?

竹中公剛
二次相続では、相続人がわたし一人になるのですが、3600万を越えたら、かなりの税率で取られるんでしょうか?良い節税みたいのは、あるんでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
上記が税率表です。
生きている時間がわかれば、その時までに使い切ることですが・・・。
わからないので苦慮します。
自宅は、一緒に住んでいる子供に相続させる。など、=お母様と一緒に住んで、その土地建物を相続する。=これが一番です。
でも相続人から考えると、
不動産ばかり多くて、納税資金がないのは困ります。
最低でも、相続税を支払える、預貯金があることが重要と考えます。
竹中先生、重ね重ねのご回答、ありがとうございます。しかも、税率のリンクまで貼って頂き、大変参考になりました。けっこう高い税率ですね。
そうなんですよね。何歳まで生きるか分からないので、苦慮しますよね。
母はかなり高齢でして、病気も色々あり、これからどれだけ医療費とか介護費がかかるのか、そこまでかからない前に亡くなるかよめなくて。現在は、別居で介護してるのですが、亡くなったら実家に入る予定ですが、その前に同居した方が、相続税の節税になるのでしょうか?認知症の兆しもあり、どちらにしても大変なのですが。不動産も色々持ってますが、現金がないので、株券はかなり持ってますが、私としては生前整理で、現金化しておいてほしいのですが、固執して全くしてくれないので、死後の色々な整理が大変そうです。
池田先生、ご回答ありがとうございます。父は平成27年以降に亡くなったから、それ以前の相続税だと申告の義務もギリギリなかったのだと思いますが、新たな税法になり安くなり、申告の義務が発生したんですね。まさか、税理士の先生が、申告の義務ない人に申告勧めるわけはないですからね。
戸籍謄本は、必ずしも、委任してとって貰えるわけではないんですね。また、母亡き後、あの面倒臭い仕事がって今から頭痛いですが、仕方ないですよね。父が亡くなった時に、税理士も強く勧めるし、配偶者の特例と母のことばかり気にして、遺産は一円も受け取りませんでしたが、二次相続の税率の高さに打ちのめされ、やはり遺産は権利もあったわけだし、半分もらっておいた方が得策だったのかも、と後悔してます。今更ですが。

竹中公剛
なくなったら入る予定でしたら、今から住民票を移して、同居したほうが良いですね。
株券は現金とみてよいです。相続人が決まれば、相続人に移転してくれます。
相続人関係図作成については、連携している司法書士に依頼します。相続人の依頼を受けてからですが。この関係図を法務局で、作成するとあとは楽になります。思えていてください。
作成料は、せいぜい1万から2万円だと思います。でも、依頼する前に聞いてください。高いといけませんので。戸籍謄本の手数料などは別ですが。
現在、相続人はあなた1人とのことですが、もし、あなたにお子さんがいれば、お母さんと養子縁組をして法定相続人数を1人までなら増やすことが可能です。その結果、基礎控除額が600万円増加し、課税財産額が減少します。
ただし、孫養子となった相続人が相続財産を取得した場合、その孫養子となった相続人が納付すべき税額は算出税額の2割加算となります。
竹中先生、お返事ありがとうございます。亡くなってから入るよりは、その前に同居した方が、実家の不動産が丸々、課税対象から外れるのでしょうか?うちの母親は性格的に非常に難があるので、同居も辛いものがありますが。。
相続人の関係図は、今の所、法定相続人は私一人だけで、すごく単純な感じになると思うのですが、必要でしょうか?
池田先生、お返事ありがとうございます。私には子供が一人いますので、母親の孫養子にしたら、600万が基礎控除に加算されるのですね。まだ未成年なのですが、親権とかも移ってしまうのでしょうか?また、亡くなって相続した後は、戸籍を戻せますか?モラハラっぽくて、子供もあまり、祖母を好いてはいないので、拒否されそうな気もしますが。
養子となっても、特別養子とは異なり、あなたの実子としての親族関係が途切れる訳ではありません。したがって、お母さんがお亡くなりになった後も養子縁組前と相続以外の法律関係に変更はないと思います。
この方法はあくまで相続税節税のみの観点から申し上げた方法ですので、他の法律関係については、法務局や司法書士・弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、現在お母さんが居住されている家屋の敷地がお母さん名義で、あなたと同居されているのであれば、宅地の課税価格が330㎡までの部分について80%減額される特例があります。
池田先生、ご回答ありがとうございます。返信がめちゃめちゃ遅れてしまいまして、すみませんでした。相続税の為に、娘を母親の養子にしても私との親子関係は変わらないのですね。実家についても、私が同居していたら減額されたりとか、あるのですね。
池田先生、色々教えて頂きありがとうございました。
竹中先生も、色々教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年08月12日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。