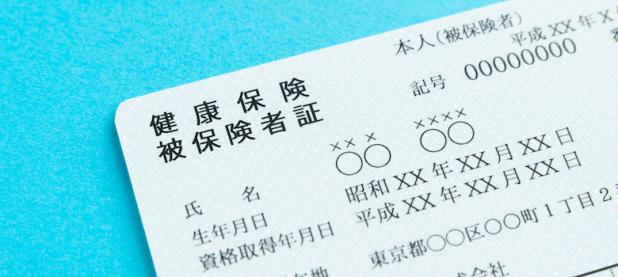インタビューした場合の勘定科目、源泉徴収
今後起ち上げたい仕事の情報収集として、知人の体験をインタビューした場合ですが、外注工賃で良いのでしょうか?
支払者、個人事業主 白色申告 源泉徴収義務のない個人。
受取者、会社員と源泉徴収義務のない個人。
1回一万円を数回実施、払う契約。
または、原稿料に該当した場合、
源泉徴収は必要でしょうか?!
税理士の回答

ご質問の状況について、以下のように解説いたします。
外注費としての取り扱い
知人の体験をインタビューする場合、これは事業の準備段階での情報収集活動と見なすことができます。したがって、支払う金額は外注費として処理することが適切です。
源泉徴収の必要性
支払者が源泉徴収義務のない個人事業主(白色申告)であるため、原則として源泉徴収を行う必要はありません。
原稿料としての取り扱い
インタビューの内容を文章化し、原稿として受け取る場合は、原稿料として扱う可能性があります。この場合でも、支払者が源泉徴収義務のない個人であるため、源泉徴収は不要です。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
迅速な御解答、ありがとうございます!
少し疑問ありまして宜しければご教授下さい。
1、請負契約ですが、
他人が代替出来ないその個人の体験のインタビューですと、給与と判断されてしまう可能性はないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
外注費と給与の判断基準
国税庁では、以下の5つを判断基準として公表
判断基準1.他人が代替して業務を遂行できるまたは、役務を提供できるかどうか
同じ業務を他の業者などが代わりにできるものであれば、「外注費」となります。その反面、その業務を他人が代わりにできないのであれば、報酬の支払者と受注者の間には雇用主と従業員と同じような結びつきの強さがあると考えられます。そのため、このような場合には「給与」と判断されます。
2、原稿料としての取り扱いの場合の必要書類
以下、教授頂いたのですが、
請負契約書や明細等は必須でしょうか?
(年間で10回実施した場合、支払が10万円)
インタビューの内容を文章化し、原稿として受け取る場合は、原稿料として扱う可能性があります。この場合でも、支払者が源泉徴収義務のない個人であるため、源泉徴収は不要です。
3、原稿料と判断された場合
一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下
年間で10回実施した場合、一人への支払が10万円ですと、
以下に該当になりますでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

ご質問ありがとうございます。それぞれの点について詳しく説明いたします。
1. 請負契約について
他人が代替できない個人の体験インタビューの場合、確かに給与と判断される可能性もあります。
消費税法基本通達1-1-1では、次の4つの基準を例示し、これらを総合的に勘案して外注費か給与かを判定すべし、としています。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
⇒個人の体験を話すという点では、他人の代替可能性は低いため、給与的な側面を持ちますが、個人の体験について多数の回答の中から具体的な体験のとして紹介したいためサンプル的に話してもらうという場合は外注費としての側面もあるかと言えます。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
⇒インタビューを受ける知人の方が自由に体験を語るケースにおいては、事業者の指揮監督を受ける、つまり雇用契約またはそれに準じる契約に基づく労働の対価という性質はないかと思いますので、外注費とみる方が自然かと思います。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
⇒インタビューは役務の提供そのものであり、完成品の引渡しという概念が適用しにくいです。インタビューを実施した時点で報酬を請求できると考えるのが自然かと思われます。この点では給与的な性質を持ちます。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
⇒インタビューに答えられる知人がインタビューという行為を行うに際し、特別な材料や用具が必要となり、それをご質問者さまが提供されている場合は給与的な側面があると言えます。
上記を総合的に勘案となりますが、ファクターとして大きいのは2点目かと思います。すなわち、本件ではインタビューを受ける知人の方との関係は労働契約またはそれに類する契約に該当するでしょうか?例えば、インタビューの方法や回答について指揮監督関係がある場合には雇用関係に近しい部分もあるかと思いますが、純粋に体験談を語ってもらうだけでは給与とはみなされない可能性の方が高いと判断されるかと思います。

2. 原稿料としての取り扱いと必要書類
原稿料として取り扱う場合、以下の書類を準備することをおすすめします:
・簡単な契約書:依頼内容、報酬、支払方法を明記。
・支払明細書:各支払いの詳細を記録。
・成果物(原稿)の保管:インタビュー内容を文章化したものを保管。
これらの書類は必須ではありませんが、取引の実態を証明する上で重要です。特に、年間で複数回の取引がある場合や外注費か給与かの判断が難しいと想定される場合は、適切な記録を残すことが望ましいです。
3. 原稿料と源泉徴収の判断
ご質問の状況(年間10回、合計10万円)は、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下の規定には該当しません。この規定は1回の支払いに対するものであり、年間の合計額ではありません。
重要なポイントは以下の通りです:
・支払者が源泉徴収義務のない個人である点。
・受取者が会社員または源泉徴収義務のない個人である点。
これらの条件下では、原則として源泉徴収は不要です。
場合によっては、相手方において確定申告が必要になるケースもありますので、以下のリンクに該当するような場合は事前にお伝えしておくことが望ましいと考えます。
本投稿は、2025年01月02日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。