株式(譲渡益と配当)の確定申告をする場合の住民税に関して、
株式(譲渡益と配当)の確定申告をする場合の住民税に関して、
・まず、確定申告をすれば住民税も還付されるのでしょうか?
・所得税の申告は「総合課税」あるいは「申告分離課税」で申告しても、配当+譲渡益がマイナスのため、保険料が上がることはないと思ってよいでしょうか?
・他に所得があり「総合課税」を選択した場合、、株式の損(配当+譲渡益)が他の所得と相殺されて、配当分の所得税に加え他の所得の所得税の一部も還付されますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
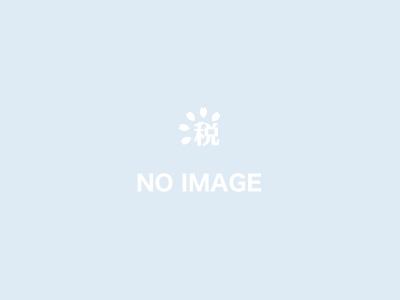
安島秀樹
上場株式の損は給与などと相殺することはできません。
配当と譲渡損益は別の扱いです。

中島吉央
すみませんが、もう少しだけ詳しい質問者さんの情報が必要です。
1つ目として、質問者さんの株式取引の口座は特定口座(源泉あり)、特定口座(源泉なし)、一般口座のどれでしょうか?また、配当は、その口座に入っている方式でしょうか?
2つ目として、「保険料が上がる」とは、社会保険のことでしょうか?その場合、質問者さんは国民健康保険料を自分で払っているのでしょうか?それとも、会社で働いており給与から保険料を引かれているのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
言葉足らずで申し訳ございません。
・株式の口座は「複数」の特別口座(源泉徴収あり)です。それらの配当と譲渡損益の合算がマイナスで損となる予定です。
・配当は現時点では証券会社の口座に入っていますが、銀行口座に振り込まれる形に変更予定です。
・ご指摘の通り、保険料とは国民年保険と国民健康保険です。これらの保険料は自分で払っています。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

中島吉央
特定口座(源泉徴収あり)に上場株式等の配当等を受入れている場合、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却損と当該特定口座に受け入れている上場株式等の配当等は自動的に通算されます。よって、現時点では、特定口座(源泉徴収あり)に、上場株式等の配当等を受入れて売却損との通算の結果、マイナスであるとのことなので、徴収されている税金がないということであり、確定申告しても戻る税金はありません。また、そのマイナスを確定申告しても、給与所得、事業所得や不動産所得などと損益通算できません。
ただし、上場株式等の売却損は、確定申告義務はありませんが、確定申告することにより翌年以降3年間繰越すことができます。上場株式等の売却損を上場株式等の配当等と損益通算した場合は、損益通算後に残った売却損が繰越対象となり、繰越した売却損は、翌年以降3年間に生じる各年分の利益(上場株式等の売却益等、配当等)と通算できます。つまり、翌年以降のプラスで源泉徴収された分に関しましては、翌年以降、結果的に税金が戻るということになります。
なお、今後、特定口座(源泉徴収あり)に上場株式等の配当等を受入れているのを金融機関の預金口座で配当を受取る方法に変更した場合、その場合の配当については、源泉徴収されたままなので、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却損と確定申告することによって、配当で源泉徴収された分は戻ってくることになります。
上場株式等の配当は、配当控除を受ける場合は総合課税により確定申告し、上場株式等の売却損と損益通算する場合は申告分離課税により確定申告する必要があります。つまり、確定申告する場合には、総合課税か、申告分離課税か、いずれかを選択しなければなりません。質問者さんの場合は、株式等の売却損と損益通算する場合は申告分離課税を選択するということになります。
次に、国民健康保険料の算定方法は、市区町村ごとに定められており、各市区町村がそれぞれ算定します。算定方法としては「前年の所得金額等」、「固定資産税」、「被保険者の数」・「(地域の)世帯数」の4項目すべてを基に算定する方法や、いくつかの項目を基に算定する方法等がありますが、「前年の所得金額等」の項目はすべての市区町村が採用しています。つまり、申告してもマイナスであるならば、その部分については所得が増えるわけではないので、その部分に関して言えば、国民健康保険料は上がりません。
次に、介護保険に関しては、前述した株式売却損の繰越控除の適用を受けた場合は注意が必要です。話が長くなるので、下記にリンク(福岡市)をはっておきますが、税制と社会保障の制度はリンクしていません。なお、国民健康保険料、介護保険に関して具体的なことについては、お住まいの市区町村に直接聞かれることがよろしいと思います。
外部リンク先 福岡市
http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/qa/FAQ4178_2.html
中島吉央先生、
丁寧な説明をどうもありがとうございます。
背景として、高齢の親の株式を暦年贈与(当面は贈与税率15~20%程度で)を進めようと思っており、配当所得が増加する可能性があります。
Webを読んでいろいろと勉強しましたが、やはり素人には難しく感じます。下記に私の理解を書きました。お手数ですが、もうすこし追加で教えていただけますでしょうか?
また併せて、確定申告、贈与税申告を税理士にお願いした場合に必要となる費用を一般的な条件の概算で結構なので教えていただけますでしょうか?
====
贈与およびその後の相続の手続きを円滑に進めるため普段自分が利用している証券会社とは別に、親が利用している証券会社にも口座を作る予定で、両方とも、特定口座(源泉徴収あり、配当は銀行振り込み)とする予定です。
前提として、複数の特定口座の合計では、【配当所得+譲渡損 < O(マイナス)】とするつもりですが、単独の口座を見た場合には益がでる可能性があります。
(A)
そのため、特定口座(源泉徴収あり)でも、複数の口座での合算がされないため確定申告は必要である。と理解しておりますが、これは正しいでしょうか?
(配当が銀行振り込みの場合は単独の特定口座でも合算されないため申告が必要)
(B)
全体で損の場合、住民税も還付(翌年の住民税が安くなる?)される。申告方法は総合課税でも申告分離課税でも結果は同じ(株式の損とそれ以外の所得は相殺できない)。また、住民税も株式全体では損のため増えることはない。健康保険と国民年金も増えることはない(ただし、介護保険は損益の繰り越しができため要注意)との理解で正しいでしょうか?
(C)
もし全体で利益が出ていた(譲渡損が配当益よりも少ない)場合、配当金にかかった所得税の一部還付を受けるため確定申告をすると、それが所得増となるため住民税、健康保険と国民年金に影響が出る可能性がある。その場合には、住民税の申告不要制度を利用すれば配当益による影響をさけることができる。との理解で正しいでしょう?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

中島吉央
>確定申告、贈与税申告を税理士にお願いした場合に必要となる費用
所得税の申告、その後の住民税の申告不要制度の手続き、贈与税の申告となるので、安くても10万円から15万円はかかると思います。税理士に依頼する場合、基本、質問者さんのお近くの税理士に依頼されるのがよろしいと思いますが、証券税務は特殊で税理士の大多数はよくわかっていないのが実情ですので、その点、理解して、お近くの税理士から探してください。
>贈与およびその後の相続の手続きを円滑に進めるため普段自分が利用している証券会社とは別に、親が利用している証券会社にも口座を作る予定で、両方とも、特定口座(源泉徴収あり、配当は銀行振り込み)とする予定です。
まず、ここがひっかかったのですが、親御さんは特定口座を利用されていないのでしょうか?利用されていたなら、贈与者(親御さん)の特定口座から受贈者(質問者さん)の特定口座の移管となり、同一の金融機関であるか関係なしに、贈与者から受贈者に対して、同一銘柄の一部の贈与が行われる場合には、受贈者が受入れる特定口座に同一銘柄の株式を保有していなければ可能というのが原則だと思います(もっとも、金融機関によって取扱いが異なる場合があると思いますが)。質問者さんの現在の特定口座だけで株を保有・贈与を受け入れることは不可能なのでしょうか?
>前提として、複数の特定口座の合計では、【配当所得+譲渡損 < O(マイナス)】とするつもりですが、単独の口座を見た場合には益がでる可能性があります。
以下、そのことを全体で話をしたいと思います。
(A)
正確には、違います。特定口座(源泉徴収あり)なので、申告はしなくても良いです。ただし、A口座(プラス)とB口座(マイナス)の場合、A口座の源泉徴収された分の還付を受けたい場合は、確定申告は必要となります。配当も同様に、銀行振り込みされた配当の源泉徴収された分の還付を受けたい場合は、B口座(マイナス)とぶつける必要があるため確定申告する必要があるということになります。
(B)
>全体で損の場合、住民税も還付(翌年の住民税が安くなる?)される。
これは、A口座(プラス)とB口座(マイナス)の場合で、B口座のマイナスのほうが大きという場合でしょうか?その場合は、A口座で源泉徴収された所得税は還付となり、住民税は安くなります(めったにないでしょうが、引ききれない場合は還付となります)。
>申告方法は総合課税でも申告分離課税でも結果は同じ
この意味がわからないです。配当は総合課税がとれますが、上場株式等の配当は、配当控除を受ける場合は総合課税により確定申告し、上場株式等の売却損と損益通算する場合は申告分離課税により確定申告する必要があります。質問者さんの場合は、上場株式等の売却損とぶつけるので、申告分離課税となるのではないでしょうか?
(C)
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(特定口座源泉徴収あり分)について、所得税では申告をし、住民税では申告不要とするという異なる課税方式を選択できます。そのため、所得税の申告をした後、お住まいの自治体で住民税申告不要制度の手続きをすれば、その分の(安くなるであろう)住民税はソンをすることになりますが、国民健康保険料には影響を与えないことになります。
本投稿は、2019年07月21日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




















