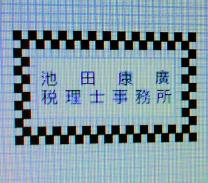相続の進め方について
片親の相続が発生しました。
概ね10か月の終了が目安との事ですが、過ぎてしまったらどうなりますか?
また2次相続を含めた1次相続は節税的にどう考えたらよいでしょうか?
何か目安はありますか?
税理士の回答
相続税の申告義務がある者が申告期限を過ぎて申告書を提出した場合、納付すべき税額の他に無申告加算税が賦課されます。また、申告期限から遅延した日数に応じた延滞税が納付すべき相続税額によっては賦課されることになります。
第1次相続の相続人に被相続人の配偶者がいる場合は、分割協議の成立を条件にその配偶者が取得した財産の価額が民法の規定による法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額に対する相続税の金額までは相続税はかかりません。
また、遺産のうち、被相続人の居住していた宅地・建物を配偶者または同居の相続人が取得した場合は330平方メートルまでの部分は80%課税価格が減額されます。
概ね10か月の終了が目安との事ですが、過ぎてしまったらどうなりますか?
相続税の申告納税期限は相続開始を知った日から10か月です。
それを超えると無申告加算税や延滞税が課されます。
遺産分割協議が完了できない場合でも未分割の申告をすべきです。
2次相続を含めた1次相続は節税的にどう考えたらよいでしょうか?
ご承知のとおり、2次相続では法定相続人が1名減るため、基礎控除額が減少します。
このため、たとえば、2次相続では相続税がかからないように(相続税が少なくなるように)、1次相続において次の世代であるお子様へ多く分割するなどの対策が必要です。
財産額にもよりますので、相続税申告を依頼する税理士にシミュレーションをしてもらい、最適な分割割合を提案してもらうことをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり失礼いたしました。
・期限については理解しました。
・2次相続について具体的に質問させてください。
父の保有する額を確認したところ、
1.路線価、固定資産税評価額から推定して土地建物で約1000万円(330㎡土地+築40年の家に母のみ居住、地続き別文筆150㎡の畑+自家駐車場)
2.預貯金・証券で4500万円
計5500万円、他に母が受取人の生命保険がありました。
母と同戸籍、別居の子1人(私)と別戸籍の子1人(将来母と同居予定)の3人が相続人となります。80才母の保有財産は現在約4000万円+生命保険分です。
今後母は年金でやっていけると判断しておりますが、お金の管理は子供達に任せたいと言っており、将来的に資金が必要になった時は母の分に加えて子供が準備する事になると思います。
以上の様な条件で、考えられる良い分割割合があるでしょうか。
アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
節税のためには2次相続における被相続人の遺産額が相続税の基礎控除額以内であればよいわけです。
2次相続における基礎控除額は4,200万円です。
お母様の生命保険分がいくらかが不明のため、お母様の保有財産が分かりません。
4,200万円を大きく超えないのであれば、1次相続では小規模宅地の特例が適用できる土地のみをお母様が相続し、その他はお子様が相続してはいかがですか。
そのうえで、お母様に長生きしていただき生活費などで預貯金を費消し、2次相続で同居する子が小規模宅地の特例を受ければ、1次相続、2次相続とも納税額は少額またはなくすことができると思われます。
詳細は是非、税理士にシミュレーションしてもらってください。
わかりやすい回答ありがとうございます、方向性が見えてきました。
父、母とも死亡保険に入っており、2次で1000万前後超えそうなので詳細のシュミレーションが必要なようです。
シュミレーションにあたり、何を用意したら良いのでしょうか。
不動産の固定資産税評価証明書はありますが、預貯金の銀行は記帳途中の通帳しかありません。
具体的にまだ依頼する税理士を決めておりませんがシュミレーションのみの依頼はできるのでしょうか。
何を用意したらよいかは、依頼する税理士によって異なりますので依頼してから確認してください。
少なくとも固定資産評価証明書のほか、公図測量図などの土地の形状が分かるもの、預貯金残高、生命保険契約状況が分かるものなどが必要です。
もちろん、とくに相続税分野に強い税理士はシミュレーション業務のみも承っています。
本投稿は、2022年10月03日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。