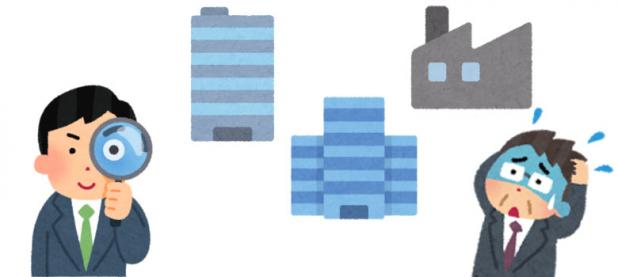自己の会社と親の会社が関連会社として認定される可能性について
こんにちは。
日本に在住のAが日本国内で会社を経営しています。
香港在住(日本住民票無し)のBは、香港で会社を経営しています。
ただし、お互いにお互いの会社の支配権はありません。株の持ち合いなどもなく、ABは単純な取引関係です。
Bは、海外からの荷物を取りまとめて、Aの会社に売掛で輸出し、Aは国内で卸売りをしております。
BとAは親子ではありますが、互いの法人としては、完全に独立して営業活動を行っております。
この場合、両名の会社が、「移転価格税制」に関わる「関連会社」として認定される可能性はありますでしょうか?
Bは、売掛でAに販売するため、AはBに対して多額の買掛金があったとしても、それは通常の取引で発生しています。
また、BがAに対して、売掛債権を放棄することもありません。BはAに対して、買掛残の債務があるため、BがAを支配し、海外に過剰な利益を落としているといった実態もありません。
しかし、税務署は「親子なのだから関連会社では?」と無茶な論理を振りかざします。
これで関連会社といわれるのでしょうか?
ご教授いただければ、幸いです。
税理士の回答

この場合、両名の会社が、「移転価格税制」に関わる「関連会社」として認定される可能性はありますでしょうか?
可能性はあるでしょう。
理由は、取引の実態が、その他の取引会社間とは、値段の設定があいまいであるなど。
下記関連会社の定義ですが、親子の場合には、下記に当てはまるのでは・・・。
税務署の言い分にも、正当性があるようにも思います。
契約書や、値段の設定などについて、他の会社と同じかどうかを自分なりに吟味ください。
関連会社は会社法で定められた会社計算規則で次のように定義されます。 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等 (子会社を除く。 )をいう。 法律の独特の言い回しで分かりにくいですが、要は「ある会社に対して影響力を与えることができる」会社を関連会社と呼ぶ、と定義しています。 一方、会計上は関連会社を以下のように定義しています。 「会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。 」 (財務諸表規則第8条第5項)
回答ありがとうございます。
上記は、日本の会社が海外の会社を自在にコントロールできる立場であることが前提だと思います。
本件の場合、
取引の実態が、その他の取引会社間とは、値段の設定があいまいである>>該当しません。
1.)きちんと、B社のインデントも、A社の仕入れ価格も適正です。税務署は不当に高い価格で買っていると疑っているようですが、そんなことをすれば、国内での売り先がなくなります。
2.)「ある会社に対して影響力を与えることができる」
日本のA社は、海外の経営に対して、何ら影響力がありません。
Bの会社に利益を移転させること自体が、そもそもできません。
3.)「会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。 」
日本のA社は、B社に対して、資金を出したり、人や技術を派遣している事実もありません。
A社はBに対して、買掛が多い、とか、BとAの会社の経営者が親戚あたる
ということのみで、AがBに利益移転をしていると考えているようですが、それは全くの誤認であり、根本的にBとAの間に取引以外の関係はありません。
B社はA社に販売する際に、特に法外な利益を取っていることもありません。
つまり、通常の海外取引の範疇でしかないのに、今回のものいいは、到底承服しがたいと考えております。

つまり、通常の海外取引の範疇でしかないのに、今回のものいいは、到底承服しがたいと考えております。
承服できないのなら最後まで、闘えばよいだけです。
でも、移転税制は、(あまり理屈は通りません)どの会社との取引についても、格差を(原価の差)をしてはいけないので、格差があれば、認められないでしょう。
頑張ってください。
本投稿は、2022年03月09日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。