要件定義費用も資産計上している場合のソフトウェアの取得価額と稼働時期
現在、要件定義費用100万円をソフトウェア仮勘定を使って、資産計上しています。
弊社では要件定義費用も会計上と税務上ともに資産計上しています。
今後システム開発費用が200万円かかります。
ソフトウェアの取得価額及び償却開始タイミングはシステム開発及び検収完了時点で
300万円(要件定義費用100万円+システム開発費用200万円)で計上してよろしいでしょうか?また、要件定義費用分の100万円のみを要件定義終了時点で償却開始する必要があるでしょうか?ご教示お願い致します。
税理士の回答
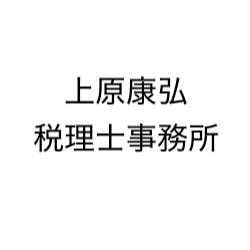
企業会計基準上ソフトウェアは次の3つに区分されます。
➀受注制作のソフトウェア
➁市場販売目的のソフトウェア
➂自社利用のソフトウェア
ご質問のソフトウェアが会計上どの分類かわかりませんが、仮に➂である場合は会計上は下記のようになると思います。
会計上自社利用のソフトウェアの資産計上のタイミングは「将来の収益獲得又は費用の削減が確実である」と認められることが要件となります。将来の収益又は費用が削減確実ということを立証できる証憑としては社内稟議書等が挙げられます。資産計上が終了時点は作業完了報告書や最終テスト報告書等により制作作業が完了したタイミングです。制作作業完了以降償却が始まります。従って、将来の収益獲得又は費用削減が確実であるならば、当該ソフトウェアが完了するまでは制作途中のソフトウェアの製作費として仮勘定で計上し、作業が全て完了したタイミングで下記のような仕訳を計上し、償却が始まると思います。
無形固定資産××/ソフトウェア仮勘定××
要件定義と開発費用を含めた300百万は開発が全て完了するまでは仮勘定に計上して、開発完了後上記のように本勘定に振替て償却が開始されます。
一方税務上は会計のように将来の収益獲得又は費用削減の効用で判断はせず、その取得に要した費用かどうかで資産計上するか否かを判断します。
従って原則そのソフトウェアに制作に要した費用は一旦資産計上し、開発完了後5年で償却がされると思います。ご質問のケースですと、要件定義100万とシステム開発費用200百万は一旦仮勘定として計上し、開発完了後300万を5年にわたり償却することになると思います。
※要件定義の段階で将来の収益獲得又は費用の削減が確実でなければ会計上は全額費用処理、税務上は資産計上することになり、会計上と税務上で処理方法がことなる結果になると思います。税務申告上調整が必要になります。
本投稿は、2019年02月27日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
























