古民家を購入し、改修して事業を始めた場合の資産計上について
個人事業主です。
事業を行うため、築60年の古民家を200万円で購入しました。
以下のリフォームを行いました。
建物に該当するものとして、内装工事150万円
建物附属設備に該当するものとして、電気工事・水道工事300万円
その際の減価償却についてどのようにすればよいのでしょうか?
調べたところ以下の2つが方法があるように思うのですが、正しいのでしょうか?
①中古資産の資本的支出を行った場合として
国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5404_qa.htm)を参考にして
取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合
その中古資産の取得額(資本的支出の価格を含む)÷{(その中古資産の取得額(資本的支出の額を含まない)/(その中古資産につき簡便法により算出した耐用年数)+(その中古資産の資本的支出の額)/その中古資産に係る法定耐用年数)}
ということで、本件であれば、
650÷{200/4(※1)+350/22(※1)}=9.8年 = 9年(切り捨て)
※1中古資産…木造事業用の法定耐用年数は22年であるため、22年×20%=4年(切り捨て)
このような方法でよいのでしょうか?また、これは、資本的支出ということで、建物工事と建物付属設備を一緒に計算してもよいのでしょうか?
②建物は建物だけで資産計上し、それぞれの工事で減価償却する。
また、別のWEBサイトなどを見ていると。
建物だけを資産計上し、それぞれの建物工事と建物附属設備のそれぞれの法定耐用年数で減価償却をするという方法もありました。
どちらの方法でもよいのでしょうか?
税理士の回答
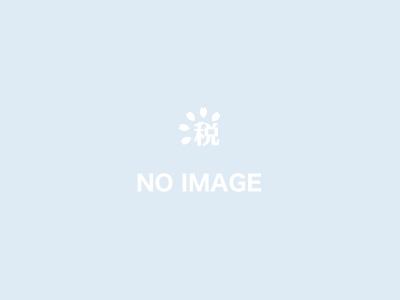
安島秀樹
どの方法でもよいと思います。それぞれ合理性があります。
ありがとうございます。
経理の世界では、どちらかが正解というような決まりはないのでしょうか?
答えは一つではないということでしょうか?
また、どちらにした方がよいなど、それぞれのメリット・デメリットなどがありましたら、教えていただけたら幸いです。
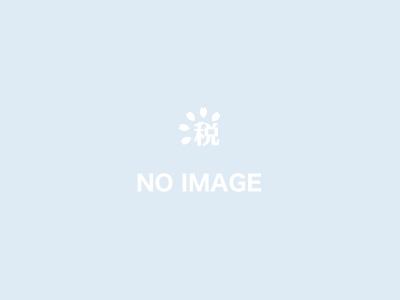
安島秀樹
わたしだったらこれ というのがそれぞれの税理士さんにあるのだと思います。それでいろいろな説があるのではないでしょうか。お客さんの立場からすると早めに償却できる方法がいいみたいです。
本投稿は、2020年01月29日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
























