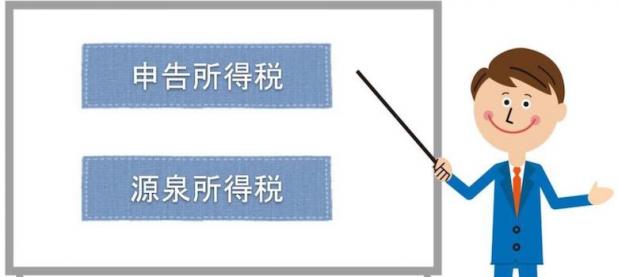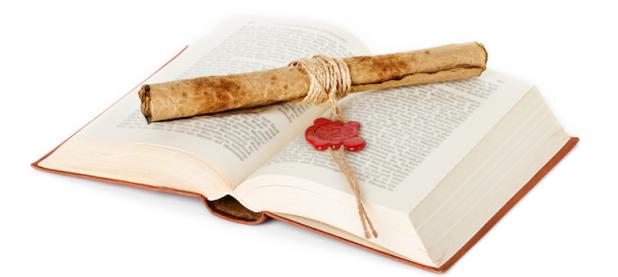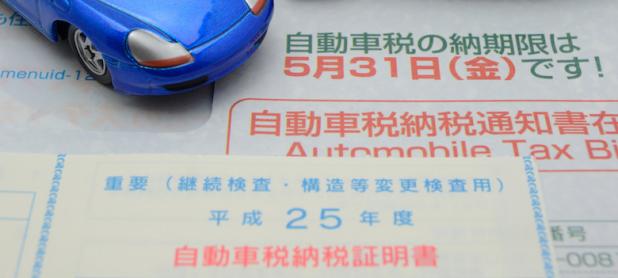無料でゲームをしたときの課税について
友人に無償でご飯を奢ってもらった場合経済的利益(贈与税)となりますが、友人の家で無償で本を読ませてもらったりゲームをさせてもらった場合経済的利益を得たことにならないのはどうしてなのでしょうか?
税理士の回答

小川真文
贈与税についての課税対象の範囲で考察しますと、定義上の贈与財産は贈与によって取得した財産で、金銭で換算できる経済的価値のあるものとなりますので、「無償でご飯を奢ってもらった場合」には外食時の店舗が提供する食事の金銭的価値が確認できることから経済的利益(贈与税)と判断できますが、「無償で本を読ませてもらったり」「ゲームをさせてもらった」場合には、一般的なサービスの対価の評価が著しく困難ですので「金銭で換算できる経済的価値のあるもの」とはなりえないと考えます。
ただ社会通念上は「友人に無償でご飯を奢ってもらった場合」でも、その状況や性質、金額の多寡からみて課税の対象とはならないものと思われます。
ありがとうございます。
定価が5000円のゲームだったら5000円と評価できそうに思えるのですが違うのでしょうか?
例えば歌手の友人に無料で歌を聞かせてもらったり
マッサージ師の友人に無料でマッサージをしてもらうなど役務を提供してもらった場合もやはり金銭では換算できないと考えるのでしょうか?

小川真文
「定価が5000円のゲームだったら」あくまでも購入価額が5000円であって、当該ゲームの使用貸借による対価が「5000円と評価できそう」とは異なるものと考えます。
「歌手の友人に無料で歌を聞かせてもらったり」、「マッサージ師の友人に無料でマッサージをしてもらう」場合には、無関係の第三者に提供するサービスの対価に相当するもので金銭的評価は可能ですが、あくまでも個人的な家族や友人知人等の特別な関係下での役務提供については、強いて課税しなくても弊害はないものと考えます。
再度のご回答いただきありがとうございます。
つまりこれらの経済的利益については贈与税や所得(一時所得)の範囲に勘定しないで良いということなのでしょうか?
税金は難しいですね....
例えばテレビ番組の出演者が番組内で無料(テレビ局の経費)で食事や宿泊などのサービスを受けることができますが、そういった経済的利益は課税されているのでしょうか?

小川真文
テレビ番組の出演者が番組内で無料(テレビ局の経費、もしくは取材先の店舗の無償提供等)で食事や宿泊などのサービスを受けることは、社会一般的に行われていると感じますが、この場合はあくまでも企画番組作成のための体験取材が目的であり、それに付随する飲食等のサービスについては利益の供与ではなく制作上必要な行為という意味が強いので、税務上は経済的利益として給与課税等は行われません。
経験値では旅行雑誌編集社において多額の取材費が必要でしたが、当該飲食宿泊入浴観光等のサービスを受益した記者については(本人的にどれだけ恵まれた環境であっても)課税することはありません。
ありがとうございます。
どうしても気になっていたのですが先生のお応えで納得できました。
日常生活で知らないうちに経済的利益を得ていないかビクビクしていたのですが、どうやら金銭で評価できるような経済的利益は少なく課税される状況は限定的の様です。
また気になることがあったらお尋ねしてもよろしいでしょうか?
すみません
貧困層の方々対象の食料配布って税金的には一時所得になるんでしょうか?
すみませんこんなことばかり気になって....

小川真文
税法上の明文の規定はないかと思いますが、社会通念上は担税力のない方々へ食料等の現物提供や金銭の寄付等の支援による一定の利得があったとしても課税を強いるような取扱いはしないものと考えます。
「貧困層の方々」に限らず、今般の能登半島地震で被災された方達が支援物資や義援金等を受領する場合も課税の対象とはなりませんので、寄付提供される人も感謝して頂く人も安心してください(当事務所でも少ないながら寄付させて頂きました)。
国税庁ホームページより引用
災害により受領する災害義援金等
災害により受領する災害義援金等のうち次のものについては、所得税及び復興特別所得税の課税の対象とはなりません。
・被災者生活再建支援法による被災者生活再建築支援金など、支給する法令の規定上非課税とされているもの。
・心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける義援金や見舞金で、その受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるもの。
そうなのですね!
支援物資や寄付金が課税対象になるのではと不安だったのですが安心いたしました。
お忙しい中丁寧に分かりやすくご回答いただきありがとうございました。
また何かあれば是非よろしくお願いします。
すみません何度も...
「強いて課税することはない」というのは法令に何か具体的に根拠があるんでしょうか?
それとも実務上課税されないだけで厳密には申告義務はあるということなのでしょうか?

小川真文
この場合は「実務上課税されないだけで厳密には申告義務はある」とお考え下さい。課税庁においては「申告義務はある」場合でも、税額の発生が見込めないものや少額で徴税するのはあたらないもの、技術的(課税標準の決定とその税額の計算等)に困難なもの、及び課税対象者が膨大であり費用対効果のうえで合理的でないものについては「強いて課税することはない」ものと考えます。
これは政策上で特に弊害がないうえ、強いて課税した場合には世論の批判等の問題が生じる虞が高いと想定されますので、「強いて課税」しないで「指導に留める」等のニュアンスで行き過ぎた免税行為を抑制するなどの方策を摂っているものと思います。
再度のご回答いただきありがとうございます。
「実務上課税されないだけで申告義務はある」
税金は難しいですね.....
納税者としてはどう対応すれば良いのでしょうか?
自分の得た収入や贈与の金額をカウントするときに実務上課税されない経済的利益をカウントの対象から外すのはやっぱり駄目なんでしょうか?
実務上課税されないし他の人が申告せずにいるなら真面目に気にしている自分が馬鹿を見るみたいで....
でも毎日こんなことばかり気にしていたら生活に支障が出ますし...
少額でも積み重なっていったら意図的でなくても脱税してしまうのではないかと不安です。
例えば贈与税の場合だったら109万5000円までカウントがたまっているときに、強いて課税されない経済的利益5000円を申告せずにいたら脱税になるんじゃないかと不安です。.
..

小川真文
繊細かつ真面目な相談者様とお見受けします。私見を申し上げればそんなに(生活に支障がでるほど)気にしなくても大丈夫とお考え下さい。
例えば課税される一時所得には、過去のマイナポイントの付与やGOTOトラベル、ふるさと納税の返戻など広く一般的に普及しているものが数多くありますが、税金の有無について意識される方はごく少数です。ポイントサイトで付与されたポイントも「一時所得」とみなされますが、確定申告される方は余程の高額でない限りはお見受けしません。
また社会通念上(世間一般の常識のレベルで)家族や友人知人の間での奢り奢られやプレゼントの授受等で、贈与だから税金を納税しなければと考える方はまずいません(そこまですると交際上では窮屈な人と思われてしまいます)。
税金はもちろん適正かつ公平に課税されるものが大原則ですが、貴方様の場合は少し楽天的に構えて頂いてもよろしいかと存じます。
返信ありがとうございます....!
励ましのお言葉をいただき大変嬉しいです
そうなんですよね....
楽観的に構えたいところなんですが
やっぱり全部の経済的利益を1円漏らさずカウントしなきゃ駄目だという強迫的な観念が強くて...
その理由としてカウントしないでおくと、
さっき挙げた109万9000円みたいな控除ギリギリのときに申告漏れが発生して意図せず脱税になるのではないかという不安があって
他の質問で110万をちょっと超えたぐらいでは追及されることは少ないという回答もあったので、
カウントしてなくてもお尋ねが来てなかったらセーフぐらいの認識では駄目でしょうか...?
もちろんお尋ねが来たら誠実に応えます!
あとやっぱり実務上課税されなくても申告の義務があるということで
申告しなかったら悪いことをしているように感じてしまって、でも申告しても周りはしてないのに自分だけ馬鹿を見てるみたいでむなしくなってと
どうしたら良いのでしょう。

小川真文
憲法84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」は租税を課し、又は変更する際のルールを規定しています。「租税」とは、国または地方公共団体が、一方的強制的に賦課徴収する金銭給付のことです。
このように、租税に関する事を規定・変更するには、必ず国会の議決によらなければならないとする原則のことを「租税法律主義」といいます。租税法律主義の具体的内容として、課税要件法定主義、課税要件明確主義、租税行政の合法性の原則といったものがあります。
「課税要件法定主義」とは、課税要件と租税の賦課・徴収の手続きは、法律によって規定されなければならないとする原則です。刑法の罪刑法定主義のように考えていただければよいのですが、「法律なければ税金なし」という原則とイメージしていただければと思います。
「課税要件明確主義」とは課税要件と租税の賦課・徴収の手続きは、誰でも理解できるように一義的で明確でなければならないという原則です。
「租税行政の合法性の原則」課税要件を満たしている限り、租税徴収を行う税務局が租税を減免したり、租税を徴収しないというような恣意を封じ、法律で定められたとおりの租税を徴収しなければならないとする原則です。
この租税法律主義によれば、税法で定められた課税要件に従い、たとえ発生する納税額が100円であっても納税することになりますが、現実にはそこまで極端には考えません(もちろん税務署では申告納税制度ですので受入れはしますが)。贈与額が110万1千円で100円税金が生じた場合には、加算税や延滞税といったペナルティも賦課されませんので「セーフぐらいの認識」で大丈夫です。 交通ルールでも原則では制限速度で1キロオーバーでも速度超過違反となりますが、警察がこの程度で違反切符を切ったりはしません。
税理士としては基本的に税法因りですのであまり見て見ぬふりをすることもできません(あくまでも法律に準ずる立場です)が、ご自身の周りで信頼できる方とご相談頂いて「これくらいなら全然大丈夫」と線引きのラインを話し合ってみることをお勧めします。
何度も回答いただき本当にありがとうございます。
一円でも見逃したら即脱税だとビクビクしていたのですが、道交法の速度オーバーの規定と一緒と考えると少し身体の緊張が解けてきた感じがします。
そうですよね
一円の申告漏れを全部脱税にしてたら国民の大半が脱税犯になっちゃいますよね...
脱税になるのはあまりにも金額が大きい場合やお尋ねを無視したり追徴金を払わないなど悪質度が高い場合だけと考えて良いのでしょうか?
私家族間での贈与税でも凄く悩んでいて
今まで家族間でもかかると知らなかったのでびっくりで
家族で何々を買うたびにこれって贈与税のカウント対象になるのかなあと凄く不安になって....
特に収入がある子どもや親に対して生活費を負担する場合非課税と認められない可能性があると聞いて
じゃあ一緒に住んでる親と社会人で収入のある子ども間で惣菜を買って食事をしたり、冷蔵庫の中の食品を取って食べるだけで贈与の金額のカウントが増える可能性があるのかと思うと全身緊張状態になってしまって....
ここで似たような質問を見かけたのですが
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/
「給与で得たお金は貯金に回し、生活費として生活費用の口座に振り込んでもらって生活費として利用している証拠があれば問題ないか」
という質問に「お金に色はついていないから贈与をしたと疑われてもしょうがない」という回答で
これは両親と同居してる社会人の子どもは生活にかかる費用全て贈与税として申告しないといけないということなのでしょうか....
でも実家暮らしの社会人で給与を全額貯金にしている人なんて一杯いますよね....
すみません本当に色々と聞いてしまって

小川真文
相談者様のご意見を伺う中で浮かんだ言葉があります。
課税する側の税務署は自分の大事なお金を持って行ってしまうイメージが強いと思います。確かに国の財政が緊迫している昨今の状況(能登半島地震への支援等)ではやむを得ないとは感じます。ですが、あまりに理不尽な課税徴税は極めて禁忌と思います。
「正直者には尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」
この言葉は、国税庁開庁式におけるGHQ歳入課長ハロルド・モス氏の挨拶文です。あまり有名な方ではないかもしれませんが、ハロルド・モス氏は、シャウプ博士招請を発案した人であり、戦後の混乱期の中で税制の基礎作りに携わっています。言葉の意味は、税務職員の仕事に対する姿勢を訓示されたものです。
「常に真摯に適正・公平な姿勢を貫け、そうすれば自ずと、誠実な納税者からは尊敬の目を向けられ、不誠実な納税者からは恐怖に駆られる存在となる。」
正義感を持って、適正・公平な執行をしなさいということであり、「良き納税者には菩薩のごとく、悪しき納税者には夜叉のごとく対応する。」というように、納税者により対応を変えるのではなく、正しい仕事をすれば、納税者の信頼が自ずと深まるという意味です。
(私も国税のある部署で「憲法を順守し」、「良心に従い」、「納税者に寄り添い耳を傾けること」との宣誓を行いました)
相談者様の遵法精神はとても尊敬しますが、あまりに度が過ぎると周りから窮屈に思われてしまいます。
悪意をもって税を免れる意図がない限り、普通の生活を送っていれば脱税で罰せられることはないと思います。
ネット上の言葉ではお力になれないかと思いますが、身勝手な利得の為に金銭(利益)を受領を隠そうとしない限り、「正直に」ごく普通の身近の生活の中で税金を課して徴することは道徳的に反するものと感じます。
相談者様にはあまり強迫的に囚われることなく、周りの方々に合わせて生活して頂ければと思います。
ありがとうございます。
どんなに理不尽に思えても申告納税制度である以上納税者側が1円も漏らさずに申告しなければいけないと考えていたのですが、
理不尽な課税は忌まなければならない、徴収する側の税務職員こそ公平で公正な姿勢を保たなければならないという先生とハロルドモス氏のお言葉にコペルニクス的転回を感じました。
ただ一つだけ喉に刺さった棘のように気になっていることがあります。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_130127/
このような質問があるのですが、家族での海外旅行費用が贈与税の課税対象かどうかが税理士さんの間でも分かれているのです 。
数千円ならともかく数十万円単位で贈与のカウント金額が変わりうる対象への判断が専門家でも分かれているとなると、自分で判断しなければいけなくて
非課税だと自分で判断して申告しなかった場合
意図的に所得隠しをやろうとは思ってやった訳ではないので、税務署の判断と違っていたとしても脱税にはなりませんよね...?
、
金額が大きいので最悪脱税になるなのではと考えてしまうのです。
こんなに大きな金額でも判断が分かれているならいつか重大な申告漏れをしてしまうのではないかと凄い怖くて
本投稿は、2023年12月26日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。