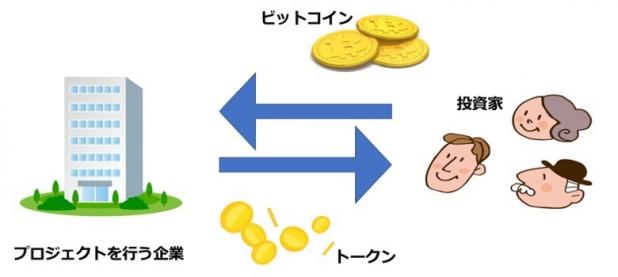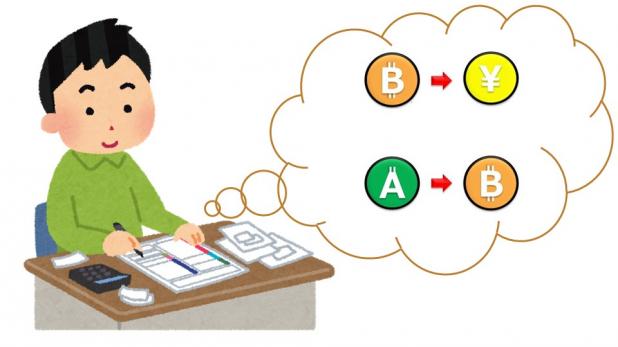親の扶養内で勤務している大学生。キャンペーンで得た暗号資産の売却益の計算方法や税金について。
親の扶養内及び住民税がかからない範囲でアルバイト(年間100万)をしています。
現在行われている暗号資産の取引所のキャンペーンで得た暗号資産の、損益の計算の仕方や取り扱いに関して相談したいです。
キャンペーンの内容としては、10万円以上の暗号資産の購入で、購入価格計算で5000円分の暗号資産が貰えます。10万円分の暗号資産を売却し、およそ3000円の損失になり、5000円分の暗号資産を売却で4000円を得ました。
この際の損益の計算の仕方などを教えていただきたいです。
1.キャンペーンとして暗号資産を受け取った地点での購入価格(5000円)が利益となる
2.キャンペーンで受け取った暗号資産を売却した価格(4000円)が利益となる。
3.受け取った地点での購入価格(5000円)が一旦利益となり、売却した価格(4000円)のため、差額で利益はマイナス1000円となる
4.それ以外
1-3について、キャンペーンの条件を達成するために暗号資産を売買する際に発生した損失3000円や入金手数料などを利益から引く。
これが正しいかどうかも教えていただきたいです。
このキャンペーンを繰り返すことで、キャンペーンの条件を達成するために暗号資産を売買することによる損失と、キャンペーンで得た暗号資産を売却することによって得る利益?が6万円程度となるため相談させていただきました。
現在アルバイトで95万円稼いでおります。
損益の計算方法や取り扱いについてと、
もしこのキャンペーンに参加することで100万円を超えない場合、100万円を超える場合、103万円を超える場合、の確定申告の必要性や方法に関しても教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
扶養親族の要件、住民税がかからない範囲の問題として、誤解している人が非常に多いので以下で整理しておきます。
扶養親族の要件・・・・・(合計)所得金額が48万円以下
住民税の課税最低限度・・・・・・(合計)所得金額が43万円以下
この要件で、
給与収入(アルバイト料)である給与所得には必要経費が最低55万円あるので、アルバイト料100万円のみであれば給与所得金額は45万円となり、扶養親族にはなれるが住民税はかかるということになります。
一方、暗号資産(仮想通貨)の運用利益は「雑所得」です。したがって、アルバイト料以外の所得がある場合には、収入金額ではなく、所得金額に置き換えて上記の要件を満たすかどうかを判断することになります。
よって、アルバイト料が95万円、暗号資産の運用益が6万円となると、所得金額は40万円(95万円-55万円)+6万円=46万円となります。
キャンペーンですが、10万円以上の暗号資産の購入が条件ですので、一種のキャッシュバックと考えられます。
この場合の処理として、10万5千円分の暗号資産を10万円で購入したと考え、暗号資産の購入代金は10万円として計上します。
よって、暗号資産の購入で10万円を支払い、暗号資産の売却で10万1千円(9万7千円+4千円)受け取ったことになりますので、1千円の運用益(雑所得)が発生することになります。これに手数料などの経費があれば差し引くことができます。
なお、アルバイト料以外の収入が20万円以下であれば確定申告は不要とすることができます。ただし、アルバイト料の金額によっては住民税の申告が必要な場合があります。
土師様
回答ありがとうございます。
誤解していたため、非常に助かりました。
大変恐縮ですが、再度お尋ねさせていただきたいです。
最後の文にある、
>アルバイト以外の収入が20万以下であれば確定申告は不要とすることができます。
ただし、アルバイト料の金額によっては住民税の申告が必要な場合があります。
雑所得が20万円以内なら確定申告が不要ということは
(95万(アルバイト料)-55万)が48万円以下であれば、それに加えて雑所得は20万以下までであれば扶養親族となれるのでしょうか。
住民税は、(95万(アルバイト料)-55万)+雑所得が43万円を超える場合に雑所得が20万円以内であっても申告が必要ということでしょうか。

土師弘之
20万円以下の「確定申告不要制度」は、所得税だけに適用される制度であり住民税にこの制度はありません。
また、この制度は給料以外の収入が20万円以下であっても原則として課税となるのであるが、課税事務の効率化の観点から申告をしなくても追及はしませんよという制度ですので、申告しなかったから非課税になるというものではありません。
したがって、扶養控除の判定には申告しなかった分の所得も加算する必要があります。
本投稿は、2020年09月08日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。