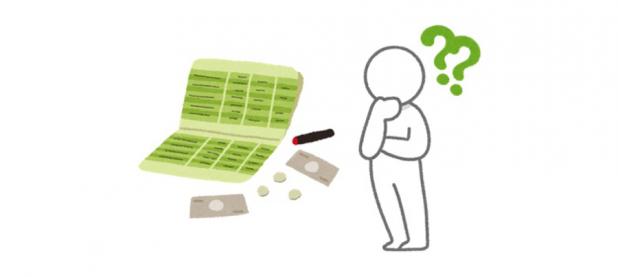法定相続分とは何ぞや? 小規模宅地等の特例との関係。
自分の財産を【法定相続分】で相続させたい「太郎さん」がいたとします。
太郎さんの法定相続人は妻・長男(別居)・長女(別居)の3人でした。
太郎さんの相続財産は土地1000万円(路線価)、家屋200万円、現金5000万円でした。
太郎さんは、
「遺産の2分の1を妻に、4分の1を長男に、4分の1を長女に相続する」という旨の包括遺贈の遺言を作成しました。
その後、太郎さんの相続が発生して、遺言書を確認した相続人たちは、
法定相続分を目安に財産(土地・家屋・現金)を分けることにしますが、
土地を妻が相続すると、小規模宅地の特例で土地の相続税評価額が80%OFFになることに気づきます。そして、相続人全員で「土地・家屋は妻が相続する」と合意しました。
そこで、相続財産を下記のように分けることにしました。(分割案①)
【分割案①】
妻:土地200万円、家屋200万円、現金2300万円
長男:現金1350万円
長女:現金1350万円
しかし、ここで、
「妻が土地を相続することで相続財産を圧縮できて、全体の相続税が少なくなったのは良いけど、それは税金の計算の問題であり、土地は本来は1000万円の価値があるのだから、家族の分前を考えるときは、本来の価値をベースに法定相続分で分けないといけないのではないか」と疑問が生まれます。(分割案②)
【分割案②】
妻:土地1000万円、家屋200万円、現金1900万円
長男:現金1550万円
長女:現金1550万円
ここで質問です。
【分割案①】と【分割案②】はどちらが正しいのでしょう?
(補足)
もちろん、遺言書があっても、相続人全員が合意すれば遺言書と違う割合で分けられるということは承知しています。今回の質問は、遺言の包括遺贈の割合を絶対的なものとして考える時に、実務的には、現場ではどちらで計算しているかを知りたいです。
税理士の回答
小規模宅地の特例はあくまでも相続税のためのものですので、分割案①か②かと聞かれれば、②ということになります。
ただし、家庭裁判所が審判で判断する際には実勢価格(時価)で判断しますから、遺産分割においては②でもなく実勢価格を基準とするのが一般的でしょう。
実務的にというのであれば、包括遺贈の割合を絶対的なものとして考えることに意味はなく、実勢価格を不動産鑑定士に有料で依頼してまで算定するのか、不動産業者に無料査定してもらうか、相続税評価額を8で割って10をかけるのかなども含めて、相続人間で協議がまとまればよいわけです。
ご回答いただき、ありがとうございました。
実務的な対応に関しても教えて頂き、理解が進みました。
本投稿は、2023年03月14日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。