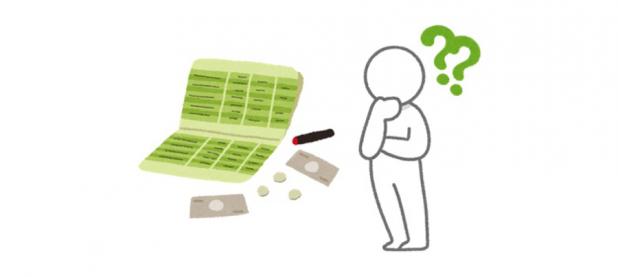母親の遺産相続財産に、土地と債権がある場合について
7日の月曜日に相続税無料相談をさせて頂き大変助かりました。
その際に、法定相続人が姉弟2人居て、母親の残した財産が、土地と弟への債権があり、
その債権含め、姉の方に全額相続させると言う内容にした場合、弟から、遺留分の請求をされる可能性があり、その場合は、
土地と債権のどちらかは選べない。
しかし、もし、母親の土地が、
1パーセントでも母以外の名義が含まれていたら、遺留分の請求をされた時に、
土地の方は現金化出来ないと教えられました。
裁判を起こされた際、母親の土地を弟に渡さないようにする為、
贈与税が掛からない110万の範囲で、姉である私か、あるいは、私の主人に贈与してもらおうかと考えました。
そのような場合、贈与する相手は、法定相続人の私では意味がないのか、他人にした方が良いのかを確認し忘れた為、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

確認ですが、まだ、相続は起こっていない。
相談文では、姉弟と表現していますが、これは母から見て子のことですね。
相続のときまでに、姉にすべての財産を相続させる旨の遺言がある状態にするということですね。
そうであれば、弟と表現している子の遺留分を侵害している状態で相続を行う意向ですね。
もちろん弟の遺留分を侵害していますから、弟は、遺留分を請求することができ、姉は遺留分に相当する現金を支払うのが原則です。
2019年7月1日以後に発生した相続から、民法改正により遺留分減殺請求から、遺留分侵害額請求の制度に変わりました。
何が変わったかというと、現物引渡しから、金銭の引渡しに変わりました。なので、侵害している遺留分に相当する金銭を用意すれば良いので、現物である母親から残した土地を手許に残すことは可能です。
もし、金銭が手許にないので、渡せないのであれば何らかの方法により金銭を調達する必要があり、場合によっては、あなたの所有する金銭以外の財産を売却、又は代物弁済することになるかもしれません。
金銭がないから諦めてくれが通れば良いですが、共有の土地は売却が非常に困難です。売却できないからといって、遺留分侵害の状態が解消される訳ではないので、母親の土地を売却が困難な状態にするのは得策ではないと思います。
それよりも、遺留分を侵害する金額に相当する金銭を用意した方が良いと思います。
繰りかえしますが、新しい制度では現物の引渡しは請求できず、侵害している金額の金銭の請求です。
長谷川様
早速のご回答ありがとうございます。
ご質問頂いた件は、ご理解のとおりです。
また、ご回答の内容を了解しました。
もともと相続予定財産内容が、
土地と母から弟に貸した債権であるので、
遺留分請求された場合でもその債権分から遺留分相当を相殺できますね。 この理解で正しいでしょうか?
土地で払う事がないのであれば、
母親の土地を1部他の人に贈与する必要が無くなります。
貴重なアドバイスをありがとうございます。

債権と相殺?
債権の一部を相続させるのであれば、金額により遺留分を侵害しない可能性があると思いますし、債権を現金化して遺留分侵害額を払えば、丸く収まると思います。
相殺という表現はおかしいとは思いますが、大体、いいたいことは分かります。
債権というのが、母が貸付金で、弟は借入金というのなら相殺かもしれませんが。
再回答をありがとうございます。
はい、母が弟に貸し付けた金額は、
弟への遺留分相当の金額を大幅に上回っています。
遺留分は、弟としては、自分の債務が減る、つまり母から私へ相続される
債権金額から、弟の遺留分金額を差し引くと言う意味です。
相殺と言う表現でないのであれば、なんと言う表現が正しいでしょうか?
母の遺言書に、書く文言として
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

相殺と言うことは考えずに遺言書に書けば良いです。
弟に対する債権を、弟に取得させると、相殺ではなく、債権債務が同一人物となるため、民法の混同の規定により、債権債務が消滅します。
なので、混同は意識せずに「弟には、弟に対する貸付金のうち○○○円は弟に、○○○円は姉に相続させる」とか「姉にすべての財産を相続させる」などと書いて貰えば良いです。
前者で弟に相続させる貸付金が少ないか、後者なら遺留分侵害の状態になり、対処は私の最初の回答になります。
再再回答をありがとうございます。
とても良く理解出来ました。
これで、遺言書の表現もクリアになりました。
貴重なアドバイスを何回もしていた深謝いたします。
本投稿は、2020年09月09日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。