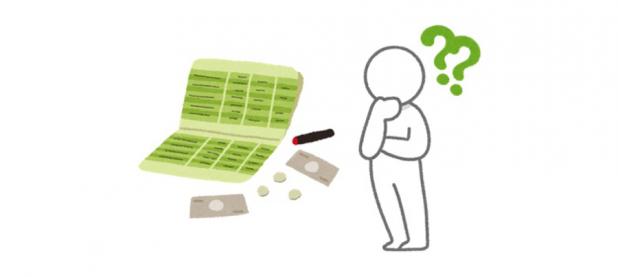相続と遺贈の税金の違いについて
現在余命宣告をうけ、自身の相続についての整理と遺言書の作成を進めています。
事業を経営していることもあり、自身の財産の状況が複雑なため、②実子には現金(現金、有価証券等)等のわかりやすい財産を残し、残りの自宅不動産、債権債務(会社の連帯保証、住宅ローン等)、出資金等は、①③④に相続もしくは遺贈したいと考えています。
関係者としては、下記になります。
①母(父死亡)
②実子(3人)元妻が養育中。
③妹(+夫+3人の子)※普通養子縁組も検討中
④弟(+妻+2人の子)※普通養子縁組も検討中
【質問内容】
この場合には、法定相続人としては②実子3名となりますが、③④の妹弟を養子にしない限り相続させることはできないのでしょうか?それとも、養子にしなくても、「遺贈」すえれば、妹弟の負担する税金は同じなのでしょうか?(基礎控除の加算等、不動産登記関係)
税理士の回答

遺産にかかる基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)や相続税の総額を計算する場合の各取得金額の法定相続人は、実子がいる場合でも1人は相続人として計算に含みますから、実際のところ、節税効果は見込めます。
2人以上養子にしても、その部分の税負担は同じです。
なお、妹の子、弟の子を養子にすれば、民法上は相続人となり、一親等の親族となるため、相続税の二割加算の規定が適用除外となるので、節税効果はあります。
税負担は以上の通りですが、養子縁組すると相続人としての権利が発生しますから、遺産分割の話し合いで揉める要素の一つです。
財産を渡すのが目的であれば、遺贈をすると相続人以外にもできます。ただ、遺贈と相続では登記費用も遺贈の方が高いです。
相続で、揉めないとの自信があれば、養子縁組、そうでなければ遺贈を考えたらどうでしょうか。
ご自身のお身体が大変なご状況の中、ご相続のことをお考えになられるのは本当に大変なことと存じます。
まず、妹様、弟様に財産を承継されたい場合は、養子縁組でなくとも遺言書を作成することにより遺贈することができます。
ただし、現在の法定相続人であるお子様には遺留分が存在するため、ご自宅不動産、債権債務、出資金などの時価が高く、お子様へ相続等させる予定の現金等の額が遺留分に届かない場合、その差額が妹様、弟様に請求されることになる可能性がございます。
養子縁組をされると1人あたりの法定相続分が減り、遺留分もそれに伴い減少しますので、遺留分の問題も解消しやすい状況にできるかもしれません。
なお、遺留分の計算は相続税評価を基に行うものではないので、その点ご留意ください。
以上は相続に関する問題です。
続いて、相続税の問題です。
妹様、弟様と養子縁組しない場合、相続税の計算における基礎控除は、実子であるお子様の人数で計算されることとなります(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)
また、一親等の血族以外であるため、妹様、弟様が負担される相続税が、2割加算されます。
養子縁組をする場合、実子がいるときは1人までしか上記計算に加算できません(3,000万円+600万円×4人=5,400万円)
この場合は、2割加算はございません。
法定相続人となれば、登録免許税も税率が下がり、不動産取得税も非課税となるように進めることができます。
相談者様の家系に財産を残したいのか、元配偶者様の管理化になったとしてもお子様に残したいのかによってご決断は変わることと存じます。
以上の件は、事業の承継のこともございますでしょうし、詳細な状況を勘案して判断したほうが宜しいかと思いますので専門家にご相談されながら遺言書のご準備をされることをおすすめ致します。その方が、ご相談者様のご負担にもならず、お考えを形にすることができるのではないでしょうか。
本投稿は、2021年05月21日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。