遺産分割協議書の文言と事業承継税制の適用要件について
相続および事業承継税制に関するご相談です。
現在、親族間で遺産分割協議書の調整を進めており、相続人の一人が事業用財産を承継し、事業承継税制の適用を申請する予定です。
協議書の案文に、以下のような文言が含まれています:
「本協議書に記載なき遺産および後日判明した遺産・債務は○○が取得または負担する」
この一文の税務上の妥当性やリスク、代替案の可否について懸念があります。
【現状】
- 相続税申告および事業承継税制の手続きは税理士事務所に依頼中です。
- 担当は補助スタッフで、税理士本人から文言の説明は今のところ受けていません。
- 上記の文言について補助スタッフからは、「後日判明した財産はすべて後継者が取得する」または「全員で協議する」のいずれかが一般的だと言われました。
- 私としては、あるかないかわからないものを決めてしまうのは不安なため「原則後継者が取得するが、高額等の場合は協議のうえで分配する」といった柔軟な文言(バランス型)を提案しましたが、「曖昧な表現は手続きが複雑になる」として否定的でした。
【確認したい点】
1. 「後日判明した遺産は後継者がすべて取得する」との文言は、事業承継税制の適用要件として本当に必要なのか?
2. 「原則取得、ただし高額等は協議」という文言でも、制度適用に支障がないケースはあるのか?リスクがあればどんなリスクか。
3. 上記の文言があるまま万一財産が出てきた場合、他の相続人は内容を知る権利や協議の機会があるのか? また、後継者から分けてもらった場合に贈与税が発生する可能性や、事業承継税制の取消リスクはあるか?
4. このような重要な文言を含む協議書を作成・進行する際、税理士本人の説明がないまま補助スタッフだけで進めるのは適切か?
【補足】
現在提示されている事務所からの手続きの流れは以下のようなものです:
① 遺産分割協議の成立
② 税理士事務所で協議書や相続税申告書類等の作成
③ 相続人宛に署名・捺印書類の送付(現時点で税理士本人の関与説明はなし)
このような進め方に不安を感じており、公平性と制度の安定適用の両立を目指したいと考えています。
実務的なご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
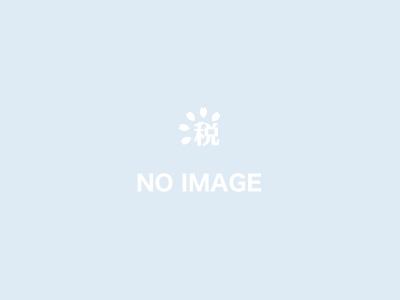
安島秀樹
似たような案件で、遺産分割のやり直しとかあります。法律にはっきり規定していないことは役所の通達や、裁判所の判例の積み重ねでだんだんとはっきりすることになるとおもいます。事業承継税制は役所の利用促進策にもかかわらず件数はほとんどでていないとおもいます。不確かなことはあらかじめつぶしておいたほうがいいという税理士さんのすすめではないでしょうか。明確な回答は税理士にはできないようにおもいます。
本投稿は、2025年07月27日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






















