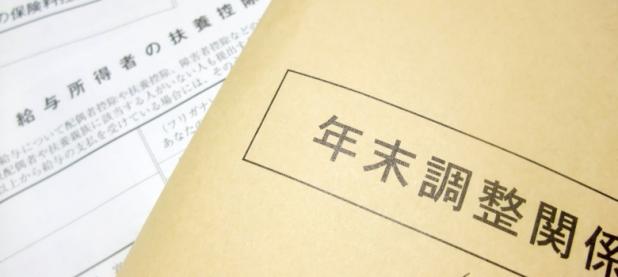退職後の年末調整、確定申告の要不要を知りたいです。
配偶者の海外赴任帯同のため、20年務めてきた会社を退職することとなりました。
9/30付で退職になるので、今年の年末調整を自分で依頼しなければならないのでしょうか。
また、確定申告が必要になるでしょうか。
予定としては、10月に配偶者の扶養に入る予定。
おそくとも11月には海外に引越することになります。
手続き上、本人が行えない場合は代理人を立てる必要があるのでしょうか。
税理士の回答

配偶者の海外赴任が1年以上の予定であれば、同行する貴女も出国の翌日から「非居住者」になります。
居住者から非居住者になるかたは
1 「出国前」に準確定申告をして、居住者期間の所得税の精算をする 又は
2 出国前に「納税管理人」の届出書を提出して、通常の確定申告時期に納税管理人により確定申告を提出することになります。
貴方が、日本国内に賃貸用不動産を所有するなど、非居住者であっても国内源泉所得がある場合は、確定申告義務が有りますので納税管理人を立てる必要がありますが、そのような事情がない場合は出国前に準確定申告をする方がベストではないかと考えます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「給与所得者で国外提出を予定される方へ」のパンフレット
なお、フローチャートでは、「手続き不要」に該当しますが、これは、海外出向などで勤務が継続されている方は、会社で「出国前年末調整」を行うからになります。
貴女の場合は退職をされておりますので、準確定申告により所得税の精算を行うことになります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/kokugai/pdf/04210617_01.pdf
「海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収」
あなたは、年末調整を行いませんが、申告をする際の「控除」の範囲などについて参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
「準確定申告の記載見本」です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2020/pdf/016.pdf
「海外勤務と所得税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
お世話になります。早々にありがとうございます。
>海外赴任が1年以上の予定
少なくとも1.5年以上なので、海外転出届を出す予定です。
>「出国前」に準確定申告をして、居住者期間の所得税の精算をする
なるほど。こちらで準備を進めていこうかと思います。
別件にはなるのですが、渡米後 落ち着いたらnoteなどを利用して収益化を考えております。
この場合、非居住者ですが円で収益を得ることになりますが、
居住地に納税する原則通りに、納税の全てはアメリカで実施する認識で間違ってないでしょうか。
もし御存知でしたら、ご享受いただけると幸いです。

非居住者の日本の課税に関しては、「国内源泉所得」のみ課税になります。noteの収入が国内源泉所得になるか否かは、その内容で判断されますが、おそらくは課税対象外になる可能性は高いと思います。
また、米国の課税に関しては詳細は不明となりますので、米国の課税に関しては、米国の課税当局又は税理士にお尋ねください。
※日本と同じような「非永住者」の規定があるか否かも分かりません。
なお、日本の国内源泉所得に該当するか否かは、notaeによってどのような収益を得るかにより、判断されると思います。
いわゆるアクセスによって得る広告収入なのか、当該映像や文章などの著作権に係る収入なのか。
仮に著作権の使用料的な収入であっても、日米租税条約で日本では免税に該当しますが、支払者を通じて手続きが必要になります。
貴女は米国の居住者になると考えられますので、まずは米国に課税権があると考えます。
そこで、申告方法など課税当局又は米国の税理士に確認されることをお勧めいたします。

追伸
恐れ入りますが、「新しい質問」に対しては、別途ご質問をupされるようにしてください。
その方が、より多くの先生方の目に触れますので、詳しい先生からアドバイスをいただけると思います
早々にありがとうございます。
新規質問も教えていただきありがとうございます。
新規質問については、今後別に設けさせていただきます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
>新規質問については、今後別に設けさせていただきます。
⇒ お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年09月05日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。