投資不動産(中古マンション)の減価償却費計算においての設備費の割合の調査方法について
投資不動産(中古マンション)の減価償却費の計算において、マンションと設備を分けて計算したいです。設備があること自体は確かなのですが設備費をマンションとわけて算出するためにはその割合を証明できるものがないと実際に設備があったとしても設備として定率15年の算出はできず、マンションに一括して計算するべきと言われています。ただし設備自体はあり、かつ設備として計算できた場合には償却費が多くなるため可能であればそちらを採用したいと思ってます。
都税事務所での調査も試みましたが、マンションが古く明確に設備費の明細(割合)がわからない、と言われてしまいました。つきましては他にマンションの設備を調査する、証明する方法はないでしょうか?
税理士の回答
中古資産の法定耐用年数も検討されたら良いと考えます。
(参考)
No.5404 中古資産の耐用年数
[平成30年4月1日現在法令等]
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。
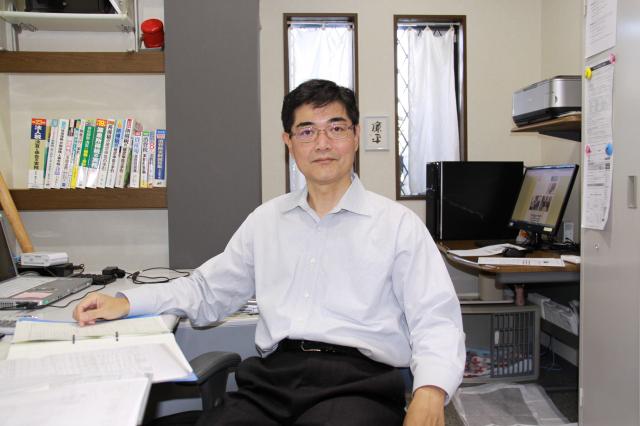
別府穣
設備=建物付属設備と察知しました。建物付属設備は新築であっても耐用年数15年、かつ定額法しか使えません(現行税法)
ご質問者様の御内容では客観的に耐用年数を設定するの困難かと思います。
簡便法を使うにしても建物付属設備の取得価格を算定するのは難しいかと存じます。
よって建物の取得価格に含めて減価償却をされたら如何でしょうか?
ご回答ありがとうございます。
建物付属設備のことです。
>よって建物の取得価格に含めて減価償却をされたら如何でしょうか?
建物に含めるより、建物と設備としたほうが減価償却費が増加するため、設備がたしかに存在するのであればそれをなにかしら合理的な根拠で算出したいと思ったのですが、方法はなさそうということですか?
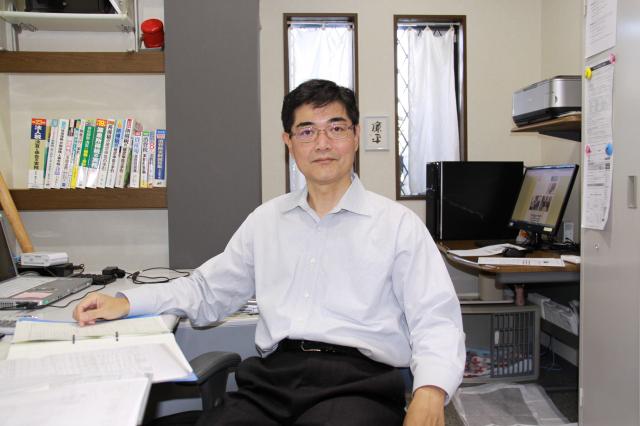
別府穣
資本的支出の関連が国税庁に記載されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
ご参考お願いいたします。
本投稿は、2019年01月19日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

























