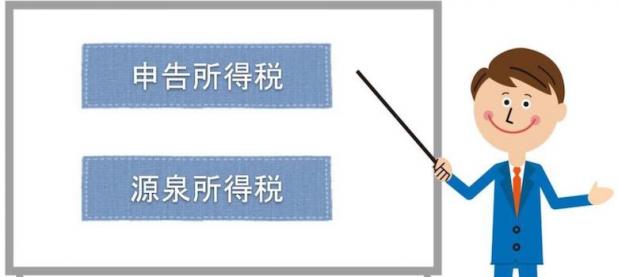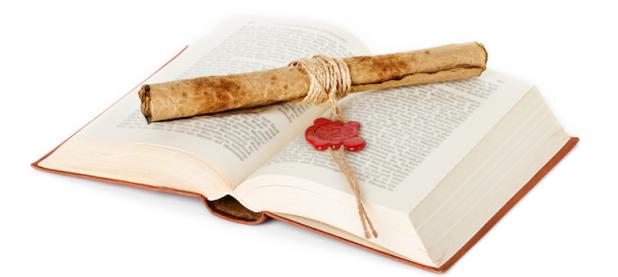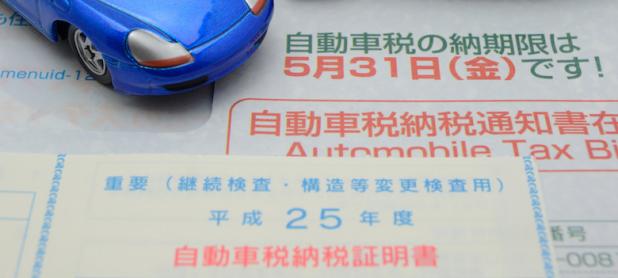著作権の譲渡対価を譲渡所得として申告すべきか事業所得とすべきか?
状況:
年収1000万のサラリーマンですが、ウェブサイトを作成し、そこに自作の小説を載せたり、自分で原作を書いて、漫画家さんに対価を支払って作成した漫画を掲載することで集客を行い、そこに広告を載せて広告収入を年間500万円程度得ています。また、漫画を販売する権利を電子出版社に卸すことで年間400万円程度の印税収入を得ています。広告収入、印税収入については事業所得として青色申告(65万円控除)を行っています。
相談内容:
漫画の原作を漫画家さん(個人事業主)に譲渡して対価10万円を受取りました。
この収入について、所得税の区分は譲渡所得と考えていますが、一方で事業所得と認定されるおそれもあると考えています。専門家のご意見を頂きたいです。
譲渡所得と考える理由:
「漫画原作者としての印税収入と広告収入」と「著作権の譲渡による収入」は同じく、私が創作した著作物という固定資産の価値に起因する収入ではありますが、以下の点で決定的な違いがあります。
即ち、「漫画原作者としての印税収入と広告収入」については、漫画原作をもとに、私の指揮命令のもと、漫画家さんを使って、完成漫画という更に価値の高い資産を作り上げ、その資産を利用して、印税収入や広告収入を継続的に得るものであります。
一方、 「著作権の譲渡による収入」については、資産そのものを売却することによって一回限りの収入を得るものであります。ちなみにその後は、漫画家さんがご自分の判断で完成漫画の形にして、漫画家さん自身が印税収入を得て、私には追加の収入はありません。
賃貸業(土地と言う資産を利用する事業)を営み事業所得を得ている大家さんが、土地を譲渡して収入を得た場合、譲渡所得としての申告が可能と聞きます。
そうであれば、私の漫画原作に掛かる著作権の譲渡については、期間も不定期であり、頻度もせいぜい年間10回程度であり、譲渡対価も100万円程度にすぎないのですから、到底事業規模であるという結論には至らないものと考えます。
どの程度になれば事業規模との認定を受けるかについては、想像の域を出ませんが、頻度が年1回程度であれば譲渡対価が1000万、2000万であっても土地の例を見ると譲渡所得になると考えますし、頻度が年間10回程度であれば譲渡対価の総額が年間300万円程度までであれば譲渡所得になると考えます。
税理士の回答

小野陽祐
ご記載の内容について、理論的にはどちらも成立すると思います。
著作権は譲渡所得の対象資産です。(タックスアンサー3105でも例示列挙されています。)
一方で、ご記載の通り、営利目的で継続的に譲渡を行っていれば事業所得とされます。
不動産であれば、業として不動産の売買を行うには許認可が必要なのでわかりやすいのですが、ご記載のケースでは実質的判断になると思われます。
頻度や定期・不定期などで画一的な基準はなく、それぞれの資産の性質によっても異なります。
私の考えとしては、貴殿の事業の範囲を広くとらえ、著作権自体の売却も主たる事業目的に従って行われるものと判断し、事業所得と考えます。
理由
ご記載の通り、著作権自体の売却が営利目的で継続的に行われているかどうかです。
貴殿の事業の核は「創作、著作」であり、原価の面でも、貴殿は日常的に「創作、著作」に関する費用を事業経費として損金計上しているものと思います。
そういった営利事業の中での販売形態として著作権それ自体を売ったり、著作物の出版権を売ったり、その他ご記載の形式で収入を得ているものと考えます。
私の考えとしては、著作権の「創作、著作」事態が事業の一環の中にあり、しかも、年間10回程度もそのような形態の販売があれば、
営利目的で継続的に譲渡を行っていると判断し事業所得とします。
なお、譲渡所得とした方が納税者としては有利になります。譲渡所得とするためには税務署との事前の話し合いと、ある程度の覚悟を持って行うことをお勧めします。
レアケースで、難度の高い質問にご回答ありがとうございます。ご回答の内容を反映して、どの程度の譲渡額と頻度が妥当かなどを考えつつ、覚悟をもって創作、申告を行っていこうと思います。
ご回答を参考に宅建法なども眺めてみましたが、著作権の譲渡先は不特定多数というわけではなく、特定の相性の良い漫画家さんなので、そういう点では非事業的と解釈する方向にプラスと思います。
また、私の事業活動が「創作、著作を核にしている」とのご指摘はその通りなのですが、そもそも値段を付けて著作権を売るという行為自体が、「創作、著作を専業にする作家、漫画家」か、「いわゆる先生と呼ばれる専門家」以外には困難かと思います。高収入で安定的な後者の著作権譲渡を優遇して、不安定な前者の著作権譲渡を厳しく課税することには社会的公正の観点からやや違和感があります。
創作の場合、インスピレーションが全てですので、長期継続的な収益をあげるのがそもそも難しいのですよね。
いろいろ考えさせて頂きました。有難うございました。

小野陽祐
そもそも論ということでは、事業主が事業目的の資産を売却した利益は事業所得とすることが理に適っていると思います。
ただ、特に土地や建物といった不動産は経常的な取引金額よりも大きくなりやすく、政策的な意図として一定税率の分離課税となっています。
総合課税の譲渡所得の対象となるものに事業用固定資産を含むのはオマケのようなものだと思います。
このように納税者を政策的に救済する措置として見れば、私はまんざら悪い仕組みでもないと思います。
なお、譲渡所得・事業所得の区分の話からは逸脱しますが、会計基準が知的財産についての対応に手を焼いているということもあります。
税務の基準は会計基準に従う形になっているのですが、会計基準の場合、
貸借対照表の資産価値にも一定の配慮があるため、無形のものは特に難しいのだと思います。税務の立場で一方的に基準を作るとすれば、著作や創作のための出費は
すべて資産計上の上、減価償却ということになるでしょう。そして、除却に関しては相当ナーバスにならないといけないような基準になると思います。考えただけでいやになります。
会計基準としては研究開発費及びソフトウエアの会計処理に関する実務指針及びそのQ&Aというものがあります。
この基準は創作・著作については対象としていませんが、参考程度にはなります。結局貴殿のようなケースでは創作・著作に関する費用は研究開発費として即時費用計上となります。
この中で強いて類似のものとしては、自社作成の販売用ソフトウエアの基準ですが、商品マスターとしてある程度形になるまでの費用は研究開発費として費用計上です。
譲渡所得の規定がある中で、なぜこのような例外を定める必要があったのか「営利目的で継続的に行われている」とは具体的にどの程度のことを指すのかなどと更にいろいろ検討しましたところ、証券の譲渡に関して、「年間50回以内で20万株以下の取引であればそこで得られた所得を非課税とする制度があった(昭和63年改正前所得税法9条1項11号)」との記載を発見しました。
また、現在は措置法第37の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》により、略所有期間が1年を超えるものの譲渡に関しては譲渡所得としてよい規定もあるようです。
こういった規定を参照しつつ、自分で創作した著作権が常に長期譲渡として取り扱えることも考えますと、やはり年間10回程度でも事業所得になるとするご意見は創作者にとって酷に過ぎると考えますが如何でしょうか。
実際に収益を得ている以上は営利目的ではないとの主張は難しいとは思うのですが、創作というのは(私の場合ですが)「他人の心を揺さぶる素晴らしい作品を作りたい」というものが根底にありまして、決して営利のためだけではないのです。また、作品も大げさな言い方になりますが自らが生み、育てた我が子であり、思い入れがあるものです。株式の譲渡に譲渡所得が許されて、著作権の譲渡に譲渡所得が許されないのはおかしいのではないでしょうか。
本投稿は、2016年04月16日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。