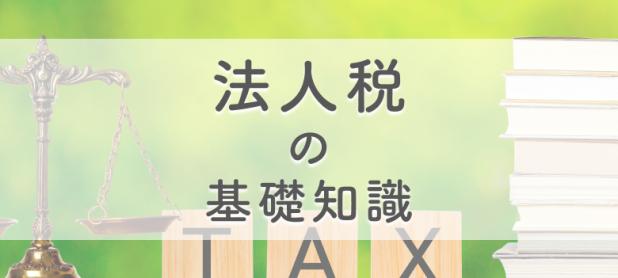学会の学術集会における税について
医療関係の学会についてです。
・本部のほかに都道府県支部があり、全国規模の学術集会とは別に都道府県支部単位の学術集会がある
・都道府県単位の学術集会の当番病院は、その都道府県内にある様々な病院が毎回入れ替わる
・学術集会の会長は当番病院の院長または管理者等が当たる
・学術集会の運営資金は前回開催当番病院より引継ぎ、学術集会終了後精算して、余剰金を次回開催当番病院へ送金する
・講師へ講演料を支払うため、税務署への給料支払事務所登録は、その学術集会の名義、会長名にて行う
・収入として、参加費・広告収入・寄附金・雑収入(誤入金があったものの支払者より返金不要の申し出があったもの、等)がある
・学術集会は任意団体で、税務処理は都道府県支部とは別に扱う
・学術集会自体に定款はなく、都道府県支部の定款に準じる
Q1. 上のようなケースの場合、広告収入が法人税の課税対象となるのですか?
Q2. 法人住民税、法人事業税も課税されますか? 他にかかる税はありますか?(会計規模が1,000万円未満の場合消費税は関係ないと思いますが)
Q3. 課税される場合、税務署、都道府県、市町村に個別に申告するのですか?
Q4. 万が一課税されるとして、余剰金が税額を下回った場合、どうなるのですか? 開催当番病院が公立病院なら、病院からの補填はハードルが高いと思いますが…。
以上、長文・多質問となりましたがご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
学術集会は「人格なき社団」に該当し、「収益事業」のみが法人税・法人住民税の課税対象になります。
「収益事業」は34業種に限定されており、「広告業」はこの中に含まれていませんので、「収益事業」に該当しないと思われがちですが、実際には、広告がどのような内容かによって判断することとなっています。
・広告主から依頼を受け、内容・デザイン・カットなどを行う場合・・・・・「請負業」(収益事業)
・広告主から提供されたものをそのまま掲示する場合・・・・掲示する媒体の付随事業
たとえば、
出版物に掲載するのであれば「出版業」(収益事業)
会報等に掲載するのであれば会費収入に付随する事業(非収益事業)
Q1. について
広告収入が法人税の課税対象となるかどうかは上記の内容次第です。どのような収入かは不明ですので。
Q2. について
法人税の課税対象となれば、当然、法人住民税、法人事業税も課税されます。
Q3.について
法人税・地方法人税は税務署、
法人都道府県民税は各都道府県、
法人市町村民税は各市町村
に個別に申告します。
Q4. について
収益事業部分のみ課税され、会費・寄付金などは課税されませんので、剰余金が納付税額を下回るのは、非収益事業部分の使途(使い道)の問題であることになります。税金の問題よりも、全体の事業経費の問題だと思われます。
詳しく説明くださり、ありがとうございます。
追加の質問ですが、
●寄附金…個人、会社を問わず、開催趣意に賛同してなされる寄附金なら非課税ということで合ってますでしょうか?
●広告費…例えば、学術集会の抄録集(参加者をはじめ寄附者、広告提供業者、特別講演者、学術集会のスタッフ等に無料で配ったり、前述の人たちだけが見られるようにパスワードをつけてホームページで公開する)に載せるための広告掲載費なら、課税の対象となるということで合っていますでしょうか?
●企業に展示ブースを貸し出して費用を受け取る場合、課税の対象になるかと思いますが、ランチョンセミナーや、ウェブ形式の学会ならオンデマンド方式の共催セミナー(スポンサー企業が共催セミナー費として学会に費用を払い、企業は講演者を決めて講演動画を依頼・学会に提出する)の費用をもらった場合、課税の対象になりますか?

土師弘之
・寄付金収入・・・・・収益事業でないため非課税です
・広告収入・・・・・妙録集が無料配布なら出版業に当たりませんので、その妙録集にスポンサーから提供された媒体をそのまま掲示するだけなら収益事業(課税)にはなりません。
・ブースの貸し出しは席貸業(収益事業)ですが、
・ランチョンセミナー・共催セミナー・・・・・セミナーの内容が「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車・小型船舶の操縦、学力の教授」に限定列挙されている技芸教授業に該当しなければ、収益事業(課税)になりません。
ありがとうございます。
共催セミナーについて、医学的内容や労働基準などの内容の講演だと、技芸教授等に該当しないということですね?
セミナーは、参加者は無料で参加でき、講演者を手配・講演者へ講演料を支払い会社名を抄録集等に載せる企業からスポンサー料の支払いを受ける場合でも、収益事業に当たらないということで合っていますでしょうか? ランチョンセミナーの場合は、企業が学会にスポンサー料の支払いをし、講演者を手配・講演者に講演料を支払い、参加者用の弁当も費用負担しているそうですが…。
法人税の課税対象となれば法人住民税も課税されるそうですが、課税対象でない場合、均等割はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

土師弘之
セミナー自体が収益事業に該当しなければ、協賛金も収益事業の付随収入にはなりません。
ただし、講演者に対する講演料は源泉徴収の対象となります。
法人の課税対象でなければ、法人住民税も均等割を含め課税にはなりません。
ありがとうございました。
やはり素人だと判断が難しいですね。
最後にもう一点だけ質問させてください。
広告に関して、
・広告主から依頼を受け、内容・デザイン・カットなどを行う場合・・・・・「請負業」(収益事業)
・広告主から提供されたものをそのまま掲示する場合・・・・掲示する媒体の付随事業
ということですが、例えば、スポンサー企業から、広告データの完成版PDFなどで提供してもらい、抄録集に載せる場合、寸法が大きすぎたので抄録集に合うように少し縮小したり、逆に小さすぎるので少し拡大して載せたりする行為は、請負業に該当するのでしょうか?
広告データのすぐ外に「サイズ変更禁止」と書いている企業や、「〇〇mm×〇〇mm」とサイズを表記している企業もあれば、何も表記していない(ファイルのプロパティでページサイズを確認しないと分からない)企業もあるようです。

土師弘之
請負となるのは、アイデアを出して広告のプランニングを行う場合であって、サイズの変更だけであれば請負には当たりません。
なるほど、よく分かりました。ありがとうございました。
すみません、さらに質問したいことが出てきました。
Q5.参加費を、参加申込者が誤って振込手数料を差し引いた額で振り込んでしまい(A円)、その後改めて振込手数料を差し引かずに振り込み(B円)、最初のA円の返金は不要と言われた場合、学会側では「雑収入」として計上するかと思いますが、これは課税対象になるのでしょうか?
Q6.抄録集自体の販売はしませんが、参加費・広告掲載費・寄附金・共済セミナー費を払った人ならびに企業や、学術集会スタッフ、講演者、後援団体、当番病院の部署といった、限定した範囲で渡したり公開したりし、不特定多数に渡したり公開したりするのでない場合、参加費や広告掲載費等が、事実上の抄録集代とみなされてしまうことはありませんか? ちなみに、参加費は学会会員の方が非会員よりも安く設定されているとします。
Q7.毎回「第○回」という数字は異なりますし、会長名も違いますが、過去の学術集会と同一の団体とみなされるのでしょうか?
Q8.次の開催当番病院が準備できるよう、ある程度の余剰金を残し、開催準備金としてリレーしますが、同一の団体とみなさない場合、最初に受け取る開催準備金は課税対象となりますか? もし自病院で開催した際に余剰金が多すぎた場合はどうなりますか?全額次回開催当番病院へ渡しますが…。
多質問ですが、よろしくお願いします。

土師弘之
Q5について
収益事業に当たる事業に係る雑収入ではないため、課税対象にはなりません。
Q6について
参加費や広告掲載料というのは名目で、実際には妙録集代であったということであれば「出版業」に当たるかもしれませんが、そうではないはずです。
会員はそもそも会費を支払っているのですから、非会員と参加費が異なるのも当然のことです。
Q7・Q8について
毎年毎年会員を募集してその都度解散する学術集会ならば、1回ごとに別の団体だと言えますが、第1回目から会員(構成員)はほとんど変わらないはずなので、団体として継続していることになりますです。
トップが変わったらその都度別の団体になるようなことは聞いたことがありません。病院の院長が変わったらからといって別の組織の病院にならないということと同じことです。
団体が継続しているので、当然余剰金は翌期に繰り越されます。なお、当該余剰金は、会計上は収入として計上する場合もありますが、新たな収入ではありませんので、課税になることはありません。
ありがとうございます。
講演される先生に講演料を払うために給料支払い事務所開設届出をする必要がありますが、法人番号が分からないので空欄にして、新たに法人番号を発行してもらうことになる場合でも、前回と同じ団体とみなされるんですね。

土師弘之
法人番号は1度取得したら半永久的にこれを使用します。新たに発行するのではありませんので、前任に確認してください。
不明の場合は、「給与支払事務所等開設届」を一番最初に提出した担当者かその所轄の税務署に問い合わせる必要があります。
本投稿は、2021年07月12日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。