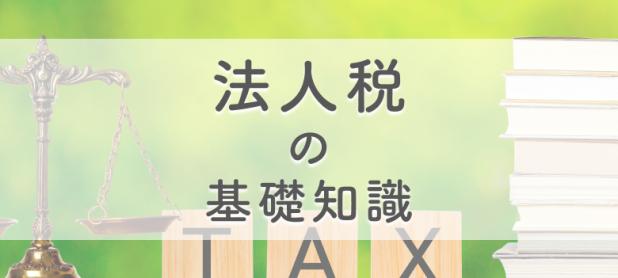電子取引における電子データの保存について(交付する側の対応)
令和4年1月1日以降に電子取引で受領または交付した電子データは、電子データで保存するのが義務となりますが、交付する側の対応は下記の認識で合っていますでしょうか?
【例】自己が一貫して電子計算機で請求書を作成し、書面で発行。(交付する側は原則、書面で保存)
①電子データ → 電子データの場合
書面を電子データ(PDFファイル)に変換し、電子メールで送信した場合は、電子取引に該当するため、交付した側も電子データで保存する。
②書面 → 書面の場合
書面を電子データ(PDFファイル)に変換し、電子メールで送信した後、郵送した場合は、電子取引に該当しないため、交付した側も書面で保存する。
交付する側は、電子データ保存と書面保存が混在することになるため、特例である電子帳簿保存法4条②を適用した方が良いかと考えております。(税務署への事前承認は不要)
まとめると以下のとおりです。
【自社が交付する場合】
・電子取引(自己が一貫して電子計算機で作成。例えば、請求書や領収書など) → 電子データで保存(電子取引のため電帳法7だが、電帳法4②を適用)
・電子取引(自己が一貫して電子計算機以外で作成。例えば、見積書や注文書など) → 電子データで保存(電帳法7)
・書面の交付 → 原則、書面で保存。電帳法4②を適用すれば電子データで保存が可能。
【自社が受領する場合】
・電子取引 → 電子データで保存(電帳法7)
・書面の受領 → 書面で保存(原則)
電子取引で受領または交付した見積書や注文書の電子データまで保存となると、かなりの労力が必要となるため、一般書類である見積書、注文書は書面で保存、重要書類である契約書、納品書、請求書、領収書だけを電子データで保存したいと考えております。青色申告の承認取消しになる可能性は少ないと思っておりますが、他に問題等ございますでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「電子取引」とは、メールやネットなどで取引情報をやり取りすることで、書面を一切交わさないデータの授受をいいます。
令和4年1月1日以降は、「電子取引」はデータで保存することが義務付けられ、書面に出力して、法人税法・所得税法に規定する「帳簿書類」として保存することが認められなくなります。
したがって、同日以降に書面に出力して「帳簿書類として」保存し電子取引データを削除すると取引記録を保存していないこととなり、帳簿等の保存義務違反となり、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
したがって、以下の部分に理解の誤りがあると思われます。
「②書面 → 書面の場合
書面を電子データ(PDFファイル)に変換し、電子メールで送信した後、郵送した場合は、電子取引に該当しないため、交付した側も書面で保存する。」について、
相手方に電子データと書面との二重に交付することになるため、どちらが有効なのか効力に疑問が残る。電子データをメインにすると「電子取引」に該当し、書面の保存は不可。(令和4年以降)
「・電子取引(自己が一貫して電子計算機で作成。例えば、請求書や領収書など) → 電子データで保存(電子取引のため電帳法7だが、電帳法4②を適用)」について、
電子取引に該当すると、書面に出力し帳簿書類として保存することは認められません(法定外の参考書類として保存することは任意)。したがって、電帳法4②を適用することはできません。(令和4年以降)
土師先生ご回答ありがとうございます。
相手方に電子データと書面との二重に交付することになるため、どちらが有効なのか効力に疑問が残る。電子データをメインにすると「電子取引」に該当し、書面の保存は不可。(令和4年以降)
取引先ごとに継続性があるか・ないかで判断しても良いのでしょうか?
・A社へ電子メールで送信後、書面を継続的に郵送 → 書面で保存。
・B社へ電子メールで送信後、書面を今回のみ郵送 → 電子データで保存。
「・電子取引(自己が一貫して電子計算機で作成。例えば、請求書や領収書など) → 電子データで保存(電子取引のため電帳法7だが、電帳法4②を適用)」について、
電帳法4②を適用することはできません。
現在、自己が一貫して電子計算機で作成した請求書や領収書などを税務署の承認を得てデータで保存し、電子メールやクラウドサービスで発信(交付)している。とします。
令和4年1月1日以降、電子メールやクラウドサービスで発信(交付)した場合、電子取引に該当し、データで保存するのが義務となるのであれば、交付する側は二重保存とならないでしょうか?「電帳法4②(作成)」と「電帳法7(交付)」どちらが優先されるのでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ございませんが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

土師弘之
「取引先ごとに継続性があるかどうか」で判断するのではなく、その書類が電子データか交付書面のどちらを有効なものにするかどうかです。書類1件ごとに判断します。(二重となってもいいので)両方とも有効なものとして取り扱うのであれば、その点をはっきりとさせたうえで、それぞれの処理規定(電子データ及び書類)に従うことになります。
「現在、自己が一環として電子計算機で作成した請求書や領収証などを税務署の承認を受けてデータで保存し、電子メールやクラウドサービスで発信(交付)している。とします。」
この記述には矛盾があります。
請求書や領収証などを電磁的記録で保存する場合、「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存」について税務署長の承認を受けるのは取引先に書面で交付する場合です。本来なら書面で交付するものはその控等を書面で出力保存しなければならないのを作成時の電磁的記録で保存する場合に適用されます。したがって、この場合電子データの交付記録を残さない場合にも適用されることになります。
そもそも、書面で交付しない場合(電子取引を行う場合)には、取引先に交付する書面はないことから、税務署長の承認は不要とし、電子データか出力しての書面保存かはどちらでもいいことになっていました。それが、令和4年1月1日以降は書面での保存が認められなくなったということです。
電子データと書面の両方を受け取った件ですが、
取引先から電子メールなどで取引情報を受け取り、そのあと取引情報の原本を書面で受領した場合は、原本を正本として取扱うといった社内のルールで取り決めを行っていれば「書面の保存のみで良い」と、いうことですね。
二重保存の件ですが、目的が異なるため、同じ取引情報の物でも保存が必要。と、いうことですね。
・写しを作成した記録として書面の保存が必要。
(電帳法4②を適用していれば電子データで保存)
・取引先へ交付した記録として電子データの保存が必要。
大変お忙しいなか、ご回答ありがとうございました。

土師弘之
「二重保存の件ですが・・・」の部分について、
電子データを交付した場合は、令和4年1月1日以降は書面の保存が認められませんのでご注意ください。
ご教示ありがとうございます。
写しを作成した証として書面を保存し、電子で交付した場合は、交付した証として電子データも保存するようにいたします。(同じ取引情報ですが、写し(書面)と交付(データ)の2つを保存)
本投稿は、2021年09月01日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。