起業家のための助成金・補助金まとめ【2022年版】
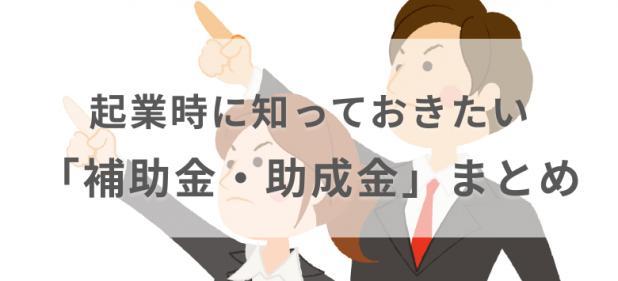
起業の際に利用できる助成金、補助金には様々な種類があります。ただし、受給する際はいくつかの注意点に気をつけなくてはなりません。
そこで「起業したいけれど資金が足りない」とお悩みの方に向け、気をつけるポイントをはじめ、目的別に利用できる代表的な助成金、補助金制度について紹介します。
※この記事の情報は2022年3月現在のものです。補助金・助成金の活用を検討する際は、各制度の最新情報をご確認ください
目次
「補助金」と「助成金」はどう違う?
補助金・助成金は、国や地方公共団体、民間企業などから返済不要な資金を調達できる制度です。しかし誰でも受給できるのではなく、「申請に必要な要件を満たすこと」や「審査に通ること」が必要になります。
「補助金」と「助成金」の違いについては、「助成金」は通年申請でき、要件を満たせば受給できるものが多い一方、「補助金」は制度ごとに予算や件数、公募期間が決められていて、審査を通過しないと受給できないものが多いです。
ただし、これらの違いは明確に区別されているわけではありません。補助金と助成金という名称であっても、前述した条件に必ずしも当てはまるとは限らないので、各制度の内容をよく理解したうえで、活用を検討するようにしましょう。
受給する際の注意点
補助金や助成金の制度を利用する前に、以下の注意点を確認しておきましょう。
基本的に「後払い」である
実は補助金も助成金も、基本的には「後払い」のため、受給が決まってからすぐにお金がもらえるわけではありません。
設備投資の完了後など、計画実施後に支給されるため、実際に入金されるタイミングについてしっかり把握しておく必要があります。
法人税・所得税の課税対象になる
補助金や助成金は「収入」とみなされるため、原則として法人であれば法人税、個人事業主であれば所得税の課税対象になります。ただし、受給金額のすべてに課税されるのではなく、受給金額と売上高を合わせた収益から、費用を差し引いた「利益分」に対して課税されることになります。
なお会計上では、受給する権利が確定したときに「雑収入」として計上します。
消費税の返還が必要になることも
補助金・助成金は事業取引の対価としての収入ではないため、消費税がかからない「不課税取引」となります。
一方で、補助金・助成金の対象となった事業に伴う事業経費は、控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能です。その場合、受給した金額から事業経費を差し引くと課税売上はゼロとなり、課税事業者はその消費税に相当する金額の還付を受けることになります。
つまり、国や地方自治体からすれば、補助金・助成金を交付したうえに消費税を還付することになり、その分が重複してしまいます。
これを調整するために、控除対象仕入税額のうち補助金・助成金に係る部分については、返還を求められることになっています。
起業・創業支援を目的とした助成金・補助金
まずは、起業・創業支援を目的とした助成金・補助金を紹介します。
地域に根ざした事業を行うとき
「地域貢献性が高い新事業」に取り組む中小企業者・創業者に対する助成制度です。中小機構と、各都道府県の公共団体・金融機関等が共同出資して組成されています。
地域独自の官民ファンドのため、助成上限額などは各都道府県により異なり、例として「とちぎ未来チャレンジファンド」では助成上限額は300万円、助成率は助成対象経費の2/3以内となっています。
M&Aなどで事業を引き継ぐとき
事業承継やM&Aをきっかけに「経営革新」などを実施する中小企業者や個人事業主に対して、その取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。
補助上限額は500万円以内(廃業・再チャレンジ事業は150万円以内)、補助率は補助対象経費の1/2以内となっています(令和4年度当初予算の場合)。
申請はデジタル庁が運営する電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用します。
UIJターンをして地方で起業するとき
地方での起業や、東京圏からUIJターンにより起業する個人事業主や法人が対象の制度です。
地域の課題解決に取り組む社会的事業を支援するもので、都道府県が支援金を支給します。
助成上限額は200万円、助成率は起業等に必要な経費の1/2相当となっています。
特定の地域で起業するとき
各自治体が地元で起業・創業を行う人に対して、独自に行っている制度もあります。 ここでは、起業件数が多い東京・大阪・愛知を例に、自治体が独自で設けている補助金・助成金制度を紹介します。
都内で創業予定の個人、または創業から間もない中小企業者等に対する助成制度です。
賃借料や広告費、従業員人件費など、創業初期に必要な経費の一部が対象で、助成上限額は300万円、助成率は経費の2/3以内となっています。
なお東京都では「東京都創業NET」というポータルサイトを設け、起業家をサポートしています。
大阪府内で起業または新規事業を行う個人や事業者などに対する補助金です。
補助対象となるのは創業等に要する経費で、補助上限額は100万円、補助率は経費の1/2以内となっています。
大阪府でも東京都と同様、「オール大阪起業家支援プロジェクト」というポータルサイトを設けて、将来の大阪経済を担う有望な起業家を発掘し、成長を支援しています。
こちらの補助金は愛知県内で起業、事業承継または第二創業する個人事業主や事業者が対象です。
ITや新しい技術を活用し、愛知県の地域課題解決を目指す事業にかかる経費が対象で、補助上減額は200万円、補助率は経費の1/2以内となっています。
愛知県でも創業支援・ベンチャー企業の育成に力を入れており、その内容は愛知県のホームページにまとめられています。
国の創業補助金について
以前は、国が設ける「創業補助金(地域創造的起業補助金)」という名称の制度がありました。
しかしこちらの募集は、2018年(平成30年)度を最後に行われていません。そのため各自治体が独自で行っている創業補助金制度の活用を検討しましょう。
事業拡大・整備で利用できる補助金・助成金
次に、販売促進や設備投資などで資金がかかる際に利用できる、補助金・助成金をご紹介します。
販路開拓や生産性向上に取り組むとき
小規模事業者の販路開拓や生産性向上に取り組む費用を支援する補助金です。
対象者は、常時使用する従業員が20名以下(商業、宿泊業・娯楽業を除くサービス業は5人以下)の法人・個人事業主となっています。
補助上限額は原則50万円(共同事業の場合は500万円)で、補助率は2/3となり、公募は通年行われています。
生産性向上のため設備投資を行うとき
こちらは、生産性を大きく向上させるための革新的なサービス開発が対象の支援制度です。
「ものづくり補助金」は通称で、2021年は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」が正式名称となっています。
補助上限額は一般型が1000万円、グローバル展開型は3000万円で、補助率は原則1/2(小規模事業者は2/3)となっています。
申請はオンラインでの手続きとなり、「gBizIDプライム」のアカウントが必要です。なお公募は通年で3か月ごとに行われます。
ITツールを導入するとき
ITツールを導入して生産性向上に取り組む際、経費の一部が対象となる補助金制度です。
補助上限額はA類型が150万円、B類型は450万円で、補助率は1/2以内となっています。
申請はオンラインでの手続きとなり、「gBizIDプライム」のアカウントが必要です。
人材採用に利用できる補助金・助成金
起業時の雇用のほか、事業が軌道に乗り、人材採用を本格化したい際などに利用できる、補助金・助成金をご紹介します。
試用期間を設けて採用するとき
ハローワークや職業紹介事業者などから紹介を受け、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を一定期間試行雇用した際に受け取れる助成金です。
雇い入れる側にとっては、求職者の適性や業務が遂行できるかなどを正式雇用前に見極められる、というメリットもあります。
助成金額は1人につき月額最大4万円(母子家庭の母または父子家庭の父は月額5万円)となっています。
特定の従業員を採用するとき
期間を定めず継続雇用を目的に、従業員を採用するときに活用できる助成金を紹介します。
60歳以上65歳未満の方、障害者、母子家庭の母親などを継続して雇用することで申請できる助成金制度です。
ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により、雇用保険の一般被保険者として継続して雇い入れることが条件となります。
助成額の一例として、60歳以上65歳未満の方を雇用する場合は、助成対象期間1年で最大60万円となっています。
なお、「特定求職者雇用開発助成金」はここで紹介したコースの他、雇用する従業員にあわせていくつかのコースが設けられています。
離職を余儀なくされた労働者を雇い入れる際に利用できるのがこちらの助成金です。
「離職日の翌日から3カ月以内に、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること」のほか、労働者側にも条件があります。
助成金は通常助成で、1人あたり30万円が支給されます(優遇助成は40万円)。
正社員雇用を増やしたいとき
契約社員や嘱託社員を、正社員などに転換または直接雇用する際にはこちらの助成金を活用しましょう。
有期雇用から正規雇用への転換で、1人あたり57万円が支給されます(生産性の向上が認められる場合は72万円)。
おわりに
このように、補助金・助成金は目的ごとに種類さまざまです。ここで紹介したもの以外にも起業家のための補助金・助成金制度はたくさん用意されているので、アンテナを広く張って情報収集しておきましょう。
しかし条件や手続きが複雑なものも多く、すべてを把握するのはなかなか難しいもの。
そこで、資金調達に強い税理士や社労士、中小企業診断士などの専門家へ相談するのも一つの手段です。
なにかと多忙な創業時だからこそ、専門家の力を借りて効率的に事業を始められるように準備しましょう。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!
