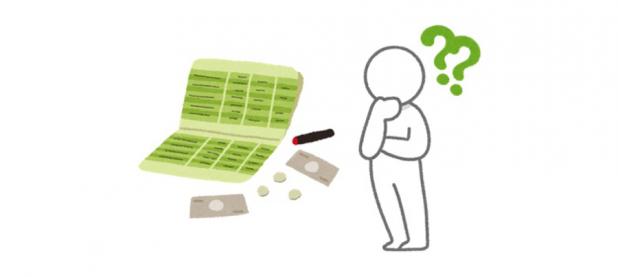相続時に、妻名義の預金が、夫に名義貸しした口座と誤認されないためには
最近、相続トラブルの雑誌記事が巷にあふれており、夫婦間の生前贈与も、よく取り上げられています。
夫の死後、妻(専業主婦)名義の預金が、夫に名義貸しした口座と誤認されないよう、贈与の意思を明確にする贈与契約書などを作成しておくと良いと聞きます。
そこで質問ですが、そのような贈与契約書は、一体、何年間保存しておかなければならないものでしょうか?
たとえば、2x22年に、夫から妻への贈与契約書を交わして、妻名義の預金にATM現金預け入れしたとします。
それ以来ずっと同一口座で、主婦が継続して印鑑・通帳を保管して残高管理していたところ、8年後の2x30年に夫が亡くなり相続が発生して、調査を受けたとします。
このとき、贈与契約書が無ければ、贈与は無かったもの(つまり名義貸しであると)決めつけられても仕方がないものでしょうか?
また、贈与は必ず振込によらなければならないものでしょうか?
私共はまだ若年のため、夫婦間での相続はまだまだ想定していませんが、雑誌記事を読むと色々と不安です。
私共夫婦のいずれが先立つことになっても、せっかくの夫婦間の意思が、死後に誤認されて無下にされる事態は回避したい思いです。
この他、主婦名義の預金が、夫に名義貸しした口座と誤認されないために気をつけるべき点があれば、ぜひ教えて下さい。
税理士の回答

贈与には「書面による贈与」と「書面によらない贈与」の二つがあります。つまり、口頭(口約束)でも、贈与者の「あげる」という意思表示と、受贈者の「もらう」という受諾の両者の合意があれば贈与は成立します。
しかし、相続が起こった後の、過去の贈与についての調査に関しては、贈与者が亡くなっている(つまり、「あげた」ということを証言する人が存在しない)ことが前提となりますので、その証明をするためには、やはり書面で残すことが望ましいと考えます。
贈与契約書の保存期間ですが、これは可能な限り残しておくことをお勧めします。
贈与の事実確認につきましては、贈与された預貯金の資金の出処はどこか、贈与後の管理運用状況はどうか、贈与された資金がどのように使われているか、といった面を総合的に判断して認定されることになります。
従いまして、贈与後の預貯金をそのまま預けっぱなしにしておくのではなく、受贈者の意思で定期預金に預け替えたり、投資信託や株式を購入したり、生命保険に加入したりと、別の運用を行って頂くのがベストな方法といえます。
相続税の税務調査において、家族名義の預金調査は重点項目にもなっておりますので、是非とも実態のある贈与を実行なさってください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年07月14日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。